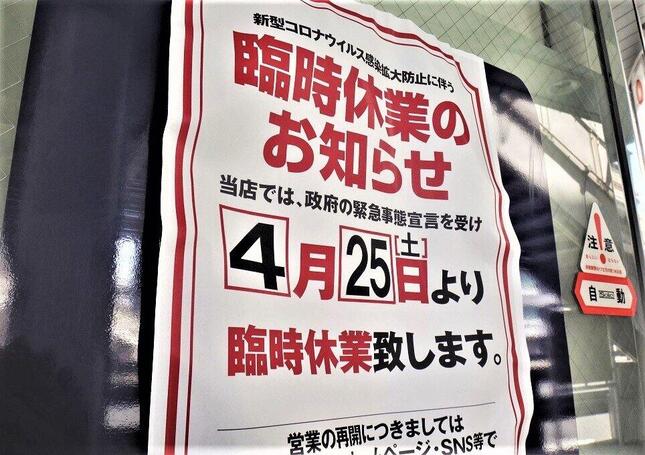週刊朝日(5月8日・15日合併号)の「老親友のナイショ文」で、横尾忠則さんが新型コロナがもたらした「画風」の変化について告白している。
前週と同じ週刊誌、それも同じ号からの引用となるが、ご了解いただきたい。
間もなく84歳の横尾さん。週刊朝日での連載は、98歳になった瀬戸内寂聴さんとの「往復書簡」という贅沢な企画。お二人の文章を見開きで載せ、この作で36回を数える。
「セトウチさん 誰も来ないし、どこにも行かないで終日アトリエのソファーに横たわったままで、週刊誌を読んだり、メールを読んだり、メールを出したり、冷蔵庫の蓋を開けたり閉めたり、描きかけの絵の前に座ったり、立ったりで、一向に描こうとしません」
描きかけというその作品は、三畳ほどの大作で「半ば投げやりの落書きのような絵」「ガサガサしたというか、イライラしたような絵」「作るというより壊すような絵」だという。そして、そんな絵が描きたくなる、描けてしまうのもコロナゆえではないかと。
「コロナは未知の体験へ連れ込まれていく不安と恐怖がありますが、そんな心情が絵にも表れているのかも知れません。だとすればコロナは僕の創作にかなり深く関わっているというか関与しています」
横尾さんの場合、コロナに限らず絵の雰囲気は制作環境に大きく左右されるそうだ。日本で描けば湿気を含みどんよりとなる絵が、ロスの潮風に吹かれて描けば南国的な原色に変わる。今回の作品は「病原菌に取り囲まれた空気からなかなか解放されませんので、やっぱり、コロナが絵の画面の中でパーッと拡大したような絵」になるらしい。
ちなみにタイトルは「千年王国」である。
文明に疑問を持つチャンス
千年王国とはキリスト教の終末論の一つで、キリストが君臨する平和の国。至福の千年が終わると、サタンとの最終戦争を経て最後の審判が待つとされる(ヨハネの黙示録)。
「千年王国がやってくる前に、人類はとことん痛めつけられます。それが今かも知れません...新しい創造の到来の前には、必ず破壊が伴うということはすでに歴史が証明しています...日本は、世界は今、終末時計の刻む音を聴いている真っ最中かも知れませんね」
横尾さんはさらに、コロナは結局「人災」ではないかと筆を進めていく。
「かつてのアトランティスやムーのように文明が極度に繁栄した時にこれらの文明が海中に没したように、コロナも文明の危機を暗示しているように思えてなりません...この辺でもう一度、人類の繁栄を目的にした文明に、疑問を持つチャンスかも知れません」
最後は、寂聴さんが天台宗の尼僧であることを意識したまとめとなる。
「自業自得、因果応報という仏教の思想は今こそ出番じゃないでしょうか。千年王国の夢でも見ます。おやすみなさい...と、ここまで書いて、まだ三行余ってしまいました。もう一度、おやすみなさいと言って寝ます」