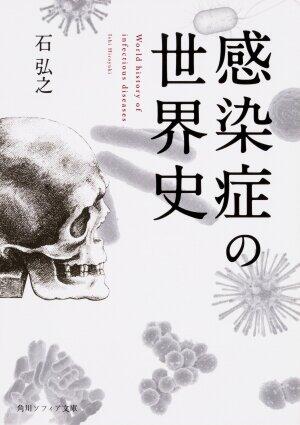■『感染症の世界史』(著・石弘之 角川ソフィア文庫)
新型コロナウイルスが世界中で猛威を振るっている。リーマンショックを100年に一度の危機と言っていたが、このコロナ・ショックは、経済面だけでなく、社会面や生活面にもわたって、これを大きく超えるショックの様相を呈している。当初の風邪と変わらないといった楽観論から、最近の各国の医療崩壊やロックダウンの現実からくる悲観論まで、この数か月、我々は大きく揺れてきた。
本書は、人類誕生の時から現代に至るまでのウイルスとの闘いを解説した一種の歴史書である。著者は、最近にわかに脚光を浴びている感染症の専門家ではなく、アフリカ、南米、東南アジア等で長く活躍した記者であり、「マラリア四回、コレラ、デング熱、アメーバ赤痢、リーシマニア症、ダニ発疹熱各一回、原因不明の高熱と下痢数回・・・」の病歴をもつ強者である。環境問題に携わってきた人でもあり、広い視点から書かれていて、文系の自分にも分かりやすい。
目に見えぬウイルスが世界を変えてきた
コレラ、ペスト、エイズ、エボラ出血熱、風疹・麻疹(はしか)、ピロリ菌、スペイン風邪、インフルエンザと、個々の病気について多少なりとも知識を持ち合わせていたつもりでいたが、本書には、これらを「感染症」として、人類との関わりを体系的に見る面白さがある。
新型コロナウイルスの猛威に直面して未知との闘いが強調されるが、人類はこれまで何度も未知のウイルスと戦い、そして、生き残り、発展してきたのである。その過程では、東西交流の拡大や農業改革に伴う中世のペスト流行(7500万人~2億人)、二度の世界大戦間にその死者を超える8000万人の死者を出したとされるスペイン風邪といった悲劇を起こしている。また、南米の新大陸発見では、天然痘などの流行が現地文明を崩壊させてしまった。歴史上の誰もが知る英雄より、目に見えぬウイルスが世界を変えてきたのだ。歴史書にはメインテーマとして書かれることはないが、人類の歴史は、感染症抜きには語れないといっても、過言ではない。また、最近の遺伝子研究により、人類、そして、日本人のルーツの解明にも一役買っている。