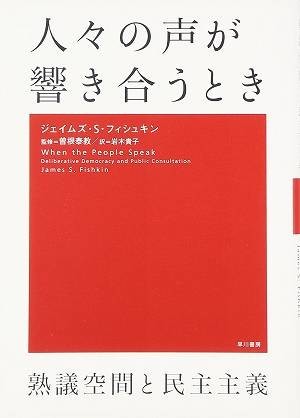■『人々の声が響き合うとき 熟議空間と民主主義』(著・ジェイムズ・S・フィシュキン、監修・曽根泰教/訳・岩木貴子 早川書房)
評者の関心のひとつに、よき集合的意思決定とはどのようなものかという論点がある。この問題が行政官としての仕事に密接にかかわることはご理解いただけるだろう。
集合的意思決定には、大きく分けて、客観性を持つ「正解」を皆で考えるという状況、皆に関わる公共の決定を話し合うような正解が必ずしもはっきりしない状況がある。前者の「正解」の探索については、見解は収れんしつつあるようである。スロウィッキーの『「みんなの意見」は案外正しい』の評でみた通り、多様な個人により、意見が独立して表明される時、集合的決定はばらばらの個人による決定よりもよいものとなりやすい。
客観的な正解がはっきりしない公共の決定はどうか。投票による場合については、坂井豊貴『多数決を疑う』で、票の数え方次第で結果が様々に異なってくることをみた。公共の決定が話し合いで行われる時には、その話し合いを「熟議」という。熟議について、評者は、サンスティーンの『熟議が壊れるとき』を紹介し、熟議はうまくいかないという方向での議論を紹介した。懐疑論はシャピロ『民主主義理論の現在』でも表明されている。シャピロは、マディソンの『派閥の弊害とその匡正策』を取り上げ、マディソンを熟議に代えて利害の均衡を通じた集合的決定を志向したものとして読んでいる。
民主主義で重要なのは「鏡」か「濾過」か
これまで紹介した本は、熟議に対して懐疑的な見解を示したものであった。今回紹介するフィシュキンの「人々の声が響き合うとき」は、熟議の機能について肯定的な立場から書かれた代表的な著作である。
本書の価値は、民主主義に付き物の困難の所在について明快な見取り図を示していることである。住民の生の声を反映する「鏡」のような存在であることこそ、民主主義の要諦であるとの考えがある。一方、生の声の危険性を指摘し、代表を通じた熟議による民意の「濾過」を重視する考えがある。フィシュキンは、この鏡と濾過の対立項のもと米国の民主制の歴史を大局的にみている。フィシュキンは、米国史に濾過を押しのけて鏡の力が強くなっていく趨勢を見出している。
たしかに民意の反映は重要なテーマである。しかしながら、大規模な民主制のもとでは、ひとりひとりの意見が真剣に考慮されることは望み薄であり、そんな時、個人が熟慮した上での意見を持つことはなさそうだ。このような時、生の声がそのまま鏡に反映されてしまうのを傍観するほかないものなのだろうか。
この今日的困難に対し、フィシュキンが持ち出す解決策が「討論型世論調査」(deliberative pool)なるものである。討議型世論調査の手順は、住民から無作為抽出した者により小集団をつくることにはじまる。その小集団に熟議をしてもらい、その後、参加者各人に自分の意見がどうであるかアンケートに答えてもらい、回収する。熟議に際しては、慎重に考慮されたバランスのとれた情報が与えられる。住民に熟慮する機会が与えたならば、きっとこのような意見を持ったに違いない、という意見を抽出するというわけである。そして、政策決定においては回収された意見に考慮が払われる。小集団の構成員が無作為抽出によることは重要な点で、この選出方法が小集団の抱く意見に民意としての正統性を与える根拠となる。
フィシュキンは、北アイルランドのような分断された社会でも、熟議が機能することを数々の実例をもって示している。サンスティーンやシャピロのような懐疑論に対し、慎重に設計された熟議は、満足のいく機能を発揮すると反論するのである。フィシュキンによると、熟議を通じて、参加者の市民としての能力が高まるという。市民としての能力には、公共精神が含まれる。フィシュキンによると、米テキサス州でのエネルギー政策の討議により、節電のために毎月の電力料金があがっても構わないという者が増えたという。我が国でも、2012年に「2030年までのエネルギー政策」をテーマに討論型世論調査が行われたことがある。
現実の政治に熟議の居場所はあるのか
熟議に希望を持ってみたくなるような気もする。しかしながら、実際の政治をみると、米国はいうまでもなく、EU(欧州連合)離脱を巡る国民投票を実施した英国、政党の分極化が進む欧州など、現実政治が鏡への傾斜を強くしていることがいやでも目に入ってくる。我が国でも、消費増税と社会保障改革についての与野党合意が達成されたのは束の間のことで、その後、熟議が政治を動かす場面をみたことがない。
討論型世論調査は手間がかかる。また、無作為抽出によって小集団を選出するとはいっても、大多数の国民からみれば、その小集団の意見がなぜ特権的に扱われなければならないのか疑問が尽きることはない。これらの障害を乗り越えるためには、関係者間に相当の熱意が不可欠である。政権の座にある側からみれば、予め自分たちの期待する結論を熟議がもたらしてくれる保証はない。権力闘争としてみると、幅広い合意を得なければやりたい施策ができないという状況にない限り、わざわざ熟議をして敵対勢力に譲歩し、敵と手柄を分け合う動機は乏しい。我が国での消費税やエネルギー政策についての熟議が、いずれも国会での衆参の捻じれのもとにある弱い政権で試みられたことは示唆的である。
それでも、注意深く設計された小集団による熟議が機能することが示されつつあることの意義は評価されてしかるべきである。小集団の熟議の先例として、フィシュキンは古代ギリシアの500人委員会に繰り返し言及している。この500人委員会は無作為に選出された市民が討議により国政の重要事項(ソクラテスの刑死を含む)を決定するものである。小集団の熟議をこのようなフォーマルな制度として国制に取り込むことができれば、たしかに政治は変わるだろう。しかしながら、そこに至る道はなんとも遠い。
経済官庁 Repugnant Conclusion