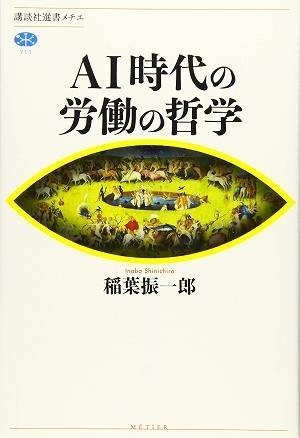■『AI時代の労働の哲学』(著・稲葉振一郎 講談社選書メチエ)
本書は労働の哲学を、AI(人工知能)を素材にして考察したものである。
著者は巷間喧しい「AIに職を奪われる」懸念に対し、まずは「取って代わられることはない」と述べる<第4章>。その指摘は、スミス、ヘーゲル、マルクスのレビュー<第1章>、労働契約や財産権等の法的側面、また産業社会論の検討<第2章>、機械化、AI化による企業組織等の変化や労働に与えるインパクトの検討<第3章>を経たものである。
次いで第5章の冒頭で、AIが技術的特異点(シンギュラリティ)を超え、道具であることを脱して自律的行動能力を獲得し、人間を上回ったとしても、(社会に大変な緊張と紛争を呼び込むだろうが)「市場経済体制、資本主義社会を根本的に変えるとは言えません」と総括する。ここで一旦、AIをコンピューターの延長線上、あるいは資本主義社会の下で人類が発展させてきた様々な機械や道具の延長線上で捉えうることを否定せず、読者をひとまず安心させる。
AIが野生化する可能性
しかしながら、ここからが本領である。
著者は次いで、たとえAIを道具の延長線上に見なし続けられるとしても、自己学習能力・自律性という性格が、我々の思考の基盤となる「人」「物」二分法の図式に挑戦するものになる可能性を想定し、それによる我々の社会観、パラダイムの転換の可能性を論じるのである。
それを導き出す上で、著者は(ツイッターなどの)botを例に議論を始める。botが飛び交うようなネットワークは自律性を兼ね備えた人工の生態系、あるいは「第二の自然」のようだが、人間は、同様の自律性を兼ね備えた動物を「物」に分類し、人間の財産となり、管理の対象とする。一方で人間の中には、動物や自然生態系などを「人」ほどではないにせよ道徳的配慮の対象とする考え方も存在し、その根拠として動物の知性や感受性が持ち出されている。そして単純な動物とのアナロジーが成り立つかはともかく、AIの発展により実現するかもしれない人工知能について、(おそらくはその「知性」を根拠に)「人間と同格の『人格』を備えた存在とは言えず、かといってもはや純然たる道具として扱うわけにもいかな」くなる可能性を指摘する。さらに自律性や自己修復性を有したAIが、人間の管理を離れ、いわば野生化する可能性は理論的には無視できないと述べる。
「人」と「人以外の生物」という区分を考えると
その上で人間社会への哲学的考察に戻る。人間社会では「人」と「物」を別に括ることで、「人」に括られた側での平等、対等性が保障されている。だからこそ「人」の間の不平等が問題になるのだが、二分法を「人」と「物」ではなく「生物」と「無生物」とし、「生物」の中で「人」と「人以外の生物」という区分を考えるとした場合、いわゆる「自然」とは別に、AIが生息する自然生態系のような世界が新たに登場し、そこに相当の知性の存在を見いだす時、人と人との間での区別や道徳的序列への抵抗がさらに少なくなってしまう可能性を示唆する(その帰結は本書をご覧いただきたい)。
仮定を積み重ねた論理であり、近い将来での、それこそ実現の「可能性」について現時点の判断は難しい。とはいえ、「人」「物」二分法の概念を持ち出し、古典古代ギリシャのアリストテレス的構図に遡って論点を抉り出した点に、著者の社会哲学に関する深い研究と思索があり、読者の思考を揺さぶる根拠があると感じた。著者の考察は、今も深層学習を続けるAIに対峙する我々が参照すべき必要な知的営為であると考える。読者の頭には、AIについての考察を契機に、人の本質は何か、人と人以外の生物を分けるものは何か、なぜ人は人であることで尊重されるのか、等々の哲学的問いが巡るだろう。
厚生労働省 ミョウガ