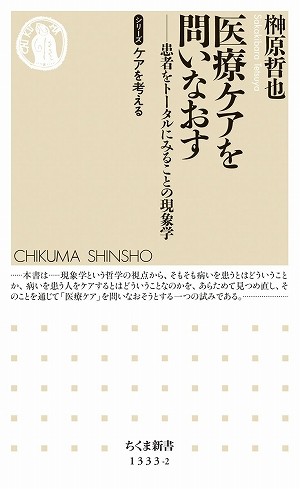■『医療ケアを問いなおす』(著・榊原哲也、ちくま新書)
初夏、義父を亡くした。持病の緊急手術を行い、手術は成功したものの、その2日後病状が悪化し、帰らぬ人となった。
当日の朝から、義母と義兄、妻と4人で病室に付き添った。ICUではなく一般の病棟の個室である。そこでは生命維持装置が無機質な光と音を放つ傍らで、医師と看護師が慌ただしく対応にあたっていた。我々は時に説明を聞き、時に遠慮して狭い病室から離れながら、避けられない時が間もなく来ることを自覚した。
亡くなる1時間前頃、看護師から、バイタルが落ち込みつつあるので、手をさすったり励ましたりして欲しい、という声かけがあった。義兄が時に手の甲をたたきながら大きな声で励まし、妻は涙ぐみながら腕をさすり、義母はただ手を握っていた。
評者は呆然とその様子を見ていたが、亡くなる20分ぐらい前であろうか、看護師が「また、暫くしたら来ます」と私に声をかけ、病室を後にした。その後、計器が示す脈拍や呼吸回数をにらみながらの声かけがしばし続き、義兄の「あー、もうだめか」という声とともに、モニターが直線を示した。
しばしの沈黙の後、評者が看護師を呼びにナースセンターに行くと、医師と数名の看護師が会議机を囲んで座っていた。彼らの普段の慌ただしさにもかかわらず、義父の臨終を待つかのようにただ座っていた様子を見て、評者は、臨終を予測した看護師が、最期の時間を家族だけで過ごさせたい、とわざわざ席を外した気遣いがあったように受け止めた。
今回紹介する「医療ケアを問い直す -患者をトータルに見ることの現象学」は、哲学、なかんづく現象学の専門家である著者が、病を患うことや、病を患う人をケアするとはどういったことなのかを、現象学の視点から問い直したものである。私事を長々と書いたのは、ともすると政策の一分野として、三人称と数字で語ることの多い医療について、そうした側面ばかりではないことを再確認した上でこの本を紹介したいと考えたためである。
患者をトータルで見る視点
著者はまず現象学の世界に読者を誘い(第1章)、続いて現象学の基本を平易に解説する(第2章)。続く第3章、第4章で、いずれも現象学にベースを置いた、(自らの多発性硬化症の患者としての経験も踏まえ研究を行ってきた)哲学者トゥームズと、看護学者ベナーらの所論を踏まえながら、患者をトータルに見る上では、自然科学的な意味での医学的な見方だけではなく、患者が経験している病いの意味の理解が求められること、またそうした理解を実践する上での有効な視点について述べる。
著者の本書での主張は第5章においてまとめられている。そこではまず、ベナーらがさらに展開した、人は「何かが大事に思われ、そのことを実際に実践できて、その実践に肯定的な意味を感じられる」ときに「安らいでいられる」とし、その「安らぎとしての健康」の回復と増進こそが、看護の目指すべきものだという考えを提示する。続いて、「安らいだ在り方」を目指して最後まで患者に寄り添い、「『その人がそう在りたいと思っている在り方でいられるように力を与える』こと」は、看護のみならず医療ケア全般にあてはまる究極の目標ではなかろうか、と述べる。また医療者も患者から「ケアすることでケアされたと感じる経験」を得るものであり、医師も患者も、傷つきやすい、病いを経験しうる人間としての運命を共有する「仲間」である。そうであってこそ医師は患者を「癒す者」となることができ、そのためには患者をトータルで見る視点が重要であると述べる。
現象学的人間観の(ベナーらが提起した)「5つの視点」は、患者観ではなく人間観であると著者が述べていることから、そうした「仲間」には、患者の家族や親しい友人といった存在、すなわち我々一人一人が含まれ得ると、評者は理解した。