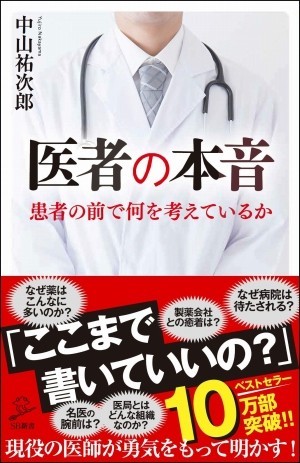■「医者の本音――患者の前で何を考えているか――」(中山祐次郎著、SB新書)
前回本欄で、患者から見た医師・患者関係について解説した本(「賢い患者」岩波新書)を取り上げたが、今回は、逆に、医師の側から見た医師・患者関係などについて本音を綴った本を取り上げたい。
本書の帯に、医師を前にして直接尋ねることがはばかられるような質問が列挙されている。
「なぜ医者の態度はいつも冷たいのか」
「患者の『薬を減らしたい』をどう思うか」
「『様子を見ましょう』という言葉の裏で何を考えているか」
「袖の下は渡した方がいいのか」
「がんの民間療法はこっそりやるべきか」
など
本書では、こうした質問に、医師となって12年目の若手外科医が率直に答えている。序文にあるように、医師が本音を綴った本はいくつかあるそうだが、いずれも引退したか引退寸前の先輩医師が書いたものばかりとのこと。現役医師で、しかもこれから数十年にわたって臨床を続ける予定の若手医師が書いたものはないという。そうした物珍しさも手伝ってか、本書は、昨2018年8月の出版以降、ベストセラーとなっており、既に10万部を突破した。
著者は、若手外科医でありながら、異色の経歴の持ち主。大部分の若手医師が属する大学医局には所属せず、修行を続け、大腸がんの専門医資格を取る一方、福島第一原発近くの高野病院の院長が亡くなり、その存続が危うくなった際には、臨時院長を務めた。並行して著述活動も精力的に行い、本の出版に加え、オンライン上で、連載で医療記事を書いている。
本書では、治療場面での医師・患者関係のほか、「病院ランキングやネットのクチコミは信頼できるか」、「医者の年収」、「製薬会社との癒着は本当にあるのか」、「ナースと結婚する医者が多い理由」、「医者の合コン相手」など、医師の生態にまつわる話まで取り上げられている。
医者の「大丈夫!」は、どこまで当てになるか
患者の立場から見ると、「大丈夫、問題ありません」とか、「もう少し様子を見ましょう」といった医師の一つひとつの言葉が気になるものだが、実際、医師はこれらの言葉をどういつつもりで発しているのか、本書では著者の経験などを基に説明している。
昨年、評者は胆のう切除の手術を受けたが、その際、主治医から言われた「もう大丈夫です」という言葉、とても心強く感じたことを覚えている。
著者も、しばしば不安を訴える患者に対して、「大丈夫!」というマジックワードを使うことがあるそうだ。不確実性が残る医学の世界で、「大丈夫」と断言できる場面など、ほとんどないにもかかわらず、つい言い切ってしまうそうだが、いつもためらいと後ろめたさがつきまとうという。
では、とても「大丈夫」とは言い難い場合はどうするか。
不安一杯の患者を前にして、医学的事実をそのまま述べるべきか、それともこの場は表現に配慮して安心していただき、後で段階的に話をすることにするか。毎回非常に悩むそうだ。
あまりに厳しい場合には、「大丈夫です」とも「大丈夫ではありません」とも言わず、「経過を見ていかないとわかりません。何とも言えません」と伝えるという。
患者にとって、自分の病状を聞くことは勇気の要ることだが、医師にとっても、厳しい情報を、患者にいつ、どのように伝えるのかは難題なのだ。
がん告知――患者が医師に聞くべきこと、伝えるべきこと
大腸がんの専門医である著者は、日常的にがんの告知をする機会があるが、大部分の患者は頭が真っ白になり、思考が止まってしまうとのこと。しかし、その後の検査や治療を効果的に進めていくためには、患者として、以下の3つの質問は主治医に聞いておくべきだという。
(1)その医師は、そのがんの治療に慣れているか(1年で何人くらい担当しているか)
(2)どんな予定で検査や治療を進めるつもりか
(3)患者・家族にできることは何か
(2)や(3)はよくわかるが、(1)は医師に失礼な感じがして、聞きづらいような気もする。しかし、著者曰く、患者のこれからの治療を左右することであり、尋ねることを強く勧めている。
「(この)質問をしただけで怒る医者はやめましょう。(中略)『年間何人そのがんの治療をしていますか』と聞かれたら、不快に思う医者はいるかもしれません。だからといって、不快な感情をそのまま患者さんにぶつける医者はこれから長い付き合いになることを思えば、避けたほうがいいと思います」
もう一つ、著者が強く勧めているのは、がんの「民間療法」はこっそりやらず、主治医に伝えておくこと。
本書で知ったが、がん患者の45%が代替医療を利用しており、月に平均5万7000円を支出しているそうだ。これほど普及している民間療法だが、著者自身、外来で出会うがん患者から代替医療を受けていることを聞くことはあまりなかったという。
代替医療に対する著者のスタンスは、「がんに効くかどうかわからないので、なんとも言えない」だが、患者には代替医療を利用していることをぜひ主治医に伝えてほしいという。そもそも、今、受けているがん治療に影響がある可能性があるし、あまりに高額なものを使わされて、詐欺のようにお金を吸い上げられていることがあるからだそうだ。
医者にとって「死」とは
最終章において著者は、医師にとって、ある意味でタブーともいえる「死」の問題を取り上げ、現場の医者が「生と死」の問題をどう考えているかについて語っている。
人生100年時代の到来が語られる現在、「何歳まで治療を行うべきか」は、医療現場の難題となっているそうだ。
本書では、著者が受け持った90歳を超えた大腸がん患者の事例が紹介されている。心筋梗塞の既往歴があり、糖尿病に加え、腎機能も低下している中で、大腸がんの切除といったリスクの高い根本治療に踏み切るか、それとも、がんは残したまま人工肛門を増設し、腸閉塞を回避するなどの延命治療とするか、悩んだ事例だ。
このケースでは、患者自身に認知症があり、自分では人工肛門の管理ができないこと、また、同居家族にもケアを期待できないといった事情も考慮する必要があったという。
結局、リスクを覚悟して、根本治療に踏み切り、綱渡りながら無事、退院できたそうだが、昨今、こうした事例がどんどん増えてきており、医療現場では、事実上、外科医にその判断が委ねられている状況だという。
超高齢の様々な病気を抱える患者に対し、リスクの高い根本治療を実施するのかどうかについて、誰が、どのような事情を考慮して、判断するのか。プロセスや判断基準を含めて考えていく必要があろう。
そもそも、こうした問いが発せられる根本には、人は最後に必ず死を迎えるという冷厳な事実がある。
では、医師は自らの死を淡々と受け入れられるのか?
著者自身がこれまで見てきた元医師の患者などからすると、日頃、死に慣れている医者だからといって、特別に死を受容しやすいということはないようだという。著者自身も、「上手に受容できるなどという気はしていません。いくらか諦めが早いかもしれませんが、死への恐怖をあまり感じない、というわけでもなさそうな気がしています」と語っている。
それでもこれまで多数の死に関わってきた著者にとって、「人間が死ぬ確率は100%である」は所与の事実であり、医師が何とかできるものではないという。
「病院の現場にいると、時々とてもやるせなくなります。自分の患者さんに圧倒的に押し寄せる死の波を、どうにかこうにかちょっとだけ押し戻した、と思ったら、あっという間に次の波が足元まで来ていた。そんなことばかりです」
「医者は無力です。神様が決めたその人の運命に、その人とともにあらがいますが、まだまだ負け越しです。死をコントロールすることは、医者にもできません。そんな時代に、こういう『人間』という生き物に生まれてきた私たち。どう生きるか、一度考えてみませんか」
「生・死」の境界で働く医師といえども、やはり「人」。医療の限界を感じつつ、苦闘しているのだ。
JOJO(厚生労働省)