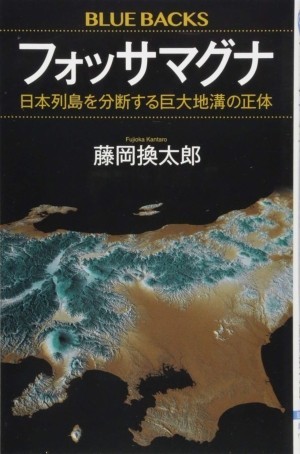■『フォッサマグナ』(藤岡換太郎著、講談社)
その言葉を知ってはいる。だが改めて「フォッサマグナとは何か」と自問すると、ろくに説明もできない。
書店で本書の表題を見かけてふとそう思い、無知を恥じて購入したものである。
本書は、今なお定説がないというフォッサマグナの成立ちに的を絞った概説書である。著者の専攻は地球科学、潜水調査船「しんかい」に51回乗船するなどフィールドワーク経験豊富な科学者という。地に足のついた議論を重ねてこられたのであろう、その御人柄を感じさせる分かりやすい文章が心地よい。
鵺と源頼政
著者は古典にも明るい教養人のようだ。
フォッサマグナを平家物語に登場する怪物「鵺(ぬえ)」にたとえ、これを射落とした源頼政に自らを重ねて、怪物退治よろしく謎解きに挑むのである。
著者のこの比喩、読み始めた当初は、何のことやら大げさだな、と感じたものだ。
だが読み進めるにしたがい、フォッサマグナの「怪物」ぶりが徐々に分かってくる。日本海の成り立ちからして不可思議であることも背景に、世界的にも他に例のないこの巨大構造がいかに複雑怪奇か。遠い小学生時代の「フォッサマグナは、糸魚川と静岡を通る大きな溝だ」というだけの浅い知識が、分厚く上書きされていくのである。
糸魚川静岡構造線はフォッサマグナの西の端に過ぎないこと。東の端は確定できていないこと。フォッサマグナが北部と南部で全く異なる構造になっていること。北部と南部の境界もまた確定できていないこと。
フォッサマグナを鵺にたとえた著者の意図が、こうして浮彫りになってくる。
鵺は、頭はサル、身体はタヌキ、手足がトラで尾がヘビという。フォッサマグナも、単一の構造線ではない。生物にたとえればキメラと言うべき複合的な存在なのである(そういえばギリシャ神話のキマイラの尾もヘビであった)。
そのフォッサマグナがどうして出来上がったのか、なぜ日本にしかないのか。詳細は本書の謎解きに委ねたい。素人である評者にも分かりやすい推論が提示されている。
そこで展開される議論のスケールは、やはり壮大なものになる。
地質学では、100万年を1単位とした年代表記を用いるという。すなわち「Mega annum」の頭文字をとったMaと表記し、1Maが100万年前とされるわけだ。著者は、これこれが生起したのが140Ma、と簡単に記す。だが、それが1億4000万年前を指すと思うと、悠久の時間をかけて大地が動く地球科学のダイナミズムに圧倒される。
自然の偉大さと科学書籍の重要性
読了して、ある種の感慨を覚える。フォッサマグナの成因を通じて、我々が暮らすこの島々そのものが、より立体的に理解されるからである。
恐竜時代に大陸で生じたプレートが横ずれを起こす。地球の奥底の膨大なエネルギーが地殻を切り裂く。島しょを次々と衝突させてくるプレートもある。この過程では、人類が知らない巨大地震や噴火も多々あったことだろう。
たかだか150年の明治維新以来の近代日本というものが、いかにちっぽけな存在かということも、思い知らされる。そして四季美しいこの国土の成立ちを奇跡のようにさえ感じつつ、数百万年後の列島の姿と、そこに暮らす未来の生命に思いを馳せるのである。
ともあれ、久々に手に取ったが、ブルーバックスはやはり素晴らしい。
ブルーバックス「発刊のことば」は、1963年、講談社の野間省一社長名である。「科学をあなたのポケットに」との題を添えた短い文章を読んでみる。
「産業人も、セールスマンも、ジャーナリストも、家庭の主婦も、みんなが科学を知らなければ、時代の流れに逆らうことになるでしょう。」 この節は、科学万能主義の時代を感じさせる。
だが現代は、似非科学とフェイクニュースが大手を振る。野間の警鐘と裏腹に、非科学的な時代の流れにどう逆らうかを考えるべき世相が、一部であれ現出してしまったことは、嘆くべきだろう。
その世相を思うにつけ、科学的思考の重要性を改めて自覚する。分かりやすく研究成果を伝授して下さる多くの著者の方々と、ブルーバックスという自然科学の啓蒙書を連綿と発刊し続けてくれている講談社に、深い敬意と感謝の念を抱く次第である。
酔漢(経済官庁・Ⅰ種)