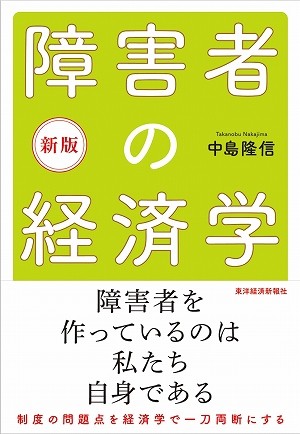■「新版 障害者の経済学」(中島隆信著、東洋経済新報社)
「障害者」をテーマに何かを語ろうとすると、つい身構えてしまうことはないだろうか。ハンディキャップがあるのだから「手助けしなくてはならない」、辛い思いをしてきただろうから「差別的な言動はよくない」等々、あれこれ勝手に思い込んで、壁を作ってしまっているところがあるのではないか。こうした距離感があるがゆえに、障害当事者や家族以外の者が語る障害者論は、つい建前論となったり、どこか表面的なものになりがちな感じもする。
本書は、脳性まひの子息を持つ経済学者が、障害者を取り巻く環境、制度などについて、経済学の視点からズバズバと分析・解説した本。著者はこれまで、「高校野球の経済学」、「お寺の経済学」、「大相撲の経済学」など、ちょっと意外なテーマについて、経済学のアプローチを用いて解説した著作を刊行している。本書は、12年前に出版され、日経・経済図書文化賞を受賞するなど話題となった「障害者の経済学」の新版。前著の後、「障害者総合支援法」や「障害者差別解消法」の制定など、障害者をめぐる社会環境が大きく変化してきたことを受けて、書き改めたものだ。
障害者問題を経済学の視点で切り取るユニークさは無論のこと、障害当事者の家族としてのリアルな実感に裏打ちされた内容は歯切れがよい。その歯切れよさのゆえに、読む者の立場によって受け取る印象は異なってくるかもしれないが、障害者問題を「深く」考える上で、貴重な一冊だと感じた。
障害者問題とは一体何なのか
著者によれば、現行の障害者対策は、障害者をその心身の機能不全の状態に応じて、特別な枠にはめることで、あらかじめ対象者の範囲を確定し、既に決められた支援を行う仕組みだという(医学モデル)。これを著者は「転ばぬ先の杖」と呼ぶ。つまり、一般の人と区別して、転びそうな人(障害者)を事前に決めておき、先回りして「杖」を与えておくというのだ。
例えば、教育分野では、障害児のみを対象とする特別支援学校が設けられ、普通校に通った場合に起こり得る様々な問題(他の生徒やその保護者との摩擦など)を避けている。就労支援の分野では、障害者専用の福祉施設が制度化され、実質的に民間企業同士の市場競争や健常者である一般社員たちとのトラブルから障害者を守るといった役割を果たしている。
こうした障害者を特別枠で対応するアプローチは、「効率的」ではあるが、同時に、障害者の存在を一般の人々から見えにくくしている。それは冒頭に述べたように、障害者との間に、勝手に壁を作り上げてしまうことになる。
結果として、形式的な「差別表現禁止」といった安易な風潮を生んだり、あるいは、「福祉は善行だから」という免罪符となり、就労支援施設における障害者の低賃金に無頓着のままといった非合理な行動を放置することにつながる。
加えて、こうしたアプローチは、今日的な課題となっている発達障害やうつ病など一時的に生きづらさを抱えている人々の場合には、適切な支援とはならないことも多い。必要なのは、弱者としての保護ではなく、これまでと同じレールなり別のレールに乗れるような支援であるからだ。
著者の理解では、障害を心身の機能不全と捉える医学モデルの時代は古くなりつつある。むしろ、本人の機能不全の有無ではなく、社会の側がこうした機能不全を受容できるか否か、生活上の困難さを取り除けるか否かこそが、大事であるというのだ(社会モデル)。
「私たちの社会には、はじめから障害者という特別な存在がいたわけではない。障害者を生み出しているのは私たち自身であるという気づきが、障害者問題に取り組む上での第一歩なのである」
経済学で考えて、気づいたこと
著者曰く、経済学を活用することの利点は、
1. 誰の肩も持たないこと(有限な資源を効率的に配分することにのみ関心があり、常に中立であること)
2. 人を冷静にすること(善悪論にとらわれず、人間の行動の動機や社会の仕組みに着目すること)
3. 物事を一般化すること(障害者問題を特別視することなく、突き詰めて考え、問題を一般化することによって、他の社会問題との共通性に気づくこと)
4. 経済学の理想形たる「完全競争」との対比から障害者対策の非効率性を発見すること
だという。
福祉や教育の関係者は、障害者であることの特殊性を一際認識しており、1~4の発想とは極めて縁遠い。したがって、障害児教育や障害者就労に関する本書の指摘は、新鮮であると同時に、手厳しく感じられるのではないだろうか。
以下、評者が本書において、強く印象に残った指摘を2点、取り上げる。
(1) 障害児教育が果たす使命とは何か――就労支援はミッションなのか?――
近年、東京都では、特別支援学校の高等部に、就労率100%を目指す課程の設置を進め、就労率9割以上という成果を挙げている。一見、望ましい取り組みにも見えるが、著者は、こうした風潮の中、障害児向けの受験塾が登場している現状を挙げ、公の教育機関として適切な姿なのかと批判する。 むしろ、本来の教育とは、神奈川県の県立高校で実施されているインクルーシブ教育(障害の有無にかかわらず同じ教育を受ける)のような取り組みではないかと指摘する。学校は、就職準備機関ではなく、子どもたちの可能性を引き出し、伸ばすものだという主張だ。
特に、教員配置が手厚い特別支援学校は、生徒1人当たりの教育費が年額725万円と、普通校の7~8倍にもなっている。これほどのコストをかけている特別支援教育の場で、企業経験のない教員が慣れぬ就職支援を行うことは非効率だというのだ。
専門高校などの存在を考えると、教育機関のミッションに就労支援は含まれていないと考えるのは早計であろうが、特別支援学校の使命を曖昧にしたまま、就労支援を行うことは、教員配置の在り方をはじめ、資源の効率的な配分という観点からは望ましくないであろう。
加えて、障害者教育のみならず、高等教育全般において、就職や就労支援が大きなウェートを占めている日本の状況を顧みると、教育とは一体何なのか、どうあるべきなのかが問われているようにも思う。
すべての人にとって地続きとなるテーマ
(2) 障害者雇用の義務付けはどこまで有効か
法律上、企業には、障害者の雇用が義務付けられているが、大企業を中心に、特例子会社を設け、障害者の雇用を行い、グループ会社内の軽作業を集約し実施している企業が増えている。こうした特例子会社を通じた障害者の雇用は、一見、有効な対策に見えるが、同時に課題もある。
規制をクリアするために、本来は外部委託するなどして効率化すべき社内業務を温存するなど、特例子会社が「企業内障害者施設化」するリスクが高まっているというのだ。
そもそも中小企業では、障害者を雇用して担わせるほどの軽作業はなく、むしろペナルティーとしての納付金を払った方がいいというところも多い。このまま雇用の義務付け(法定雇用率)を強化していく政策には限界があるのではないかというのが著者の見立てだ。 著者曰く、現行以上の法定雇用率の引き上げに当たっては、福祉事業所に仕事を委託することで、その仕事量に応じて、雇用したとみなす仕組み(みなし雇用)を一部認めてはどうかという。
障害者の支援に慣れていない企業が無理をして障害者雇用を増やす必要がなくなるし、仕事の確保に困っていた福祉事業所は、受注が増え、障害者に支払う賃金を引き上げることが可能となるというのだ。
このみなし雇用制度には、仕事を福祉事業所に発注すれば事足れりといった、企業側の障害者雇用意識の後退を招くのではないかといった懸念もある。他方、障害者が担いうる仕事が福祉事業所に集約され、そこでの待遇改善につながるほか、発注した企業の生産性の向上に資する可能性もある。
著者のこの提案は、一般企業と福祉事業所が、それぞれ自らの得意分野(企業は生産活動、福祉事業所は障害者の就労支援)で力を発揮することで、全体の効率を高めようという、経済合理性を踏まえた戦略である。この筋書き通りに事が運ぶかどうかは、慎重な検討が必要であろうが、興味深い提案である。
このように、障害者問題を経済学の視点で考えるというユニークな試みは、新たな気づきを与えてくれる。しかもそれは、障害者問題が決して特別な問題ではなく、すべての人にとって地続きとなるテーマであることを教えてくれるのだ。
著者は、本書の結びでこう語る。
「私たちに必要なのは、障害者に映し出されている社会の姿に気づくことである。これは障害者から学ぶといってもいいだろう」
JOJO(厚生労働省)