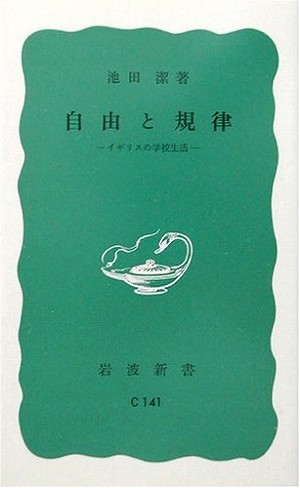■『自由と規律』(池田潔著、岩波新書)
英国パブリック・スクールでの生活を活写した往時の名著が復刊したと聞いたのは、数年前のことであったか。 子供の教育の参考にとふと思い出し、高校時代以来、久々に再読するべく新たに購入した。奥付を見ると、1949年第1刷発行、2018年2月には第109刷とあるから驚く。ロングセラーとはこうしたものを言うのだろう。
強烈なスパルタ式教育
英国におけるパブリック・スクールとは、「イギリス支配階級子弟の教育機関」(本書P9)であり、「私立であること、全校寄宿制度であること、この二点を欠くべからざる前提条件」(同P20)とした中等教育校(日本の中学・高校の期間に相当)である。
私立学校がなぜ「パブリック」の名を冠するかなど詳細は本書に譲るが、オックスフォード・ケンブリッジの両大学への進学者が多い事実や、イートン、ハローといった具体の学校名などは我が国でも有名であろう。
著者をして「スパルタ式教育」と言わしめるその教育内容は、現代日本では想像がつかないほど峻厳だ。
真冬でも開け放した窓、毛布は夏一枚冬二枚、「朝、目が覚めると毛布の裾に薄く雪が積もっていることがある」などと書かれれば、その生活はおよそ想像がつこうというものだ。現代はさすがにそこまでではなかろうが、粗食に耐え、厳しい校則に呻吟することに変わりはあるまい。そうした枠内にあっても、思想の自由が保障されているところにパブリック・スクール教育の妙味がありそうである。
輝かしい将来が約束されていることを念頭に置けば、厳しい規律はある種のバランサーとして作用する。だが、それは功利主義的なバランスではない。こうした環境で育まれる真の「ノブレス・オブリージュ」(高貴な者が果たすべき義務)が、如何なる自己犠牲と高貴な精神の発露に結実するかもまた、本書は詳らかにしてくれる。そこからは、規律が義務の履行を呼び、これが勇気を育み、その勇気が真の自由をもたらす、そうしたサイクルが見て取れる。著者の本意とは異なるかも知れないが、ここで規律(在学中)と自由(社会での活躍)のバランスが想起されるのである。
日本社会への異議と英国への憧憬
翻って我が国を見れば...などと、評者は言うつもりはない。
この国の中等教育にも見るべきものは多々ある。不登校が自死に至るくらいであればフリースクールも良かろう。大学合格の実績を競うも良かろう。受験から超然として独自の教育を施すもまた良かろう。パブリック・スクールの画一的な伝統墨守ぶりと比べれば、日本の私立高校の多様性は、市民の多様性を生み出す装置として寿ぐべきものと評者は思う。
だが著者は、戦後民主主義の揺籃期に立ち会った大学教授として、彼我の違いから、日本の教育ではなく、世情そのものを指弾する。
戦後の急進的な労働運動がどのような経緯を辿り現在に至るかを知る後世の人間としては、その時代の知識人の闘いを桟敷席から観覧しているかのような感覚を抱く。時に遠慮会釈なく切り込み、時に英国紳士的に嫌みのない皮肉を込めるその文章は、イギリス文学者たる著者の面目躍如というべき本書の味わいとなっている。
著者の日本社会への異議は、英国への憧憬とシンプルな対をなす。それだけであれば表層的な自国批判にも思えようが、そこに青春期を過ごした学校生活への懐かしさが重なり、透明感ある美しい描写が展開されることで、批判のトーンが上品に和らぐこともまた本書の際立った特徴である。
著者は、鮮烈な思い出の光の中で、生徒たちが黙々と伝統行事に従事する様を回想する。そこで「民主的でない!」と異議を言わぬことがいかに当たり前かを静かに諭す文章は、戦後の狂騒が(時代として止むを得なかったものとは言え)如何に無秩序かつ粗雑であったかを振り返らせる不思議な力を宿している。
こうした書籍がロングセラーとなり、読み継がれてきたことそれ自体が、我が国のサイレント・マジョリティーの良識を示すものではあるまいか。朝鮮半島情勢が流動化している折、左傾化した隣国市民の境遇を憂慮しつつ、先人の労苦に深謝し、そして我が国市民社会の健全なることに静かな祝意を覚えるのである。
酔漢(経済官庁・Ⅰ種)