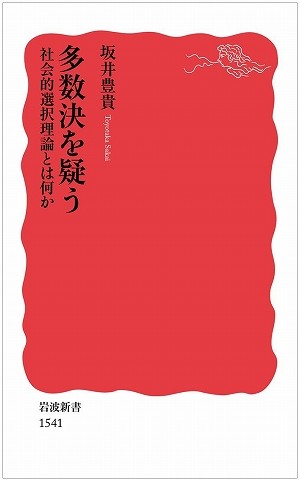■『多数決を疑う 社会的選択理論とは何か』(坂井豊貴著、岩波新書)
多数決に代替する投票ルールを分析
たいていの場合、ひとはいまある制度を所与のものとして、いかに振舞うか知恵を絞る。自分にどのような選択肢があって、なにが許されていないのか、事実としての認識はしても、その理由をいちいち問うとは限らない。このことは行政官でも変わらない。政治的正統性の源泉である憲法、その憲法のもと法律で定められた選挙を経て形成される政治的勢力のもとで、技術的問題の処理に向けて、時には創造的に、また別の時には惰性に流されるままに取り組む。
『多数決を疑う』は、このような日常の営みから一歩退いた地点から、なにが正しいのか、そのこと自体を決める制度上の取極めについて、社会選択理論という数学的に厳密な形式を持つ学問によって考察したものである(同じ著者による同じ内容を扱った『社会的選択理論への招待』が数式を含むのに対し、本書は数式を使わず、一般の方にも手に取りやすいものとなっている)。
多数決がサイクルを帰結しうることはつとに知られたことであるが、多数決の不具合として著者が挙げるのは、なによりも「ペア敗者」を選びうることである。ペア敗者とは、選択肢のなからペアごとに組んで投票した場合、ペア間の投票すべてで敗れる者のことであり、多数決はこのペア敗者を勝者にしてしまう欠陥があるのだという。
本書では、ボルダ・ルール、コンドルセの方法を中心に多数決に代替する投票ルールの性能の分析がおこなわれている。総合的にみて、本書はボルダ・ルールに好意的であるように読めるが、その理由としては、極端な見解を持つ者を抑えることが期待できることや、論理的に全員一致にもっとも近いものがボルダ・ルールであることなどが挙げられている。話の筋としては、コンドルセの方法から発展的に論じられている、陪審定理やアローの不可能性定理の議論は蒙を啓くものがあり、高い社会的価値を有するものである。ただし、コンドルセの方法は、社会にとってなにがよいか、個の考えを集計する過程として投票を理解するという、相当現実離れした想定が置かれており、この方法の実装を図ろうと読者がお考えになるなら、注意深い検討が必要となることを申し添えておく。