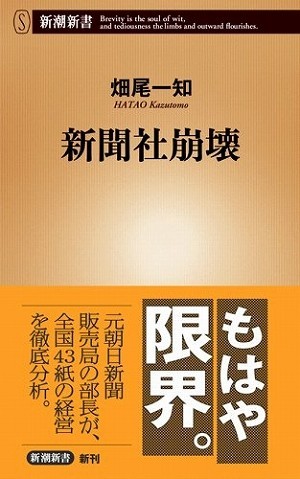■「新聞社崩壊」(畑尾一知著、新潮新書)
評者は、就職以来、30年以上にわたって、新聞を欠かしたことがない。評者にとって、新聞は仕事上の必要性はもちろんだが、世の中の動きだけでなく、人生を知る最大の情報源である。朝、目が覚めると、玄関脇のポストに新聞を取りに行き、夜は、就寝前に夕刊2紙に目を通す。新聞に費やす時間は、朝と夜を合わせて1時間近くになろう。新聞のない生活は考えられないから、新聞休刊日は耐え難いほど退屈だ。
しかし、4人家族の我が家において、新聞を熱心に読んでいるのは評者のみ。妻は1面を一瞥し、そのままテレビ欄へ。社会人と大学生の二人の娘に至っては、ニュースはスマホで知るものであって、新聞を手に取ることはない。たまに評者が出張から帰ってくると、午後、配達されたダイレクトメールとともに取り出されたらしい朝刊が誰も読んだ形跡がないままに、回収袋に入れられている始末である。
こうした事情は、どうも我が家だけではないらしい。21世紀に入って以降、急速に、新聞を購読する人が減っており、新聞業界が危機に瀕しているというのだ。
本書は、そんな新聞業界の実情を、元朝日新聞の販売局の部長が全国43紙の経営を分析し、これまで綿々と続いてきた宅配新聞のビジネスモデルが厳しい状況にあることをレポートしている。
新聞をこよなく愛する評者にとって、認めたくない現実がそこに描かれている。
10年間で読者は1300万人減少、2025年までに更に30%減る見通し
本書で初めて知ったが、NHKの放送文化研究所は、毎年、新聞を読む人の割合を調べているそうだ(国民生活時間調査)。これによれば、2005年の新聞読者は国民全体の44%であったが、10年後の2015年には33%にまで減少し、今や国民の3人に1人しか新聞を読んでいないという(2005年比で1300万人の減)。
新聞を読まぬ我が娘たちのように、20代の落ち込みは激しく、18.5%→5.5%と3分の1に減っている。仕事上、必要があると思われる中年層の読者も急減しており、過半数を超える者が新聞を読まない状況となっている(40代は45%→22%、50代は58%→39%)。
新聞離れの傾向に加え、今後、人口減少が本格化すると、2025年には、2015年と比べて30%、人数ベースで1100万人減る見通しだという。しかも、この推計は、これまでのトレンドをそのまま伸ばした場合の想定であり、仮に、デジタル化が更に進めば、もっと減る可能性が高いそうだ。
こうした読者減の影響は、新聞社の経営にも大きな影を落としており、新聞協会のデータによれば、業界全体の売上合計額は、2005年の2兆4000億円から、2015年には1兆8000億円と、25%も減少している。
著者の推計によれば、このまま2025年まで推移し、部数が業界全体で30%減ったと仮定すると、営業利益率はマイナス20%もの水準になってしまうという(2015年段階ではプラス3.7%)。
新聞販売店への影響も深刻
筆者は、朝日新聞に38年近く勤めた経験を持つが、新聞記者ではない。その大半を販売局に席を置いており、本書は、いわゆる新聞編集ではなく、新聞販売の視点から書かれている。したがって、紙幅の多くが新聞社と販売店の関係に割かれている。
日本の新聞販売の最大の特色は、戸別配達だという。毎日、4200万部の新聞が発行されているが、このうち95%の新聞が宅配されている。全国に1万6000の新聞販売所があり、30万人の配達スタッフが働いている。今では、中高生の「新聞少年」は姿を消し、家庭の主婦や別に本業を持つ人が多いそうだ。何と、新聞奨学生の応募者が激減し、近年の主流は中国・モンゴル・ベトナムなど海外からの留学生だという。
新聞読者の急減は、販売店の経営にも打撃となっており、配達スタッフは、ピーク時(1996年)の48万人から4割近く減った。さらに、新聞社の経営環境の悪化は、専売制・テリトリー制の下、立場的に弱い販売店にとって、残紙(販売店が抱える配達されない新聞)の増加という形でのしかかる。不幸なことに、この残紙問題をめぐって、新聞社と販売店の間で訴訟(いわゆる「押し紙裁判」)となるケースが増えているという。
筆者曰く、「販売店から提訴されること自体が、新聞ビジネスモデルの破綻の表れ」であり、「発行本社が裁判に至る病根を断ち切らなければ、つまり残紙を解消しなければ、新聞社に未来はない」と指摘する。
毎月、週末になると、我が家に販売店のおじさんが集金にやってくる。先週末も、夕方にやってきた。
「いつも、ご購読いただき、ありがとうございます」
愛想よく、お礼を言ってくれる。
ちょうど、販売店の様々な辛苦が書かれた本書を読み終えたばかりだったから、評者も、大変恐縮して、「いや、こちらこそ、本当にありがとうございます。いつも、じっくり味わって読ませていただいています」と頭を下げた。
雨の日も雪の日も、毎朝夕、我が家まで新聞を届けてもらえるなんて、実に贅沢なことなのだと、しみじみと感じた。
新聞が生き残っていくために
著者の言葉を借りれば、「今の新聞社は薄氷の上を渡るソリのようである」
世界に目を転じて、既存の新聞社の中で、デジタル戦略で業態転換に成功しつつあるのは、米国のニューヨーク・タイムズ(NYT)だという。NYTの紙の購読者数は、2011年から2016年の5年間で、103万部から57万部へとほぼ半減したが、デジタル版はこの5年間で60万部から185万部へと3倍に伸びた。
一見、大成功にみえるが、料金は4週で紙が6800円、デジタル版が1600円と4倍以上違うほか、紙の広告収入が激減した結果、トータルでみると、売り上げは2割、営業利益は3割落ちたという。
つまり、デジタル版への転換がうまくいったようにみえるNYTでも、経営的には苦労しており、著者は、日本の新聞社でこうしたデジタル版への転身を成し遂げることができるかについて、懐疑的である。
筆者曰く、日本において、紙の新聞が消えて、それがそっくりデジタル版へと移行するとは考えられないという。おそらくは、新聞社のニュースサイトにアクセスするのではなく、大多数は、Yahoo!などの大手プラットフォームに寄っていってしまうだろうと予測する。つまり、新聞社は、ニュースを取材、制作、整理し、こうしたプラットフォーム会社に納入する存在になってしまうというのだ。
筆者によれば、紙の新聞がなくなってしまったら、以下のような事態が起こると懸念している。
(1)世に出るべき情報が埋もれる(調査報道が行われなくなる)
(2) フェイク・ニュースが出回る(裏付けがないまま発信される)
(3)常識的な世論が形成されない(同種の意見ばかりが取り上げられ、多様性を欠く)
(4)ニュースの重要度が均衡を欠く(芸能・スポーツが重視され、政治・社会関連記事が軽視される)
(5)興味深い記事がなくなる(訓練されたプロのジャーナリストの記事が減る)
こうした事態を回避するために、著者は、人件費の大幅カットなどによって徹底的な低コスト化を図り、購読料を値下げして、読者を増やすという改革を提案している。
具体的には、
(1)値下げ(新聞代は高くなりすぎた)
(2)夕刊廃止(新聞の閲読は1日1回で十分)
(3) 紙面のコンパクト化(20ページで十分、紙面サイズもタブロイドとする)
(4)顧客の集中管理(販売店での顧客管理を止め、新聞社が直接管理へ)
(5) 流通の合理化(取材や編集業務以外はすべて外注化)
(6)人件費の抑制(記者の給料も大幅カット)
(7)販売店の多角経営化(新聞以外もデリバリー、地元企業の販促、ローカルビジネス)
を挙げている。
著者の基本認識は、この半世紀、新聞業界は、恵まれた環境の下で、高コスト構造に陥り、消費者軽視の傾向が浸み込んでしまったというのだ。事業再生ファンドなどにより、既に破綻している新聞のビジネスモデルを根本的に再構築する必要があると指摘する。
未来の新聞の姿は?
確かに、新聞代が安くなることは大歓迎だ。安くなれば、紙の新聞の購読者の減少スピードも落ちるであろう。
とはいえ、今日、日本の新聞業界に起きている現象は、「人口減少」と「デジタル化」による圧倒的な需要減である。コスト削減のみで、こうした現象に立ち向かうことには無理があるように思う。
紙の新聞を愛する評者としては、今後とも宅配される新聞をじっくり味わうことができる環境が永続することを希望したいが、果たして、それは記者の人件費をカットすることによって実現されるべきかどうかは、疑問がある。やはり高品質の記事を読みたければ、優れたジャーナリストが参加する環境が必要だと思うからだ。
メディアにとって、何よりも大切なことは、記事の中身であろう。内容のある記事が提供されるということであれば、紙の新聞への執着は諦めて、デジタル版であっても我慢するか、あるいは紙の新聞が読みたければ高い料金を負担することもやむを得ないかもしれない。兎にも角にも、読むべき記事が書かれ続ける環境を維持していくことが必要だ。
と同時に、より多くの人々に読んでもらうようにすることも重要だろう。
前述のように、新聞がなくなると、フェイク・ニュースが出回るなど困った事態も懸念される。新聞離れしてしまった我が娘たちが、読むべき記事を見落とすことなく読むようになる新たな環境を作り出していく努力が必要だ。おそらく、それは紙ではないかもしれないけれど・・・。
JOJO(厚生労働省)