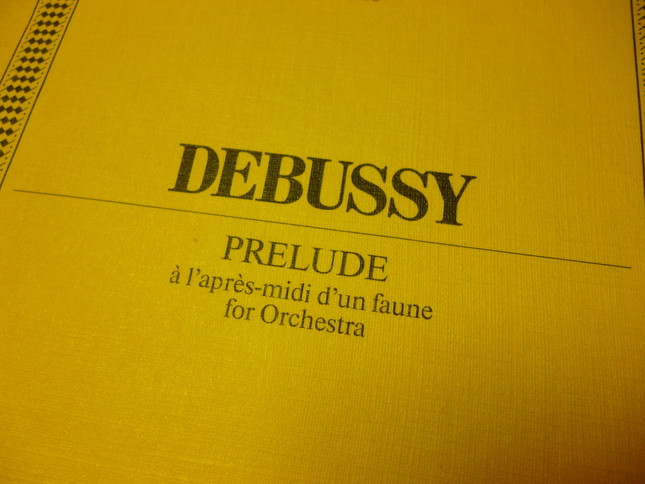先週に続いて、フランスを代表する作曲家、クロード・ドビュッシーを取り上げます。
彼が亡くなったのは1918年の3月25日、つまり、今年が没後ちょうど100年のメモリアルイヤーにあたるということで、世界中で、彼の作品のコンサートが開かれています。
今日取り上げるのは、単独の管弦楽作品、演奏時間は10分ほど、決して長い曲ではないのですが、フランス音楽と、クラシック音楽の歴史を大きく変えた彼の出世作、「牧神の午後への前奏曲」です。
「漠然としている」と批判
パリ音楽院に在籍の時代から、彼の作品は、「漠然としている」と批判を受けることが度々ありました。19世紀前半を支配したロマン派音楽の「感情をよりオーバーに表現する」という作曲法と明らかに違う自分の表現への欲求を、実感し、それを曲に反映させようとしていたからでした。それは、音楽院を終える年に受賞した若手作曲家の登竜門である「ローマ大賞」を受賞して、その副賞としてのイタリア2年留学をしても変わりませんでした。彼は、「クラシック音楽の発祥地」であるイタリアでさえ、さっぱり気に入らなかったのです。
一方、19世紀中盤からヨーロッパを席巻したドイツのワーグナーの音楽には、若いころから傾倒していたことは、前回のコラムに書いた通りでしたが、それは、ワーグナーの作品・・主に「楽劇」と呼んだオペラ作品の数々が、それ以前のクラシック音楽で成立した和声法、ハーモニーの作り上げ方を究極まで推し進めた「進化」を持ち味としていたからかもしれません。
しかし、パリに帰ってきたドビュッシーは、象徴派の詩人や、画家たちとの交流を持ち、一方で、ワーグナーのオペラの総本山ともいうべき、ドイツ・バイロイトの訪問を果たした後、ついに自分の中の美学に忠実な音楽を創り出すことに成功するのです。
音楽技法的に言えば、それは和声法の解体、ともいうべき書法でした。つまり、ドビュッシーは、彼以降、主に20世紀のクラシック音楽が成し遂げる伝統的調性からの脱却をいち早く先取りした、といってもいいのです。
それも、「調性を解体しよう」という一種の計算が働いたからではなく、あくまでも自分の「美しい」と思うもの、人からは「曖昧模糊」と言われた独特の世界を描きだそうとする中から生まれた作品でした。
初演時から大評判に
象徴派の詩人、ステファヌ・マラルメが書いた「半獣神の午後」という詩に啓発されたドビュッシーは、この詩に対する3部作の音楽を書くことを思い立ちます。結局は、第1部の「前奏曲」しか完成しなかったのですが、1892年から1894年にかけて書かれた曲は、それまでの伝統的クラシック音楽から脱却した「新しいドビュッシー」もしくは、「真のドビュッシー」の姿を示しており、彼の出世作となっただけでなく、近代音楽史の転換点となったのです。
物憂げなフルートソロで始まるこの曲は、聴く人々にマラルメの詩の世界、ギリシャ神話にモチーフを得た、けだるい午後を確かに「感じさせること」に成功し、この曲は初演時から大評判となります。その後、彼自身によるピアノ2台の編曲や、パリで人気となったロシア・バレエ団の音楽として使われることによって、ますます人気を得、近代フランス音楽と、クラシック音楽の重要作品として歴史に名を刻むことになりました。
長調・短調といった伝統的なハーモニーや、それまでのさまざまな様式から自由になった革命的なこの曲は、当時の人々にも、そして100年後の我々の耳にも、いまだに「新しさを感じる詩的な風景」を届けてくれています。
本田聖嗣