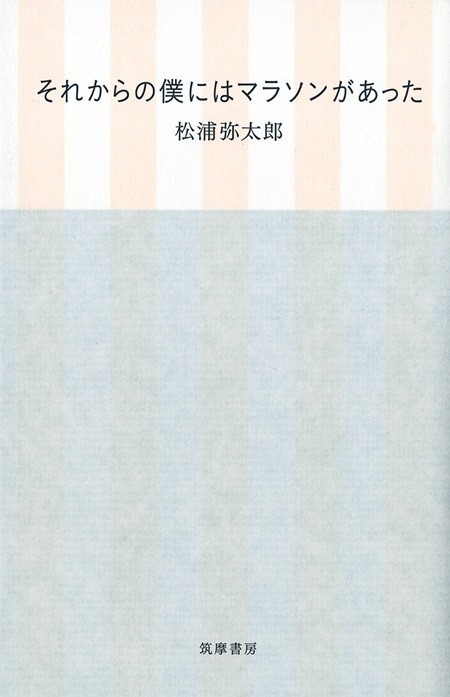■「それからの僕にはマラソンがあった」(松浦弥太郎著、筑摩書房)
評者の数少ない趣味は、「ランニング」である。海外勤務から帰国した際に、人間ドックの結果に驚愕して、近所の公園を走り始めたのがきっかけだが、子育てを終えた昨今では、自由になる時間の大半をこの趣味に費やしている。
以前、本欄で、池井戸潤の「陸王」を取り上げたが、昨年暮れ、ついにテレビ化され、毎週、日曜の夜が待ち遠しくてたまらなかった。凋落著しい足袋屋の立て直しを賭けた中小事業主の挑戦と、ケガのために箱根駅伝以来のライバルに大きな差を付けられたランナーの再起を賭けた挑戦が重なり合って進む物語に、作り話とは思いつつも、感涙を抑えられなかった。
「陸王ロス」ともいえる心境で迎えた年明けは、何はともあれ箱根駅伝。目が行ったのは、4連覇した青山学院大学の走りよりも、むしろ、他大学の4年生たちの力走。特に、早稲田大学のアンカー(谷口)は、最初で最後の箱根駅伝、一度は、後続に2秒差まで迫られながらも、粘り抜き、最後に東海大を抜いて、早稲田に3位をもたらした。最後まで諦めなかった者に祝福が与えられた瞬間に思わず感動した。
「マラソンには人生がある!」
そんな心境の下で、手にしたのが本書。雑誌「暮らしの手帖」の編集長として、その立て直しに貢献したことで有名な著者が、マラソンを始めたわけ、そして、今や、走ることが生活に欠かせない一部となっていることを語るエッセイである。「陸王」や箱根駅伝のような「熱量」とはちょっと違うけれど、マラソンが教えてくれる人生を語っている。
走ることで、支えられた
現在52歳の著者が走り始めたのは、暮らしの手帖の誌面の刷新を任されて3年が経った9年前。がんばっても成果が出ない中で、睡眠障害、そして帯状疱疹と、心身に支障が出始め、ついに心療内科を受診し、薬を処方してもらった時のことだ。
「僕はどうしても薬を飲む気になれなくて、ぼんやりと『さて、どうしたらいいのかな』と思っていました。『仕事が忘れられるような、現実から少し離れられるような、ストレス発散とでもいうようなことをしてみたらいいかもしれない。でも何がいいんだろう』と思いをめぐらしていたときに、ふと頭をよぎったのが、『ちょっと走ってみようか』ということです」
もともと運動好きの著者だったが、最初は300メートル走って、辛くなって止まってしまった。しばらく休んで、また走る、を繰り返したという。それでも久しぶりに、心地よい汗をかいた。
「ああ、体を動かして汗をかく――そんな簡単なことを、僕はずっと忘れていたのだな」
それからは、とにかく毎日、走った。走るのは辛く、苦しくても、本能的に走るのを止めてはいけない、続けていないと自分の抱えている問題を根本から解決することができないという気がしていたという。
走り続けているうちに、300メートルが3キロとなり、やがて45分間で7キロを走るといった具合に、距離も延びていった。自分のライフスタイルの中に、走ることが組み込まれ、走ることがあるから、いつも機嫌よく過ごせるようになったそうだ。
評者自身を振り返っても、月イチのランニングがマラソンへと発展した背景には、仕事の重圧や家族の病気など、己を突き動かす事情があった。マラソンを趣味とする者の中には、こうした止むにやまれぬ状況を契機として、走ることに目覚め、いつの間にか日常に欠くことのできない習慣となってしまった者も多いのかもしれない。