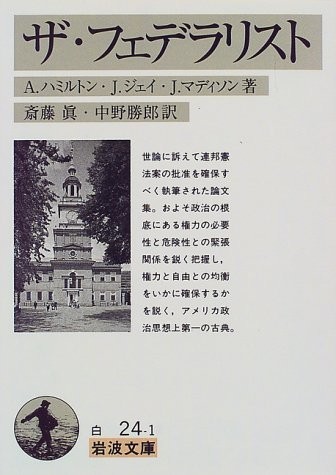■『派閥の弊害とその匡正策』(『ザ・フェデラリスト』収録)(ジェームズ・マディソン著、岩波書店)
本著はアメリカ合衆国建国の父のひとりマディソンの手によるもので、各州による合衆国憲法批准の過程で、批准推進の立場から書かれたペーパーを集めた『ザ・フェデラリスト』(1788年)の第10篇にあたる。
「派閥の匡正策」と聞いて、読者の多くがイメージするのは、派閥の解消であろう。派閥のない、歪みのない空間での理性的な熟議を通じた決定を理念とするものである。しかしながら、本著でマディソンは、派閥の原因は除去しえないものであるとし、むしろひとつの派閥が支配的にならないように、他の派閥によって対抗させるという処方箋を示すのである。「野望には、野望をもって対抗せしめなければならない」。別著でのマディソンの言葉である。
マディソンが気づいたもうひとつの可能性
弱い大統領というアメリカの統治機構の要はこのマディソンの考えの延長上にあるものである。そして、トランプ政権においてアメリカは、(歴史上幾度目かの)その真価が問われる時機を迎えているわけであるが、そのことはとりあえず本評の主旨ではない。
評者自身を含めて戦後の民主的教育を受けてきた人間は、どうしても透明な熟議さえ実現できるのなら、よりよい決定が行われるに違いないと考えがちで、少なくとも建前ではそうした態度を取るものだ。そこには熟議のほかに採りうる途がないという諦念もあるだろう。熟議に失望しても、卓越した指導者にすべてを委ねようと、現代では誰も思わない。成績優秀なテクノラートに任せよう、とは、いまどき霞ヶ関のサラリーマンでさえ考えないだろう。
ただ、実のところ、そんな指導者やテクノラートがいなくても、もうひとつの可能性があることにマディソンは気づいていた。その可能性とは、構成員が私欲、思惑のまま振舞うとしても、利害の均衡を宜しくはかる制度、アーキテクチャをデザインすることであり、18世紀にそうした設計思想によってつくられた制度がいまだに生きながらえているのである。
ところで、評者はいま熟議のなにに失望しているのだろうか。
それは、熟議(あるいは熟議を支えるべき理性)が、いまだ生まれていない未来の人間に対して、著しく鈍い感度しかもっていないことについてである。
経済官庁(課長級) Repugnant Conclusion