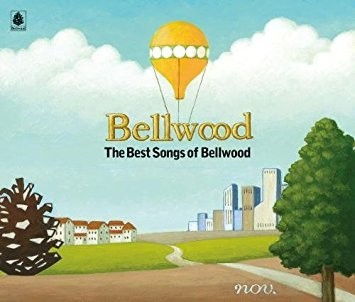タケ×モリの「誰も知らないJ-POP」
キャリー・オンという言葉がある。
直訳すると「一度は中断したものを再度運んで行く」という意味になるのだが、音楽業界では次の世代や時代に伝えてゆくというニュアンスで使われることが多い。そのアーティストが受けた衝撃や感動、音楽的体験を何等かの形で継承してゆく、ということでもある。
10月6日から9日まで恵比寿ガーデンホールで行われた「松本隆作詞家生活47周年×恵比寿ガーデンホール23周年・風街ガーデンであひませう」と10月8日に新宿文化センターで行われた「ベルウッド45周年記念コンサート」は、まさにそんな言葉を地でいったようなコンサートだった。
阿久悠以降の世代の「国民的作詞家」
音楽好きな人なら「風街」という言葉だけで、どういうコンサートなのかがお分かりだろう。作詞家・松本隆が日本語のロックの元祖と言われるロックバンド、はっぴいえんど在籍時代に発表した、日本のロックの金字塔的アルバム「風街ろまん」に由来する彼の代名詞のような言葉。デビュー45周年に発売されたトリビュートアルバムのタイトルが「風街であひませう」だった。その時には東京国際フォーラムでオリジナル歌唱アーティストを一同に介したコンサート「風をあつめて~風街レジェンド2015」も行われている。
作詞家・松本隆の功績は枚挙に暇がない。
何よりも、それまでロックのリズムには乗りにくいと言われていた日本語を使って日本語だからこそ表現できるロックを作り上げたことがある。一見難解な観念的な言葉と日常生活の中の平易な日本語の両方を使った質感やリズム感。ロックの歌詞を現代詩のような次元に高めたことが「日本語のロックの元祖」と呼ばれるゆえんだ。
ただ、大衆音楽という文脈で言えば、むしろそれ以降の功績の方が大きいと言って良いだろう。言うまでもなく80年代以降、男女を問わず彼が書いていた一連のヒット曲である。日本で暮らしている人で、彼が書いた詩を一度も口にしたことがないという人を探す方が難しいと思われるほどの実績の持ち主。阿久悠以降の世代の「国民的作詞家」と言って過言ではないはずだ。
彼が書いた詞にはいくつもの大きな特徴がある。
例えば、ディテールの描写だ。歌の舞台や情景を伝える小道具。花や雲や空、人込みやビルの様子などのスケッチ。主人公の心理を象徴するような具体的な事例をさりげなく織り込んでゆく映像感覚。悲しいとか口惜しいとか直接的な言い回しを避けながらの感情表現。「意味」や「関係」を説明しない。その人が歌うからこそ伝わる「空気」や「温度」あるいは「気分」。それは「物語的」というより「俳句的」と言った方が良いかもしれない。そして、何よりも終始、上品だった。下世話さが当たり前のようになっていた歌謡曲の歌詞の「品格」を変えた功労者なのだと思う。
松本隆の詞を愛唱し歌い継ぐ
恵比寿ガーデンホールで行われた「風街であひませう」は、彼が書いたそうした一連のヒット曲が、どんな風に受け止められているかを見せてくれたコンサートでもあった。
出演したのは、手嶌葵、富田ラボ、ハナレグミ、畠山美由紀、藤井隆、堀込泰行、斉藤由貴、クミコ。80年代当時のオリジナルを歌うのは「LEGEND」として登場した斉藤由貴。9月末に発売になったクミコの新作アルバム「デラシネ」は松本隆が書き下ろしている。他のシンガーが歌った多くの曲も2000年代入ってからの松本隆作詞曲。自分のオリジナルもあれば80年代のヒット曲のカバーもある。彼らに共通しているのが松本隆の書いた詞が愛唱曲だったということとそれらを「歌い継ぐ」という姿勢だった。
松本隆がドラマー兼作詞家だったはっぴいえんどは、細野晴臣(B・V)、大瀧詠一(G・V)、鈴木茂(G・V)、松本隆(D)の四人組。70年のデビューアルバム「はっぴいえんど」と71年の「風街ろまん」がURCレーベルから発売になったことは以前、この欄で触れた。最後のオリジナルアルバムになった72年の「HAPPY END」はベルウッドからの発売だった。初のロサンジェルス録音などを提案したのがベルウッドレコードの主宰プロデューサー、三浦光紀である。10月8日に新宿文化センターで行われた「ベルウッド45周年記念コンサート」も彼が中心だった。はっぴいえんどの細野晴臣と鈴木茂は、そちらの方に参加。筆者が担当しているTOKYO FMの番組「Kei's Bar」の中で三浦光紀は「松本君にも声をかけたんだけど、彼の方のイベントと重なってしまって」と残念がっていた。
ベルウッドレコードは、72年にキングレコードの社内に生まれた独立レーベル。あがた森魚や小室等、彼のグループ、六文銭、高田渡、はっぴいえんど、大瀧詠一のソロ、加川良、友部正人らフォークロック系の新しい才能が多数羽ばたいていったレーベルである。69年に大阪で発足した自主制作レーベル、URCの東京の受け皿と言ってもいいかもしれない。名前の挙がったアーティストの多くがURCから移ってきていた。
ベルウッドが制作していたアルバムに今も輝きを失わない名盤が多いのは理由がある。三浦光紀は、「何よりも洋楽に匹敵する音楽の質にこだわった」という話をしている。はっぴいえんど解散後、それぞれソロになった細野晴臣や鈴木茂らがバックを務めるアルバムが多かったことも大きかった。
「ベルウッド45周年記念コンサート」は、はちみつぱいやあがた森魚、細野晴臣、鈴木茂ら「LEGEND」も登場したものの、全体を仕切っていたバンドのリーダーでありコンサートのホスト的存在が高田渡の息子、高田漣だった。アコースティックギター、エレキギター、バンジョー、マンドリン、ピアノ、スチールギターと様々な楽器を持ち換えて演奏。父、高田渡の作品も含め、オリジナルに新しい息吹を与えていた。彼のバンドと演奏した出演者の最年少は90年代生まれのロックバンド、GLIM SPANKY。ヴォーカルの松尾レミは「親が好きでベルウッドの音楽がいつも流れていた」と言った。
ベルウッドの三浦光紀は、アナログ盤の復刻にも力を入れている。ドーナッツ盤と言われる7インチのシングル盤も12タイトルになった。はっぴいえんどや細野晴臣、大瀧詠一のソロ、高田渡や遠藤賢司。アルバムよりも貴重なアイテムとしてどれも中古盤屋で高価な値段がついているものばかり。「45周年コンサート」でも、それらの歌がカバーされていた。
「風街」と「ベルウッド」――。
それは「伝説」ではない。
今も受け継がれてゆく、音楽的良心なのだと思う。
(タケ)