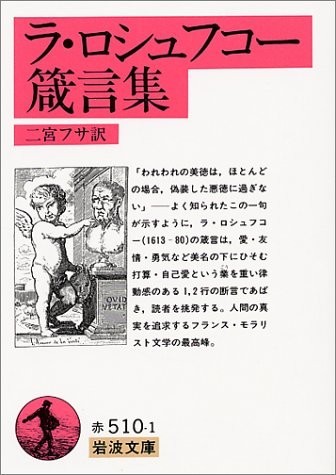■「ラ・ロシュフコー箴言集」(二宮フサ訳、岩波文庫)
17世紀フランスの古典に今さら書評もないとは思うが、ふとした契機に再読し、思うところがあったのでご紹介する次第である。
毒が薬に転じる面白さ
ロシュフコーは、モンテーニュなどと並びフランス文学史上のいわゆる「モラリスト」と位置付けられている。仏文学史に疎い評者はモラリストを正確に定義し得ないが、短文で断定的に人間の内面を抉る流派、と勝手に理解している。
岩波文庫版の箴言集では、表紙に「われわれの美徳は、ほとんどの場合、偽装した悪徳に過ぎない」との箴言が抜き書きされている。挑発的かつ逆説的な表現だが、これが本箴言集の大きな特徴であり、後代の多くの文学者から批判された所以でもあろう。
更に例を挙げてみよう。
「頭のいい馬鹿ほどはた迷惑な馬鹿はいない」
「老いは若い時のあらゆる楽しみを死刑で脅して禁じる暴君である」
「その真価が美貌より長持ちする女はめったにいない」
など。
本箴言集の特色は、これくらいで十分ご理解頂けるであろう。毒が薬に転じるのが本書の妙趣ではあるものの、子供に読ませたい本ではない。
また、公開を前提としていなかった「考察」という文章もあり、ロシュフコー公爵没後に出版されたそれらも収録されている。文庫本の3ページ前後で一つの題が完結する小文の集まりであり、箴言の断言調はそのまま、論理的な整合性など感じさせない記述である。
革命にはまだ百年ほど間がある、フランス貴族社交界の空気はどのようなものだったか。人間関係の遊泳を生業としていた人物が、そこで感得したことがここに示されているとすれば、貴族というものも、それはそれで随分と面倒な生き方を強いられていたものと空想される。