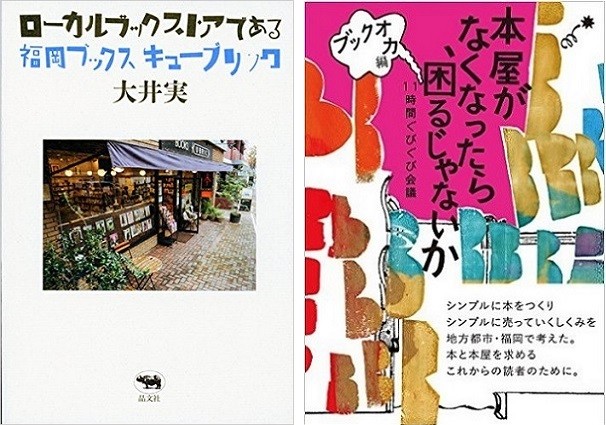■『ローカルブックストアである 福岡ブックスキューブリック』(大井実著、晶文社)
■『本屋がなくなったら、困るじゃないか 11時間ぐびぐび会議』(ブックオカ編、西日本新聞社)
中央公論3月号は、特集「祝!10周年 新書大賞2017」で、毎年恒例の「新書大賞」が10周年となった。特集の渡邊十絲子氏(詩人)との対談「厳しい時代に"骨のあるレーベル"が生き残った」の中で、出版業界の現状に詳しい永江朗氏(フリージャーナリスト)は、「この厳しい市況の中で、出版社も書店も大変です。経営資源の『集中と選択』が必要なことも理解する一方で、短期的な視野になって、ホームラン狙いの企画ばかりになるようでは、10年後も残るような価値ある本が作れなくなる。書店さんも同様で、今はチェーン店が増えて、どこの書店もランキングに基づいたものばかり。リスクを減らして、売れる物ばかり揃えようとすると、結局はお客さんが離れていく。長期的に見ればリスクを増やすことになります。」という。
評者は、仕事がらみもあり、やはり社会科学系に強い中公新書を読むことが多い。ジャーナリスティックなものは文春新書、新潮新書あたりに目がいく。なお、年間ベスト20にちくま新書が1冊も入っていないのには少し驚いた。
新規参入書店の将来像を語る
この「出版不況」といわれる中、福岡の地で、2001年に、黒田官兵衛ゆかりの福岡城(舞鶴城)の南側、素敵な雰囲気のけやき通りで「ブックスキューブリック」を新規開店したのが、大井実氏だ。2008年にはカフェ併設の箱崎店も開店している。
この「ブックスキューブリック」は、当時新規参入が事実上阻止されていた新刊を扱う独立系総合書店であり、その雄として、いまや将来の書店像を語る際に必ずあげられる、全国に名がとどろく書店となった。その大井氏が、はじめて自らのこれまでの歩みを振り返り、彼が影響を受けた様々な本を出版してきた縁の深い晶文社から、満を持して世に問うた待望の1冊が、「ローカルブックストアである 福岡ブックスキューブリック」(2017年1月)だ。
本書の表紙の裏書には、「...素人同然で始めた本屋の旅は、地元・福岡の本好きたちや町の商店主を巻き込み、本を媒介に人と町がつながるコミュニティづくりへと展開した。ローカルブックストア店主は理想の本屋像をどのように思い描き、歩んできたのか。独自の店づくりから、トークイベントやブックフェスティバルのつくり方、カフェ&ギャラリーの運営まで。15年間にわたる本屋稼業の体験をもとに、これからの本屋づくり、まちづくりのかたちを示す。」とある。きちんとした「編集力」のある書店は、地域の顧客に支えられて生きていけることを前向きに示し、勇気をもらえる。また、書店や図書館がまちづくりにおいて死活的に重要なものであることをあらためて認識させられる。
大井氏など福岡の出版社や書店で働く有志メンバーは、ブックフェスティバル「ブックオカ」(けやき通り一箱古本市)を2006年から開催してきた。
その10周年の2015年の「ブックオカ」のイベント「車座トーク~本と本屋の未来を語ろう」の模様を中心に収録した話題の本が、「本屋がなくなったら、困るじゃないか 11時間ぐびぐび会議」(西日本新聞社 2016年7月)だ。建前でない本質的な議論が、福岡ならではのノリと元気の良いつながり(もやい)の中で展開され、濃厚で魅力あふれる内容だ。大井氏も含め元気な業界人が多数登場する。「ブックオカ」自体、飲み話で東京の「谷根千」で行なわれた「不忍ブックストリート」を福岡でやってみようというのがはじまりだ。その勢いがこの本を生み出した。ドイツの状況が議論の中でよく参照され、今後の出版業界の将来を展望している。
経済官庁 AK