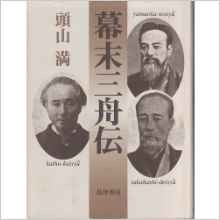■「幕末三舟伝」(頭山満著、島津書房)
頭山満といえば、戦前の右翼の巨魁と言われている。なるほど相当に暴れた過去もあるようだが、自由民権運動を支援し、これと決別してからも孫文を支援した、とも聞く。であれば昨今いわゆる「右翼」とは趣が異なる。最近評伝も出版されたが、どのような人物だったのだろう。
その頭山が、幕末の傑人、勝海舟・山岡鉄舟・高橋泥舟の三者を評して語ったのが本書である。生きる時代が一部重なっていただけあって、現代仮名遣いに直されたテンポの良い語り口によって、三者の偉業がまさに「観てきたように」活写される。
出版のため、頭山の口伝を門人・武劉生が整理したというが、同人もこう記している。「三舟の風格が翁(評者注・頭山)の舌端をかりて、躍如として現出し来ったことは、わたしのひそかに愉快とするところである」(本書「編者のことば」)。
西郷相手にみせた山岡鉄舟の胆力
全編これ痛快で引用に迷うが、ここは山岡鉄舟の言動を紹介したい。
まずその言である。曰く「...どんな事変にぶつかっても、びくりとも動かず。その難に堪え忍び、綽々としてその境遇の座を占めこんで、その大事を処理する...しかるを苦しいと云うままに、その難を免るるのは、まずまず錬胆の実薄く、忠孝仁義の誠に乏しき証拠である」。このくだりに、評者は嘆息せしめられた。
今年の仕事の山場、政治の要請を「綽々と」受け止めつつ「大事を処理」したか。「苦しいと云うままに」甘い仕事をしなかったか。
本書はさらに、駿府まで進軍した西郷南洲と鉄舟の激論を開披する。西郷の攻め手に、鉄舟は必死の防御だ。
慶喜を備前預かりとせよとの西軍の言い条に、鉄舟は堂々たる言葉を放つ。「この儀は、拙者において承知できぬばかりでない。徳川家恩顧の者、一人として承知するものはござりませぬ。つまるところ(中略)なし得ざるところを強いて兵端を開こうとなさるようなもので、これがため、数万の生命を絶つとあっては(中略)先生は、ただの人殺しでござります」。
朝命を楯になおも押し込む西郷に、鉄舟は、立場を変えてみよ、同じことを言われて薩摩藩士は引き下がれるのか、と鮮やかに切り返す。
手本をどこに求めるべきか
大軍を率いて押し寄せる西郷に、恭順の意を表しつつもあくまで理のあるところを申し立て、遂には相手にその筋を通させる。鉄舟のこの胆力。
評者には眩しい限りだ。
行政にあって、最後に責任を取るのは政治である。疎まれようとも、その「最後」まで政治に「理」を述べるのが我々の矩であろう。「平成の政治に西郷の如き度量はあるまい」などと、ぶつかっても見ずに勝手な憶測をして、直言しない言い訳をしていないか。
偉人伝を読むと、このように自らの小ささを自覚させられる。これは時に苦しい。だが読了後は必ず清々しい心地になり、少し背筋が伸びる。食事が身体への栄養補給とすれば、伝記は精神への栄養補給だ。
歴史上の偉人より、もう少し身近にはどうか。今風にいう「ロールモデル」はその役割を果たし得るか。評者は少々懐疑的だ。無論、職場の先輩や異業種で活躍する人を目標にすること自体否定するつもりはない。だが、ネットで雑文を書き散らす「メディア」事業で一儲けしようなどという、浅ましい皮算用を指して「起業家の志」などと持てはやす風潮にはうんざりだ。
大企業も最初は今いうベンチャーだった。その黎明期を支えた戦前戦後の名経営者の言葉と、昨今の「起業家」の言葉の重みの違いはどうだ。
「棺を覆いて事定まる」という。本書読了直後に、しばらく前に亡くなった官僚の大先輩の追悼文集が届けられた。ページを繰りながら、この言葉の重みを噛みしめる年末である。
酔漢(経済官庁・Ⅰ種)