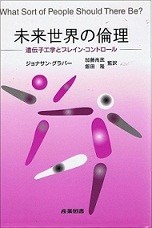教養漫画?
24年組の一角を占める竹宮惠子の『地球へ...』(1977-80年)は、環境破壊から地球を離れることを余儀なくされた人類を描いた漫画である。この世界は、「特殊統治体制」というコンピューターによる管理下にある。人間は人工子宮から生まれ、代父母のもとで育てられ、14歳の誕生日(目覚めの日)に仮の家族からさえ引き離され、子ども時代の記憶を抹消される。本作で描かれるのは、ミュウという特殊能力を持つ少年たちが地球を目指し、普通の人類と繰り広げる血みどろの戦いである。文庫版併載の石子順氏の解説では、本書は「支配者側によって苦痛を与えられたものたちが、それが何故なのかということに目覚め、やがてそれを変えようと行動していく姿のりりしさ。これは苦悩と救済のドラマであり、それを行うのは自分たちしかいないという自己発見のドラマである」としている。
教養小説(Bildungsroman)ならぬ教養漫画として『地球へ...』を読むのは、ひとつの読み方ではある。しかしながら、本作から評者に伝ってくるのは、むしろ自己発見の困難や挫折であるように思う。「特殊統治体制」への抵抗は、ミュウによる特殊能力をもってして辛うじて可能となるものであった。人類の側が対抗措置を取ることで、ミュウも人類もともに最終的には地球を失ってしまう。ミュウの長と人類の指導者の間で相互理解が得られるが、その相互理解の代償は地球そのものであった。最終章は宇宙をさすらう宇宙船の邂逅を描いて幕を閉じる。圧倒的に技術化された社会では、抵抗には人間離れした能力が必要とされ、折角の抵抗もその成果は貧弱なものである。このペシミスティックな読み方は、70年代末という『地球へ...』の執筆時期の時代の空気とも整合する。制度化された技術に対する「人間性」の弱さである。
警鐘
技術に対する「人間性」の弱さというテーマは、映画でよく取り上げられるテーマであるが、はやくから文学が開拓してきた問題である。ハクスリー『すばらしい新世界』(1932年)では、人工子宮の登場により家族は消滅しており、「ソーマ」という副作用のない麻薬が人間を苦悩から解放している。『新世界』では、野蛮人(普通の旧世界人)が登場し、新世界の守護者ムスタファ・モンドに論争を挑んでいる。最終的に「それじゃ全く、君は不幸になる権利を要求しているわけだ」とムスタファ・モンドから詰め寄られると、野蛮人は「それならそれで結構ですよ」と認めるほかなかった。結末で野蛮人は縊死してしまう。ソーマにより約束された幸福に対し、本当の幸福は別のところにあると主張することは難しい。
『新世界』は生命科学の延長で未来社会を描いているが、もう一時代前のバトラー『エレホン』(1872年)が扱うのは、意識を持つ機械への警鐘である。エレホンという架空の国で、機械がやがて意識を持ち人間を隷属させる危険性を嗅ぎ取った人々は、一切の機械を廃絶してしまう。機械の禁止は徹底したもので、外の世界から迷い込んできた主人公の懐中時計までもが没収の憂き目にあう。機械の廃絶は、機械推進派との戦争によって達成される。皮肉なのは、機械反対派も戦争には機械を使わざるをえなかったことだ。機械反対派は勝利の暁に手元の機械を廃棄している。機械の力で勝った人間がおとなしく機械を手放すのか、実際問題疑わしいと言わざるをえない。一旦はじまった機械の進化を押しとどめるのが如何に困難か、同書からの次の引用が雄弁に語っている。「成程、低級な唯物主義的観点からは、それを使用することが利潤を生む可能性がある時はいつでも機械を使用する者が、もっとも栄えるように思われるだろう。併しそれが機械の策略なのである」。
ドリームワールド
近年の人工知能(AI)ブームにみられるように、機械技術の進歩は、着実に意識を持った機械への道を歩んでいるようにみえる。生命科学においても、ゲノム編集の実用化に踏み込みはじめているし、抗鬱剤の乱用が問題視されてから久しい。技術開発とその応用は、政府の成長戦略の核をなしている。政治においても、「『人口減少下でも経済成長できる』というビジョンを国民と共有していく必要がある。我が国が世界に先駆けて、人工知能などを活用したイノベーション創出・商品化・サービス化を進めるべきである」(自由民主党「2020年以降の経済財政構想小委員会」=橘慶一郎委員長、小泉進次郎事務局長)という認識が公にされている。たとえ、技術開発の中止を言い出したところで、「機械を使用する者が、もっとも栄えるように思われる」のであり、我が国が開発を止めたところで、米国や中国で開発が進むであろうから、その場合、国家間競争で我が国が後れを取るだけのことにおわる。
それでも、評者が『地球へ...』などを取り上げるのは、技術進歩のなかで、我々が当たり前に思ってきた「人間性」が実は脆弱なものであり、この「人間性」をどう扱うか真剣に考察する時期に差し掛かっていると感じているからである。ジョナサン・グラバー『未来世界の倫理』(1984年)は、「ドリームワールド」という枠組みを用いた思考実験をおこなっている。脳と人体の感覚器官を機械につないで刺激のやりとりをするこのシステム(映画『マトリックス』を想起してもよい)は、あたかも現実の世界で生きているかのような幻の体験を人間に与える。幻の家族、幻の町、幻の政治、幻の科学研究のなかで、人間は最大の幸福を経験することができる。この機械につながれることを拒む理由はあるのだろうか。
グラバーによると、「ドリームワールド」の与える体験では満足させられない活動として残るのは、人間同士の人格的交流と科学研究のみであるという。ドリームワールド内に幻の子どもと現実の子ども、ふたりの子どもがいるとした場合、現実の子どもの死の方が幻の子どもの死よりも悲劇であるに違いない。幻の科学実験で幻の新素粒子を発見したとしても、それは真の科学研究とは異なるものである。たとえ当の本人に現実と幻の区別がついていなくても、現実の人格的交流と科学研究の方が価値が高いというのである。人間が快楽を感ずるだけの動物的存在を超えるものだとすれば、その「人間性」の根拠がここにある。
「人間性」の保護? あるいは...
たしかにその通りだろう。ただ、それだけである。本人に知らされなければ、幻の子どもと幻の科学研究とともに人間は満足して死んでいく。未来のソーマ、未来の機械が与える甘い体験の中で、「人間性」などは蕩け去ってしまう。もしそれが嫌なら、もし技術のなかで溶けていくことに違和感を感ずるのならば、その違和感を言語化し、「人間性」の保護のため技術にどのように縛りをかけるか、幅広く議論を喚起する必要がある。
あるいは、もはや人間は「人間性」などという古い殻を脱ぎ捨て、動物的幸福の最大化のなかに身を投じてしまうのがよいのかもしれない。技術革新を進めることに加え、前提条件を整える必要がある。具体的には、生産性を高め、富をあまねく行きわたらせ、人間の数を減らし、地球環境との調和を達成する。あと一世紀はかかりそうだ。ただ、実現できれば、人類史の最後を飾る偉業となろう。
さて、読者はどちらの道を進むのがよいと考えるか。
経済官庁(課長級) Repugnant Conclusion