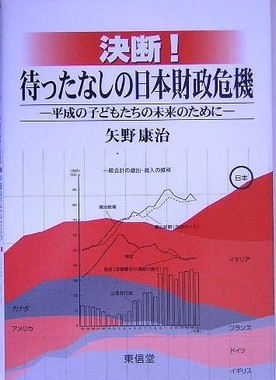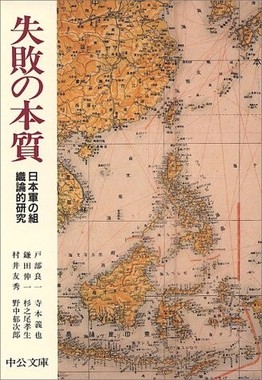的確な状況認識と鋭利な分析でその考察が常に注目される待鳥聡史京都大学大学院教授(比較政治論)が、2015年1月号の「中央公論」(2014年12月)の「特集 2015年を読む」に寄稿した「『政策の季節』から『選挙の季節』へ」で、いちはやく喝破していたように、いま、永田町や霞ヶ関は「2016年夏の参議院選挙まで続く『選挙の季節』」の中にある。待鳥教授は、頻繁な「選挙の季節」がきてしまう日本の現状は、日本政治の「アキレス腱」だとする。国際比較からしても短すぎ、「困難な政策課題がどうしても先送りされやすく、難問に取り組まねばならない現代の先進国としては明らかに不向き」だという。
頻繁な「選挙の季節」が先送りする難問への取り組み
経済政策の一端に関わるものとして、この「アキレス腱」に関して痛感するのは、「財政問題」である。財務省の現役官僚である矢野康治氏(当時主計局企画官=厚生労働係担当)が、「決断! 待ったなしの日本財政危機―平成の子どもたちの未来のために―」(東信堂 2005年7月)を、「たたかれ台」となる覚悟をもって、高い支持率を誇りながら、消費税増税を避け続けた小泉政権時代に出版したことは、霞ヶ関ではよく知られている。その後、2000年代後半の政権交代の激動の中から、国会の多数を構成する会派の合意で、不人気な増税や社会保障の見直しも含む「社会保障・税の一体改革」の成案を得たことはまさに画期的なことだった。
しかし、その後の状況は楽観できないものだ。インターネット上の言論プラットフォーム「アゴラ」の5月21日付記事「オリヴィエ・ブランシャール教授の日本財政への警鐘」で、小黒一正法政大学教授は、IMF(国際通貨基金)の前チーフエコノミストで、有力なノーベル賞候補でもある経済学者のオリヴィエ・ブランシャールが、イタリアのコモ湖畔で開催された政策フォーラムで、「ゼロ金利が、日本の公的債務に内在する危険を覆い隠している。今年、政府債務は、対GDP比250%に達し、持続不可能な軌道を描きながら急上昇する可能性が高い。」と、日本の財政状況に深刻な懸念を示したことを報じた、英国テレグラフ紙の記事(4月11日付)を紹介・解説している。
良識ある経済学者・官庁エコノミストとして、評者がその論考にいつも注目している、小峰隆夫法政大学教授は、「最新 日本経済入門(第5版)」(日本評論社 2016年3 月)で、財政赤字の問題点を、①生産的な投資と競合して将来の成長の基礎となる資本蓄積を阻害すること、②財政赤字が大きくなりすぎると、ほとんどを国債の利払いに当てなくてはいけなくなり、財政機能が果たせなくなること、③財政が硬直化して新規の分野に予算を振り向けることができなくなること、そして④社会保障費の増大が世代間の不公平の問題を生じさせることをあげる。そのため、財政のバランスを注視していかなくてはならないという。また、国債の信用にかかわることから、戦後、G7の国で、財政危機に直面しても、財政破綻(国債のデフォルト)した国はないと指摘する。
最後は何とかなるというオプティミズム
井堀利宏東京大学名誉教授は、最近出版した「消費増税は、なぜ経済学的に正しいのか―『世代間格差拡大』の財政的研究」(ダイヤモンド社 2016年3月)で、財政赤字を楽観させる「経済成長の自然増収で財政再建はできる」、「消費税増税は負担が大きく、先送りすべきだ」、「2020年までに基礎的財政収支が均衡できれば、財政再建できる」、「歳出削減と増税を実現すれば、2020年代以降も乗り切れる」は、誤解であると指摘する。
また、財政悪化の要因を「政治が若い世代や将来世代の利害を十分に考慮することなく、その場しのぎで先送りの政策決定をしてきたことにある」が、「そうした先送りも少子高齢化社会を迎えて限界に達しつつ」あり、2025年ごろには、財政・社会保障制度が破綻してしまいかねないという。そして、減り続ける若者が多くの年配層を支える賦課方式の社会保障制度が続く限り世代間不公平は解消されないとし、受益と負担を一致させる、社会保障における個人勘定の方式を提唱する。
2016年6月号の「中央公論」(2016年5月)では、評者が、このコラムの第1回目(2012年9月20日 最近の日本が「元気」を失った理由 「旧日本軍の組織」検証本から探る)で取り上げた「失敗の本質」(中公文庫 1991年)が特集されている。この特集の中で、新浪剛史サントリーホールディングス社長は、「...日本では、成功体験がそのまま進化して、精神論になっていく。これは多分、日本の文化だと思うのです。最後はなんとかなるという超オプティズム(超楽観主義)が、心の奥底にありますよね。同時にダメなら仕方ないという超ペシミズム(超悲観主義)があって、その入れ替えがしょっちゅう起きているのです。...日本はペシミズムの塊なのに、最後は何とかなるというオプティミズムがあるわけで、海外からはわかりにくい国ですね。」と指摘しているのが、最近の情勢を観ても遺憾ながら正鵠を得ているのではないだろうか。
2020年東京オリンピックの開催後に、国内経済社会は大混乱で、G7のメンバーからも滑り落ちた、といった想像もしたくない「経済敗戦」の事態を防ぐために、「国民、政府、議会の理性」(小峰教授)がいまや試されている。
経済官庁(総務課長級 出向中)AK