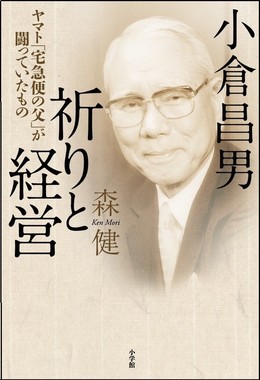電話一本かければ、自宅まで集荷に来るし、全国どこでも荷物が届く。今ではアタリマエとなった、この「宅急便」という仕組みを「発明」したのが小倉昌男だ。彼は、その実現に向けて、霞が関と闘い、全国にネットワークを広げた。引退後は、障害福祉にほとんどの私財を捧げ、障害者が働くことを徹底的に支えた。伝説の経営者として、今なおその経営書は、読み続けられている。
本書は、そんな「論理と正義の人」というイメージとは異なる「人間 小倉昌男」の姿を、1年半に及ぶ丹念な取材を基に描いたノンフィクション。ひとりの弱い人間として誠実に生きた小倉の生き方に読む者の心が揺さぶられる。小学館ノンフィクション大賞を受賞した「傑作」である。
伝説の経営者の3つの「謎」―まだ語られていない「何か」がある―
希代の名経営者、小倉昌男が亡くなって10年になるが、未だにその名声は多くの日本人に記憶され続けている。
「宅急便の父」、規制緩和のために霞が関と闘った「闘士」、そして引退後は、障害福祉に私財を捧げ、働く障害者に月給10 万円という夢を実現した「篤志家」。小倉昌男といえば、非の打ちどころのない、素晴らしい人物との印象がある。
しかし、著者は、小倉をめぐる数々の書籍を読む中で、「もやもや」する部分が残ったという。どうしてもわからないことが3つあったそうだ。
①なぜ、障害福祉の世界に飛び込んだのか? 引退後、小倉は、ほとんどの私財、具体的には、小倉自身が保有していたヤマト運輸の株のすべて(46億円相当)を投じて、ヤマト福祉財団を設立し、障害者の就労支援に力を尽くした。 小倉自身は、自著の中で、こうした福祉への取組みについて、こう語っている。 「私がなぜ福祉の財団をつくろうと思ったのかというと、実ははっきりした動機はありませんでした。ただ、ハンディキャップのある人たちになんとか手を差し伸べたい、そんな個人的な気持ちからスタートしたのです」(『福祉を変える経営』) 著者曰く、経営者時代に特段、福祉活動について関心があったようには見えなかった小倉が、46億円もの私財を投じて福祉の世界に入ったのに、〈はっきりした動機〉がないというのは奇異に思えたという。
②なぜ、外部の小倉評と小倉自身の自己評価の間に大きなギャップがあるのか? 小倉については、「名経営者」、さらに、官庁の規制と闘い、行政訴訟も辞さなかった「闘士」というイメージがあるが、自著には、そうした大きな声の言葉はまったく出てこない。むしろ、自らについては、「気が弱い」という表現が幾度となく出てくる。このギャップの大きさに違和感を覚えたという。 「どうも私は世の人々から、気が強くてケンカっ早い人間だと思われているようだ。おそらく宅急便の事業などをめぐって役人と徹底的に闘ってきたことで、そういうイメージが広まってしまったのだろう。実際は、自分でも情けなくなるぐらい気の弱い人間だ。ケンカっ早いどころか、むしろ、何か言いたいことがあっても遠慮して引いてしまうことのほうが多い」(『「なんでだろう」から仕事は始まる!』)
③なぜ、死期を目前にして渡米し、娘夫婦の自宅で亡くなったのか? 小倉は、すい臓がんが進行し、余命数か月という段階となって、長女家族が住む米国ロサンゼルスに移り、その地で亡くなった。80歳という高齢で、しかも死を自覚していながら、なぜアメリカに渡ったのか。有効な治療法や医師を求めての渡米ではないという。一体、なぜ、そんな無謀な行動をとったのか。
丹念な取材で思いもよらない事実を知る ―抱えていた思いを痛いように共有していく過程―
著者は、小倉に関する、こうした謎の答えを知りたいと思い、軽い気持ちで取材を始める。それが思いもよらない事実と遭遇し、追い続けるうちに1年半もの期間を費やすこととなった。
ノンフィクションとしての本書の核心は、この「意外な事実」であるが、ネタをばらしてしまうと、本書を読む意味が大きく減じてしまうので、ここではただ「家族をめぐる問題」とだけ触れておく。
前述のように、本書は、小学館ノンフィクション大賞を受賞しているが、史上初めて、選考の際、委員全員が満点をつけ、満場一致で選出されたという。評者自身も、頁をめくる手がもどかしく思えるほど没入してしまったが、それは、著者が、この事実に辿り着くまでの丹念な取材に負うところが大きい。
著者は、小倉に関する書籍は無論のこと、講演録など大量の資料を読み込むとともに、数十人もの関係者を訪ね、丁寧にヒアリングを行っている。その対象は、ヤマト運輸の関係者や経済界の交遊者にとどまらず、妻の友人、小倉夫妻と交流のあった神父、鍼灸師、晩年に小倉の世話をした女性、ロサンゼルスに住む子ども達にまで及ぶ。
著者の旅は、北海道、静岡、新潟、最後はロサンゼルスへと続く。小倉の知られざる一面が明らかになるにつれ、著者の小倉への思いが深まっていく。今回の取材は、「小倉が抱えていた思いを痛いように共有していく過程」だったという。
そして、最後まで読み進めた読者は、小倉をめぐる「意外な事実」の全容を知り、著者が感じていた3つの謎の意味を理解する。「そうだったのか」という思いととともに、小倉の生き方に深い感動を覚えるに違いない。
「名経営者」「闘士」とは異なる人物像―人間、小倉昌男―
著者が発見した「意外な事実」とは、低俗なのぞき見主義的なメディアなら、「スキャンダル」と扱いかねないものだ。しかし、本書で、そんな感じは全くない。むしろ、小倉にとっての「試練」であり、それを闘い抜いた小倉を知ることで、これまでの「名経営者」、「闘士」といった人物像とは異なる、「人間、小倉昌男」という新たな姿が立ち上ってくる。
前述のように、「意外な事実」とは、小倉の家族をめぐる問題である。小倉は、それを一人で誠実に向き合い、受け止めてきた。ひとりの弱い夫や父として...。
子ども達は小倉のことをこう評している。
長女:「父の視点というのは、必ず弱いものに惹かれていました。絶対強いものにはいかない。宅急便だって、ふつうの主婦とかの不便や不都合に目がいって、事業化に結びついたし、福祉財団だってそう。それは、自分も弱きものという自覚があったのかもしれない」
長男:「それは自分が小心者で、気が弱いとつねづね語っていたことともつながるよね。その小心者が世の中で闘わなくてはいけないとなって、論理とか理屈で武装した。そう考えると、一貫するんです。弱き者の立場でいるほうが、社会が見やすかったんだと思います」
小倉は、若い頃、結核で療養していた時代に、救世軍(プロテスタント)でキリスト教の洗礼を受けていたが、引退前に、妻と同じカトリックへと改宗している。毎朝、夫婦で通っていたカトリック教会では、いつもこう祈っていたという。
「今日も一日、悪いことをしませんように――」
著者から取材を受けた人々は、みな小倉について、尊敬と愛情に満ちたコメントを残している。著者自身も小倉の人生を辿る中で、次第に、冷静な取材者の立場を超え、小倉の生き方を世に伝えたいとの思いを強くする。
本書が、読む者の心を打つのは、「経営者」や「闘士」としての小倉に惹かれるからではない。「人間 小倉昌男」としての生き方に感銘を受けるからだろう。そして、小倉の数々の偉大な業績の背景に、ひとりの弱い人間としての「祈り」や「贖罪」の思いがあったという事実も心に染みる。
素晴らしいノンフィクションだ。多くの人々に小倉昌男の人生を知ってほしいと思う。
JOJO(厚生労働省)