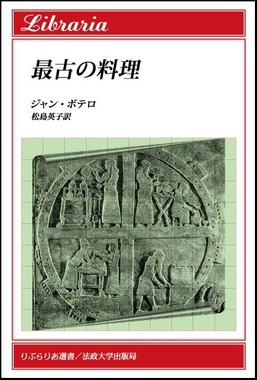古代メソポタミアと言えば、バビロン王朝のハンムラビ法典の一節、「目には目を、歯には歯を」が有名だ。
この一見野蛮に映る規定は、実は過剰な報復合戦を防ぐためのものとされる。
血で血を洗う現代中東情勢を思うと、そうした抑制が外れていることは残念だが、それだけにメソポタミア文明の洗練度合いが際立つ。
その洗練された文明のもとで、何が料理され、食べられていたのか。
1980年代、米イェール大学に保管されていた紀元前1600年頃の粘土板のうち3枚が「レシピ集」と判明した。中華文明でさえ、これほど古いレシピは現存しないとされる。
本書はそのレシピを基に、メソポタミア文明論を展開したものだ。
歴史の闇に光を照らす
著者は「メソポタミアの料理の全体像を、その独自性が浮上するような形でつかみ取ろう」と試みる。
だが如何せん、原典はたった3枚の粘土板に刻まれた楔形文字である。著者自身も「これは限りなく続く長編映画の限られた数コマに等しい」とする。そこで著者は、往時の神話なども用いて、アッカド学の大家たる歴史学者らしい分析を行い、往時の料理を再現していく。
対象となる年代は紀元前4000年から紀元前400年代(あるいはより後代)と幅広い。原資料の乏しさから、章立ては年代順ではなく、「かまど料理用具」「したごしらえ」「冷たい料理」「飲み物」「死者の食卓」等々とされる。これが奏功し、メソポタミア史に暗い評者にも読みやすかった。
散文的な部分もあるが、古代の叙事詩の数行など、わずかな情報から謎解きを行っていく過程には引き込まれる。