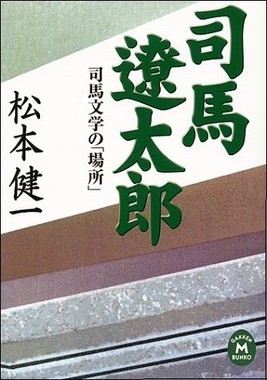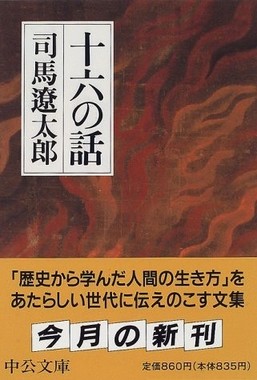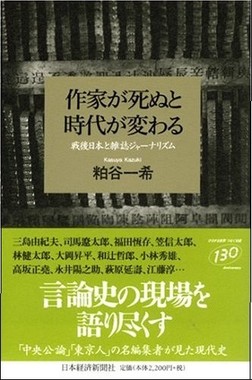今年は、「国民作家」司馬遼太郎の没後20年で、各種メディアで司馬遼太郎が取り上げられる機会も増えている。霞ヶ関に勤める公務員の中で、司馬作品はこれまでかなり好まれて読まれてきたと思う。特に、日々の仕事に追われる中で、「鳥瞰という方法」(松本健一著『司馬遼太郎 司馬文学の場所』=学研M文庫 2001年、ちくま文庫 2007年)は、とても魅力的だ。「鳥瞰」とは、「作者が鳥のように高所にいて、作中人物を眺め下ろす方法」だ。評者が、司馬遼太郎の歴史小説で一番好きな作品は、福岡の黒田藩の始祖である黒田官兵衛(如水)をあつかった「播磨灘物語」(講談社文庫 全4巻 1978年)だ。秀吉の「中国大返し」による明智光秀との決戦までの官兵衛の前半生(30歳代)が主として描かれる。諸勢力が錯綜し、混乱する戦国時代の中で、繊細な人物観察力、歴史の動向への的確な洞察力、卓越した折衝力・情報収集力をもって、最高権力者との信頼関係を構築していく「官兵衛」が、司馬遼太郎の手によってますます魅力を高めて、我々の前に鮮やかに立ち現れる。実務家の1つの理想像が描かれる。著名経済ブログ「溜池通信」を書いている双日総研チーフエコノミスト吉崎達彦氏のペンネームもまさに「かんべい」である。
加えて、随筆も味わい深い。「洪庵のたいまつ」や「二十一世紀に生きる君たちへ」が掲載されている「十六の話」(中公文庫 1997年)、厳選された随筆が掲載される「以下、無用のことながら」(文春文庫 2004年)のほか、全15巻の随筆集「司馬遼太郎が考えたこと」(新潮文庫 2001年~2002年)もおりにふれてときどき取り出して読む価値がある。
ただ、最近、霞ヶ関界隈で、司馬作品を読んでいる人口は減少しているように思う。2000年代半ばに、研修の講師として、役所の中堅若手職員に、司馬作品について読んだことがあるかを問うたことがあるが、恥ずかしさもあるだろうが、ほとんど手が挙がらなかった。
三島事件で警世家となり文士から国士に変身との指摘
名編集者として一代をなした故粕谷一希氏は、「作家が死ぬと時代が変わる」(2006年 日本経済新聞社)で、司馬は、「昭和40年代から50年代にかけては、『日本のおもしろさは、ある種軽率なほどに軽やかな創造的エネルギーだ』ともいっていた」という。そのような前向きの小説が、将来に希望が持て、白黒がわりとはっきりしていた20世紀の間は左右問わず好まれたように思う。また、松本健一著「三島由紀夫と司馬遼太郎~『美しい日本』をめぐる激突」(新潮選書 2010年)は、三島と司馬の思想・軌跡を対比しながら、司馬の「戦後」擁護の思想をたくみに描き出す。粕谷氏は、前掲著作で、松本氏同様、三島由紀夫の割腹事件(1970年11月25日)に関する翌日の司馬遼太郎の毎日新聞第1面での事件への感想と批判が、司馬が警世家となり、文士から国士に変身させたと指摘する。
2000年代の「政治主導」という役人にとっての「嵐」の中で、これを標榜する政治家が、おおむね司馬作品を振りかざしながら、「改革」を意気軒昂に進めたことに、司馬作品に対する、霞が関のいわく言い難い違和感が広がったと感じる。粕谷氏は、「...司馬さんもあまり国事にコミットすると、文士の甘さが目についてきたのである。ここに司馬さんの孤独もあった」とし、「池波正太郎がグルメの話を書いたり、藤沢周平が『たそがれ清兵衛』を書いたこと自体が、司馬さんに対する批判ではなかったか、と私は思っている」という指摘は、いま、ゼロ年代の日本政治の激動の時期を経て、とても重く感じられるのだ。
経済官庁(総務課長級 出向中)AK