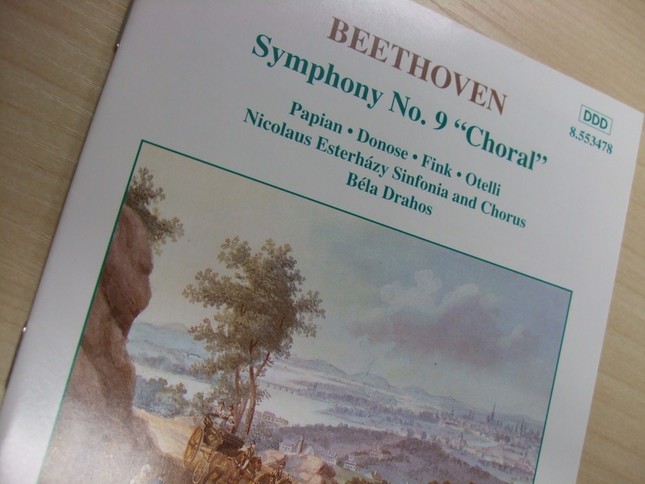「交響曲:シラー作、頌歌(オード)『歓喜に寄す』を終末合唱とし、大管弦楽、四声の独唱、四声の合唱のための: プロイセン王フリードリヒ・ヴィルヘルム三世陛下に最も深い畏敬の念をもって奉る。ルードヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン作曲、作品125番」
......初版の時に楽譜にこう書かれていた曲が、現代日本では「第九」と略して呼ばれるベートーヴェンの第9交響曲です。日本独特の習慣ですが、年末に数多く演奏されます。
「第九」については、昨年のこのコラムでも2回にわたって取り上げましたが、今回は、第九が発表された後、つまり後世に与えた甚大な影響、について書いてみたいと思います。
現代の視点から見ると、「クラシック音楽の古典中の古典」である交響曲ですが、この曲が登場した当時はものすごく斬新で、またベートーヴェンが最後に完成させた交響曲として彼の代表作としてとらえられたところから、ベートーヴェンの存在も含めて、大変な影響を後世に与えます。おそらくすべて書くことは不可能なのですが、何点かあげてみましょう。
「オーケストレーションの常識」からしたらあり得ない書法
常に新しい試みを作曲で行ってきたベートーヴェンは、第九にもたくさんのチャレンジを盛り込みます。もちろん、一番目立つのは、第4楽章に「人間の声」の独唱と合唱を盛り込んだことですが、ほかにもいろいろ試みています。
それまで、オーケストラの最も低音を担い、いわば「縁の下の力持ち」的役割のみを担ってきたコントラバスに、ソロで弾くパートを与えたり、コントラバスとその上の音域を受け持つチェロで、第4楽章「歓喜の歌」の最初の出だしを受け持っています。今までの「オーケストレーションの常識」からしたらあり得ない書法で、ここでもベートーヴェンの挑戦が見て取れます。もともと交響曲の第3楽章はゆっくりした3拍子の「メヌエット」という形式の曲が来ることが多かったのですが、これを早い3拍子の「スケルツォ」に置き換えたのがベートーヴェンでしたが、第9番では、第4楽章の盛り上がりを演出するために、「スケルツォ」を第2楽章に置き、第3楽章をゆったりとした曲調にしています。