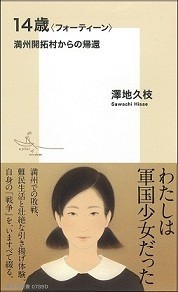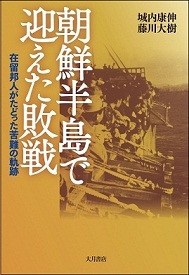トルコの海岸に打ち上げられた幼い男の子――1枚の写真が世界の人々の心を激しく揺さぶった。難民を受け入れるべきか、それとも・・・。2015年は難民問題に関心が集まった。
ところで、かつて多くの日本人が「難民」になったことを覚えているだろうか。旧満州・朝鮮半島に取り残された人々だ。今年は戦後70年ということもあり、関連の書籍の出版が続いた。
澤地久枝さんも体験記
1945年8月15日、日本は無条件降伏した。そのとき「外地」には、軍人と民間人合わせて約660万人の日本人がいた。中でも多かったのが旧満州・朝鮮半島だった。ソ連の参戦、関東軍の敗走で現地は大混乱となり、日本への「引き揚げ」は困難を極めた。そして、100万人ともいわれる大量の「難民」が発生した。
『14歳〈フォーティーン〉 満州開拓村からの帰還』(集英社新書、6月刊)は、作家の澤地久枝さん(85)の体験記だ。父親の仕事の関係で4歳のころ家族とともに満州に移住した。ところが14歳で敗戦。満州・吉林での「難民生活」は一年に及んだ。「棄民」ともいうべき壮絶な日々、そして一家での日本への引き揚げ・・・。多感な少女が軍国少女となり、戦争に翻弄されていく様子を、自身の記憶と膨大な資料から丁寧に回顧し綴った。
「誰だって、語りたくない人生体験を持っている」――だが、自分自身のそれをいま「書いた方がいいと思うようになった」と澤地さん。『妻たちの二・二六事件』『密約―外務省機密漏洩事件』などで、戦争や国家をテーマにしてきた著者の作品の根っこには、こうした苦難の体験があったことがわかる。
身内に引揚者がいた
毎日新聞編集委員・井上卓弥さんは、『満洲難民 三八度線に阻まれた命』(幻冬舎、5月刊)を出版した。ソ連軍の侵攻から逃れるために、満洲国首都・新京から朝鮮北部の郭山という小さな町に疎開していた1094人の日本人の物語だ。足りない食糧。厳しい冬。人々は飢えと寒さ、伝染病に苦しみ、子どもたちは次々と命を落とす。「このままでは死を待つだけ。なんとしても日本へ」――ついに決死の脱出行が始まった・・・。
著者は1965年生まれ。もちろん戦争体験者ではないが、この「郭山疎開者」の中に祖母と伯母がいた。記者として国際報道に携わり、旧ユーゴスラビア・コソボ紛争ではアルバニア系難民を取材したとき、国境を越えて隣国アルバニアに逃れてくる難民の姿が、自分自身のルーツと重なった。改めて当事者として、「満州難民」に取り組み、「戦後史の闇」に光を当てた。
同じく朝鮮半島を舞台にしたものでは、『朝鮮半島で迎えた敗戦――在留邦人がたどった苦難の軌跡』(大月書店、7月刊)がある。東京新聞記者の城内康伸さんと藤川大樹さんによる共著だ。二人とも戦後生まれだが、城内さんの母は朝鮮半島からの引揚者。加えて城内さんは記者になってからソウル、北京の特派員を経験したこともあり、関心を持ち続けていたテーマだった。
敗戦によって、植民地・朝鮮半島は一瞬のうちに「外国」になった。そのとき残された日本人はどんな運命をたどったのか。史料と証言を駆使して綴る。同胞の待遇改善のため献身的な努力をした日本人のことなども紹介されている。新聞連載を大幅に加筆して単行本にした。
満州の歪んだ歴史に迫った本も
「孤児」自身の自費出版もある。東京・世田谷区に住む中島幼八さん(73)は、生後間もなく一家で現在の黒竜江省へ。満蒙開拓団員の父は現地で召集され、3歳で「残留孤児」に。中国人の養父母に育てられた。16歳で単身日本に帰国したときはまったく日本語が分からなかった。『この生あるは』(幼学堂、4月刊)は、そんな数奇な半生を自ら綴ったものだ。
日本語版だけでなく、夏には中国語版『何有此生』(北京三聯書店)も出版。中国側メディアからの取材が相次いだ。中でも香港の鳳凰(フェニックス)TVは、旧満州の映像を交えつつ長時間のインタビュー特番で紹介した。達者な中国語で、「孤児体験」と養父母への感謝を語る日本人の中島さん。戦争を知らない世代の女性インタビュアーは衝撃を受けた様子だった。
多くの悲劇と難民を生むことになった「満州」――そのいびつな歴史に迫った本も目立った。
たとえば、『移民たちの「満州」―― 満蒙開拓団の虚と実 』(平凡社新書、7月刊) 。京都新聞記者の二松啓紀さんが、昭和恐慌から続く農村疲弊を解決するという名目で遂行された満蒙開拓移民政策を、体験者から託された資料を基に振り返る。多大な犠牲を出した満蒙開拓団や満蒙開拓青少年義勇軍。しかし戦後、推進した当事者たちに、「反省の弁すらなかった」と静かな怒りを込めて記す。二松さんは05年にも『裂かれた大地――京都満州開拓民』(京都新聞出版センター)を出している。
学者の本では、『満洲暴走 隠された構造 大豆・満鉄・総力戦 』(角川新書、6月刊) がある。著者の安冨歩さんは経済学者で東京大学東洋文化研究所教授。「満州」ではなく本来の表記「満洲」と書くことにこだわる。混迷の時代に成立し、わずか13年で消滅した「満洲国」。成立から崩壊までの「暴走」を、なぜ誰も止められなかったのか? 関係者の多くが、「立場に従って役を果たしただけだ」と開き直る無責任ぶり――その欺瞞の系譜は現代の日本にも連なる、と警鐘を鳴らしている。
昨年出版されたものを含めると、「満州難民」に関する本はさらに増える。戦後約70年が過ぎる中でほとんど忘れられつつある「満州難民」。だからこそ「書き残しておきたい」「伝えたい」という関係者の思いは、残された時間との闘いの中で募る。