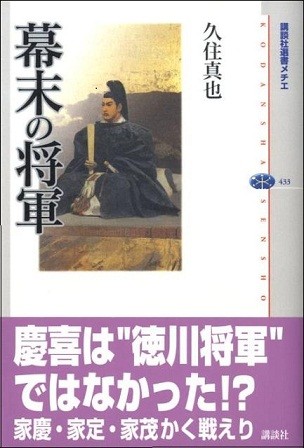■「幕末の将軍」(久住真也著、講談社選書メチエ)
坂本龍馬による明治新政府の構想では、最後の徳川将軍慶喜は「副関白」に位置付けられたとされる。このことに違和感を持つ人は多いのではないか。坂本龍馬は「大政奉還」を推進し、徳川政権を終焉させた功労者ではなかったのか、と。
素直に歴史を眺めると、薩摩・長州両藩と一部公家が主導した「王政復古の大号令」により、「大政奉還」の試みは失敗したと見るのが自然に思える。前者は「倒幕」であるが、後者は「公武合体」の一つの形であり、決して徳川家を政治の舞台から排除するものではないからである。事実、「大政奉還」の後も慶喜は内大臣という要職に留まり、引き続き外交交渉などを主導している。
「大政奉還」は徳川政権の性格を抜本的に変えるものであったことは確かである。しかしながら、それは15代将軍慶喜により唐突に行われたものではなく、ある意味で先代家茂の時代に顕著となった将軍の性質変化の当然の帰結であったということが、本書には示されている。
徳川将軍に求められた資質とは?
恥ずかしながら、徳川幕府とは何なのか? ということについて本書によって初めて理解することができたように思う。徳川幕府とは、ざっくりと言えば、井伊家や酒井家を始めとする徳川家の家臣団が政権を担い、旧戦国大名や公家を統制していた体制、ということになる。
歴史の教科書では、大名には親藩・譜代・外様があり、老中などの幕府の役職には譜代大名のみが就くことができたとあるが、分かりにくい。徳川家の家臣団である譜代大名(同じく徳川家の直臣である旗本も含む)こそが幕府そのものなのだ。そして、「大政奉還」は、少なくとも統制の対象であった外様大名や公家も政権に参画させることに最大の変革点があったといえよう。
毛利家や島津家などの外様大名からすれば、同じ戦国大名として肩を並べていた徳川家の家来に統制される、ということは面白いものではなかったに違いない。しかも奉行などを務める旗本に至っては、石高は一万石に満たない小身である。
そのような体制に正当性(納得感と言い換えても良いかもしれない)を与える仕組みこそが徳川将軍であり、それ故に将軍に求められる資質とは、権威を持っていることであった。幕末、この「権威の将軍」が異なるものへと変質していったということが、本書の主題である。
「権威の将軍」の放棄
13代将軍家定の健康問題を受けて、血縁の近い紀州藩主慶福(後の家茂)と、家康の再来と英明をうたわれる一橋慶喜の間での後継問題が発生する。権威こそが将軍に必要な資質であることを前提とすれば、血縁を重視して慶福が選ばれたことは自然だろう。
しかしながら、黒船来航以降の外交問題への対応は、徳川幕府による統治の正当性に疑問符を付けることになる。ここに至り、幕府が正当性を再び獲得するためには、「権威の将軍」は自らが政治・軍事のリーダーとしての能力を持つことを示さなければならない「国事の将軍」とならざるを得なかった。
そして、このような「国事の将軍」は、逆に将軍の権威ひいては徳川幕府の正当性の破壊を加速することになったと本書は説く。
政治・行政の正当性の再構築
現在の政治・行政においても、様々な利害関心を持つ多くの人々を一つの方向にまとめていくためには、正当性が求められることに変わりはない。憲法を筆頭とする法令、選挙による代表の選出と多数決制、"優秀な"官僚――これらは意思決定や判断を行うための実質的機能を持つとともに、そのシステム自体がある種の権威として正当性を支える機能をも持っていたといえる。
昨今の情勢を眺めると、これら全てについて、正当性を支えるという機能が低下しつつあるように思える。本書でキーとなる言葉を使えば、さしずめ「権威の政治・行政」から「国事の政治・行政」への変化による正当性の再構築が求められているということか。
その中で、徳川幕府において「国事の将軍」はむしろ正当性を低下させ、明治維新という最終解を導き出さざるを得なかったということは、心すべき教訓である。