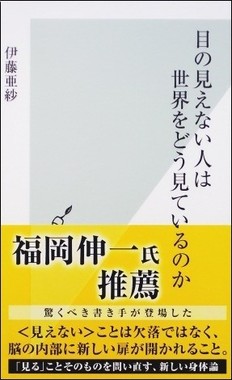■「目の見えない人は世界をどう見ているのか」(伊藤亜紗著、光文社新書)
2月に、周防正行監督の映画「舞妓はレディ」をバリアフリー・バージョンで観た。目の見えない人のために音声ガイドを、耳の聞こえない人のために日本語字幕を付けた作品である。
バリアフリー版を希望する者は、ゴーグルを着けヘッドフォンをかぶる。耳からは役者のセリフなどとともに各場面の解説が流れ、眼前のゴーグルには字幕が映し出される(もちろん、ゴーグルだけ使用することもできるし、ヘッドフォンのみ付けることも可能だ)。
最初は、情報過多でうっとうしいと感じたものの、慣れるにつれて、いつもとは違う感じで映画を観ている自分に気付いた。脚本のト書きのような場面解説を聞きながら、目をつむり、まるで本を読む感じで映像場面を想像したり、耳に入ってくるセリフと眼前の字幕の違いから要約の妙に感心したり、実に面白い体験だった。
目が見えない人が「映画を観る」なんて、悪い冗談かと思う方もいるかもしれないが、実際、このバリアフリー映画を体験してみると、映画はただ「観る」ことが唯一の見方ではなく、いろいろな楽しみ方があることがわかる。視覚障害者や聴覚障害者は、自分とは全く違う風に「映画を観ている」ことに気付かされた。
世界を違ってとらえているだろうと探究
本書は、目の見えない人がこの世界を実際どのように感じているのかをわかりやすく教えてくれる。友人から「面白いよ」と紹介されたのだが、読みながら、ちょうど、このバリアフリー映画体験を思い出した。
本書の著者は晴眼者。元々は生物学者を目指していたが、大学3年次に美学に転じ、「わかっているんだけど言葉にできないもの」をすっきりと納得したいとの思いが昂じて、生物学と美学の接点としての「体」に辿り着いた。しかも、従来の身体一般を論じた身体論では飽き足らず、生物の種が違えば体のつくりが違い、つくりが違うから世界のとらえ方が違うように、人間でも、ちょっと違う体の持ち主(視覚障害者)は、世界を違ってとらえているだろうと探究したくなったという。
本書では、著者が研究の過程で親交を結んだ視覚障害者に密着する中で、見えない人の感じ方などについて、筆者自身が気付き、考えたことを伝えている。目の見えない人と「友達」や「近所の住人」のような関係でいたいという筆者の素朴な思いを出発点とするだけに、その内容はリアルであり、新鮮な驚きに満ちている。
「見える・見えない」は「できる・できない」ではなく「世界の見え方の違い」
本書では、晴眼者には感覚的に知り得ない、視覚障害者にとっての世界が数多く示されている。
例えば、晴眼者は、月といえば立体としての球ではなく、「円」として認識しているが、生まれながらの視覚障害者は、月をボールのような球状をした形としてとらえているという。つまり、晴眼者は、絵や写真を通して、円く描かれた月が頭に刷り込まれており、月といえば、二次元の「まんまる」の形と思い込んでいるそうだ。他方、目の見えない者は、辞書の記述どおり、月を球として、概念的に正しく理解しているのだという。
富士山のイメージも同様で、晴眼者は「八の字の末広がり」、つまり「上が欠けた三角形」を連想しているのに対し、視覚障害者は三次元的に「上が欠けた円錐形」を心の中に描いているという
。つまり、晴眼者は自分で何度も目にした形に引き摺られて不正確な理解となっているのに、目の見えない者は、そうした経験にしばられることがないために、かえって正しい理解をしているのだ。
これは、中途失明者が、失明前にはコンビニに立ち寄ると、ついつい目に留まったキャンペーン商品を手にとってしまっていたが、失明後は、キャンペーン情報など視野にも意識にも届かないので、特に欲しいとも思わなくなり、必要な物だけを買うようになったという話につながる。
目の見える者は、見えるがゆえに、自らの経験や視野に囚われ、その視点からしか物事を把握できない限界があるが、見えない者は、情報量において制約がある一方、見えないからこそ、視点にしばられることなく、正しく認識し、「踊らされない」生き方が可能になっているというのだ。
また、視覚障害者は、見えない目に代わって、耳で「眺め」、足で「見て」、手で「探す」という。ベテランになると、初めての場所でも、周囲の会話や物音から、トイレはどこか、窓が開いているかどうか、家具の位置などをキャッチしている。足はサーチライトの役割を果たし、畳の目の向きから壁の方向を推測したり、自分の足元は土なのか、絨毯の上なのか、傾いているのか、平らなのかが、たちどころにわかる。著者の知り合いは、壁一面の本の中から、背表紙を触るだけで、目当てのタイトルを探し出してしまうという。
つまり、普通、目が果たすとされる「見る」機能は、他の器官でも果たし得るし、視覚障害者は、これらの器官をフルに活用して、「見て」いるのだ。
「面白い!」をベースとする、新しい障害との付き合い方
前述のように、視覚障害者の中には、しばしば、聴覚や触覚といった視覚以外の感覚をフルに使って、見る人にはできないような芸当をやってしまうことがある。そんな時、「すごい!」といって称賛するが、著者は、こうした特別視の裏には「かえって、見えない人は見える人ができることが(通常は)できないのだ」という蔑みの意識があると指摘する。むしろ、「面白い!」と思う感覚、「そんなやり方もあるのか!」という感触こそが、お互いの違いについて対等に語り合えることになるという。
特別視による神聖化は、かえって視覚障害者を遠ざけることになる。むしろ、「友達」や「近所の住人」のように身近に感じて付き合う方が楽しいと語る。「障害」という違いをなくそうとするのではなく、違いを生かしたり、楽しんだりする知恵こそが大切な場合があるというのだ。
本書では、「見えない人のための美術鑑賞」という興味深いイベントが紹介されている。彫刻などを触りながら鑑賞する手法は知られているが、本書の事例は、絵画や写真といった二次元作品を鑑賞するというものだ。目の見えない人と見える人がグループを構成し、作品の前で、時間をかけて、その作品について語り合いながら鑑賞するというスタイルだ。
「だいだい3メートルくらいのスクリーンが...見える範囲で3つあって、それぞれに映像が映し出されています」
「一つ目は雨が降っている様子、二つ目は人々が水に飛び込んでいる様子」
「飛び込んでいる水は...あまりきれいじゃないです」
「飛び込んでいるのは大人?子ども?」
「子どもです...とっても楽しそうで...」
決して、見える人による解説ではなく、みんなで一緒に見るという経験である。「ああでもない」、「こうでもない」と言いながら、作品を鑑賞する。時には、作品の解釈から離れて、「この作品を買うならいくら」、「飾るならどこ」と脱線していくのも面白い。著者曰く「筋書き無用のライブ感」に満ちているのだ。
通常の美術鑑賞では味わうことのできない、この場の盛り上がりは、著者の言葉を借りれば、「見えないという障害が、その場のコミュニケーションを変えたり、人と人との関係を深めたりする『触媒』になっている」という。
健常者が障害者をサポートする一方的な福祉の世界とは違う、「面白い!」をベースとした新しい障害との付き合い方のヒントがこんなところにある。
厚生労働省(課長級)JOJO