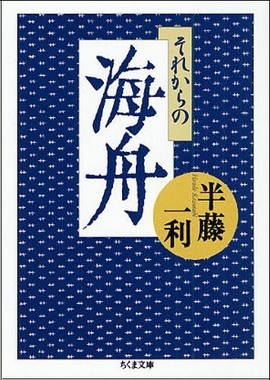「それからの海舟」(半藤一利著)
東京都大田区が「勝海舟記念館」を設立するとの報に接し、手にしたのが本書である。勝海舟のファンを自認する著者が、海舟の後半生、すなわち江戸城無血開城前夜から海舟の墓の始末までを活写する。
丁寧に資料収集した史実を基礎に据えつつも、他小説の描写も引用、のみならず憶測や感想さえも盛り込んで、とにもかくにも海舟の実像と魅力を存分に伝えようと筆を揮っている。海舟を「勝っつぁん」と呼ぶその行間に、著者が愉しみながら筆を進めたであろうことが窺える。
反骨のひと
著者は江戸っ子らしい明治維新観を持つ。
曰く「薩長軍は不平不満の貧乏公卿を巧みに利用して年若い天皇を抱き込み、尊皇を看板に、三百年来の私怨と政権奪取の野心によって討幕を果たした無頼の徒にすぎない」。だから官軍ならぬ西軍の錦の御旗についてさえ、制作の経緯を調べ尽くしてその権威を否定してしまう。
そして「徳川八万騎の反乱を抑え」江戸八百八町を戦火から護った勝っつぁんを称揚しながら、薩長土肥の「田舎侍」をこき下ろす。御維新の顕官も形無しだ。著者の反骨は筋金入りと見える。
主人公・勝海舟も反骨の人といえる。幕臣でありながら江戸城を開城し、他方で新政府にそっぽを向く。故に幕臣からも新政府からも疎まれ警戒される。批判文を送りつけられても、慇懃に礼を述べた上で「行蔵は我に存す、毀誉は他人の主張、我に与らず我に関せずと存候」と相手にすらしない。
海舟は歴史上敗者の側ではあるが、判官贔屓の語をあてはめるには事績が偉大に過ぎる。してみると著者の海舟贔屓は、偉人の反骨心に共鳴したものであろうか。著者の「海舟の歯に衣を着せぬ言は、まことにさわやかである」との言にそれが垣間見える。