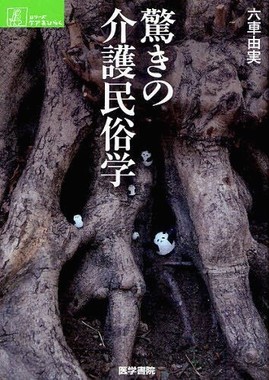「驚きの介護民俗学」(六車由実著、医学書院)
「君のお父さんは、高卒だったけれど、人の何倍も努力して、がんばっていたんだよ」。7年前、父の葬儀の際に、かつて父の同僚だった方から、意外な事実を教えられた。それまでずっと父は、特別の苦労もなく、大学に通い、就職し、無難にその会社を勤め上げたと思い込んでいた。家庭の事情で大学進学を断念したこと、就職後、夜間の大学に通い卒業資格を得たことなど、全く知らなかったのだ。
なぜ父がこうした若い時代の苦労を息子達に話さなかったのか、今となってはわからない。母は「高卒だったことを言いたくなかったのよ」と言うが、言い訳が嫌いで口数の少ない父のことを思うと、そのような説明もちょっと腑に落ちない。
40年を超える長きにわたり家族としてやってきて、父のことをそれなりに「知っている」つもりでいたが、自分が物心つく前の父のことは全くといっていいほど「知らない」のだ。
父の死は誰も予想しない突然の出来事だったから、私は、父がいなくなった寂しさ以上に、父のことを知る機会を失ったことを激しく後悔した。
◇ ◇ ◇
本書は、大学を辞めた気鋭の民俗学者が、福祉施設で働く中で経験した驚きの数々、すなわち、そこを利用する高齢者が語る物語がいかに驚きに満ち、ユニークなものであるかについて、人間味あふれる筆致で描いた本である。高齢者一人ひとりの子ども時代や青年期の記憶を「聞き書き」し、それぞれの「思い出の記」を作成することを通して、その記憶を保存し、次の世代に継承していく意義が語られている。
◇ ◇ ◇
本書を読みながら、私は、なぜか7年前の後悔を思い出した。「父からもっと聞いておけばよかった」と。
介護現場は「驚き」で満ちている
著者は、介護スタッフとして働きながら、民俗研究者としての過去の経験を生かして、高齢者の記憶や経験を「聞き書き」している。
「利用者たちの子どものころや青年期についての記憶に思わず触れる瞬間は、私に驚きと興奮と、そしてひとときの幸せを与えてくれている。老人ホームには、今ではムラの調査では直接出会うことのできない世代である大正一桁生まれはもちろんのこと、明治生まれの利用者もいる。また地元だけではなく、利用者の出身地は全国各地に及ぶ。そして彼らの記憶の何と鮮明なことか」
福祉施設には、戦前から戦後にかけて存在していた「忘れられた日本人」が数多くいるという。
・村々を回って役畜として使われていた牛馬の鑑定や仲買をしていた「馬喰(ばくろう)」
・農家の副業として、夜、飲み屋をまわる「流しのバイオリン弾き」
・村々を歩いて、蚕の尻を見て、雄か雌か、日本種か中国種かを仕分ける「蚕の鑑別嬢」
・専門職として母子家庭の生活を支え続けた「電話交換手」
――など、今では想像すら付かない職業生活を経験してきた高齢者が存在しているのだ。
著者によれば、認知症の高齢者からも、話を聞いたり、その行動を観察することを通じて、多くの発見があるという。
「一般的に老人ホームは、身体能力も記憶力も衰えた〝社会から見捨てられた〟老人たちが集まっているというイメージがあるのではないか。(しかし)子どものころから青年期についての彼らの記憶はかなり鮮明であり、ムラで出会うお年寄りたちに勝るとも劣らない記憶力の持ち主たちばかりである。それは認知症を患った利用者であってもあまり変わらない」
認知症の進んだ高齢者は、まずご飯を全部食べた後に、おかずの皿に箸を伸ばして平らげていくというように、ご飯とおかずと汁物を交互に食べていく『三角食べ』が難しいケースが多いという。しかし、「『三角食べ』の方が、ある時期の学校教育の中で強制された特殊な食べ方なのである。ましてやご飯が何よりものおかずだった時代を生きた利用者たちにとっては、ご飯からまず平らげるというのは自然なのであり、身体の深くにある記憶なのだ」
そして、何より、トイレこそがワンダーランドだという。トイレは極めてプライベートな空間だからこそ、トイレ介助を通じて、利用者との距離が縮まり、関係が深まっていく。そこで利用者の普段とは違った言葉や不思議な行動に接することができるというのだ。特に、認知症の方は、汲み取りトイレ時代の生活記憶の中に生きているようで、
・便器の中を覗き込み「なんだか怖いようだね」と呟いて、出て行ってしまった
・便器に向かって手を合わせ深々とお辞儀をし後退りして出て行ってしまった
――などの行動が見られるという。
また、ある認知症の女性は、昔の農家の女性が畑でしていたという立ちションを彷彿させるように、男性の立ちション用トイレの縁におしりをつっこんで用を足していたそうだ。
著者が「○○さん、むかし、立っておしっこしていましたか」と尋ねると、「そりゃしてたさー、百姓だもの。みんなしてたよ」との返事だったという。