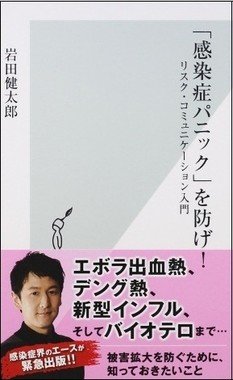『「感染症パニック」を防げ!リスク・コミュニケーション入門』(岩田健太郎著、光文社新書)
「デング熱」、「エボラ出血熱」と、今年は、見慣れぬカタカナの病気がメディアを賑わした。デング熱では2カ月近くもの間、代々木公園等が閉鎖される事態となったし、エボラ出血熱では、発熱した西アフリカからの入国者が隔離され、「日本でも患者発生か?」と徹夜で検査結果を固唾を飲んで待つという大騒ぎとなった。
幸いにして、現時点で、日本ではこれらの感染症のために死亡した者は確認されていないが、これらの話題が、今年の重大ニュースの一つとなったことは間違いない。
感染症は、伝染(うつ)り、広がるだけに、「怖さ」を伴う。この「怖さ」がパニックを生み、更に被害を拡大させてしまう。本書は、アメリカでの炭疽菌事件(2001年)、北京でのSARS騒動(2003年)、神戸で発見された新型インフルエンザ症例対応(2009年)といった数々の感染症対策に従事した著者が、無用で有害なパニックを防ぐために、政府や医療機関は、どう行動すればよいかについて、様々な喩(たと)えを用いて、わかりやすく解説したものである。
「感染症パニック」の影響は甚大
「ワクチン後進国」等と呼ばれ、感染症対応では「ダメダメ」と言われる日本に対し、米国は、1万5千人余のスタッフを擁するCDC(疾病予防管理センター)を中心に、積極果敢な対応で「お手本」とされてきた。しかし、今年は、エボラ出血熱騒動で受難の年となった。
特に、10月に、エモリー大学病院で、西アフリカから連れ帰った患者(医療従事者)から看護師が二次感染する事態が起こって以降は、米国全土が蜂の巣を突ついたような騒ぎとなった。「西アフリカ諸国からの入国は禁止すべき」、「医療支援から戻った医療従事者は、現地で感染防護措置を採っていたとしても潜伏期間中(21日間)は外出禁止にせよ」等といった「乱暴な」議論が横行。本来、こうした過度なパニック反応を抑える役目を果たすCDCも、「二次感染を防げなかった」ことで、信頼を失い、混乱に歯止めをかけることができなくなってしまった。
一連の騒動は、オバマ政権への不信を増幅し、中間選挙での民主党の敗北にまで影響したという。現在のところ、米国でのエボラ出血熱の感染者数は4人(死者は1人)にとどまっており、被害の程度を考えると、騒動の大きさが際だっている。もちろん、騒ぎが大きくなった背景には、中間選挙という「政治的要因」もあったのだろうが、「感染症パニック」がもたらすインパクトがいかに大きいかがわかる。
日本も例外ではない。エボラ出血熱に関しては、これまでのところ、幸いにして患者は未発生だが、先般の3例の疑い症例が明らかになったときの報道ぶりを見ても、万一の時のパニック・リスクは否定できない。仮に、患者発生という事態が生じても、パニックの発生を防ぐには、二次感染拡大の防止徹底とともに、効果的なリスク・コミュニケーション(リスコミ)を実施できるかが鍵となる。