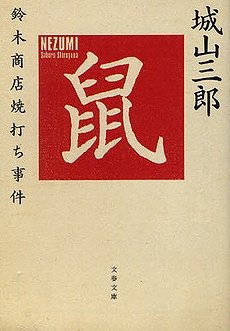「鼠 鈴木商店焼打ち事件」(城山三郎著、文春文庫)
城山三郎、30代の傑作である。戦前の新興総合商社である鈴木商店について、名番頭と名高い金子直吉を主人公に据え、歴史における「真実」とは何かを問うた書と言える。
歴史は「正しい」のか
米価が高騰する中、米を買い占めたとして焼き打ちに遭い、その後、金融恐慌で資金繰りがつかなくなり倒産したとされる鈴木商店。悪どい守銭奴のイメージと裏腹に、その番頭であった金子直吉を直接に知る人は、揃ってその人柄を褒め称える。著者はそこに違和感を見出し、綿密な調査を開始する。
本書は、そこで歴史として知られている事実と、調査によって得られた事実との乖離を淡々と描き出す。執筆の動機らしきものとして、著者は「不遜な歴史。歴史は、無数の違和感を歯牙にもかけず歩み去る。やがて、わたしたちはその違和感ごとアブクのように消え、歴史はより誇らしげに歩を進める-それが気に入らない」という。そして、少年兵となり戦後価値観の逆転を経験した自身の来歴と併せ、歴史に一矢報いる覚悟を語る。
その筆致の迫力と、事実を丹念に追いつつ、主観を排した記述とのギャップが印象深い。
ジャーナリズムと学究への懐疑
著者の目的は、鈴木商店の名誉回復ではあるまい。鈴木商店の一事を以て、歴史というよりも人間活動の過ち易さを述べたかったのではあるまいか。
当時の新聞報道はどうであったか、またその後の歴史検証における学者の仕事がどのようなものであったか、そして焼き打ちの背後にどのような勢力のどのような思惑があったのか。そういった事柄を、多くの生き証人にインタビューを行い、一次資料にあたり続けることで、浮き彫りにさせていく。
いわば調査報道の王道を往くかのような丁寧な作業と事実の適示である。他方で当時の報道について、著者はこう記す。「新聞はつくられるだけでなく読まれるものである。攻撃が重なるにつれ、第三者である多数の民衆が、鈴木に対する悪い虚像を徐々に持たされて行く。重なれば重なるほど、虚像は実像となる。」
学問なるものにも容赦はない。米騒動に関する権威ある研究書について、著者はそこで引用される文書の証言者を訪ね歩き、鈴木商店に関する証言が「三つとも信憑性のないものとわかった…予断に満ちた圧縮と言ってもよい」と結論づける。
これはそのまま、当時あるいはその後の戦後社会における報道や学問のあり方に対する一つの挑戦であろう。伝聞のみで構成される報道や学説の危うさを、これほどまでに鮮やかに、しかも批判的記述を極力抑制した事実の積み重ねで示した書を、浅学菲才の評者は知らない。
人間讃歌としての城山文学
むろん、城山三郎の小説である。歴史への挑戦を一通り片づけた後には、いよいよ鈴木商店大活劇と相成る。
主人公にして鼠のような風貌の金子直吉の発想力と純粋さ。支配人・西川文蔵の人柄。高商派の頭目たる高畑誠一の剛胆さ。登場人物は、いずれ劣らぬ光彩を放ち、勃興期にある若き日本の屋台骨を担う自負が横溢している。
鈴木商店は、現在の神戸製鋼所、帝人、双日、太陽鉱工、日本製粉、J-オイルミルズ、ダイセル、サッポロビール、昭和シェル石油などにつながる原点となった総合商社である。鈴木の破綻は歴史的事実だが、破綻という将来に待つ運命を読者が知るからこそ、鈴木の隆盛と登場人物の痛快とも言うべき活躍は、一層その輝きを増す。
そこでは、学生時代に洗礼を受けたという著者の、人間を観る温かさを感じる。そこまで考えて、著者が当時の新聞社の幹部に対しても、決して批判的な書き方をしないことに気付く。してみると本書は、歴史との対峙の書であるとともに、人間讃歌でもあろうか。
当時の歪んだ報道やその後の偏向した研究に対する違和感は大いに示されるが、どのような局面であれ、個人を名指しで断罪することはない。本書の中盤に詳細に語られる長谷川如是閑との対話はまさにそうである。また、終盤にイニシャルで語られる鈴木商店のアウトロー?達の描写もそうである。
人間は過つ。それを赦しつつ、しかし過ちをいかに防ぐか。現代日本の報道のあり方にも通じる本書の問いかけは重い。故城山三郎氏の偉業に改めて敬意を表するとともに、鈴木商店を原点とする各社の隆盛を心からお祈りしたい。
酔漢(経済官庁 Ⅰ種)