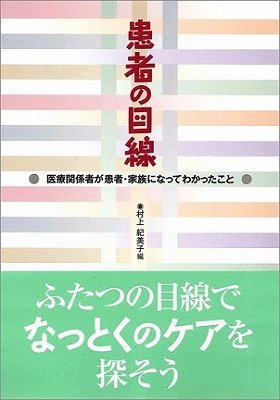「患者の目線 医療関係者が患者・家族になってわかったこと」(村上紀美子編、医学書院)
職業柄、30歳を過ぎた頃から、毎年人間ドックを受診しているが、近年とみにその時期が近付くと憂鬱になる。血液検査は、ところどころ正常値を外れるようになり、内視鏡検査等を受けると精密検査に回される場面も出てくる。その上、肉親を看取り、加えて、家族が相次いで「がん」に罹るというシビアな経験も重なって、評者にとって、「医療」は仕事の対象であると同時に、今や「自分事」でもある。
そんな事情もあってか、医療関係者が自分や家族が「がん」や「難病」と診断されたときに、どのように感じ、考え、行動するのかがとても気になる。数多くの患者を診てきたのだから、「自分事」となっても、淡々とその事実を受け止め、合理的な治療を選択し、これ以上の治療効果は望めないと悟ったら、潔く死を受容する。そんなイメージがある。 本書は、20人の医療関係者が患者・家族となったときに感じたこと、考えたこと、困ったことなどを率直に綴った体験ドキュメンタリーレポートである。
医療関係者といえども、患者・家族としての気持ちは同じ
がん患者の相談支援を熱心に進めている、ある消化器外科医の告白(妻のがん騒動)を読み、医師といえども、自分事となると同じなのだと感じた。
「"がん"と聞いた瞬間から、本人も家族も気もそぞろになり、本当に周りの空気の色が変わるような体験でした」
「(休み明けに行われるPET検査を待つ連休の間)いろいろなことが頭をよぎり何も手につかなくなった、というのが本音でした。それでも、淡々と家事などをこなす家内を見て、"女は強い!"と実感しました」
「(内視鏡による簡単な手術とは頭で理解しつつも)『術中に何か起きたら…』、『目が覚めなかったらどうしよう…』など、心配は尽きませんでした。1時間半後に回復室に戻った家内と話ができたときには、手を握り安堵したことを思い出します」