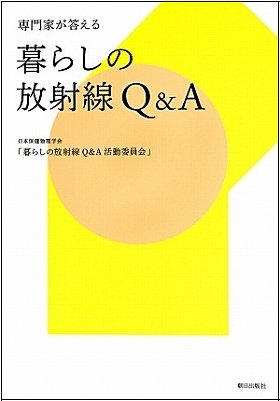東京電力原発事故後大きく報じられている放射線の話は、とても気になる。この問題については、事故当初の危機的な状況下で、政府のほか、マスメディア側も明らかに混乱をきたしていた。その後、事態がとりあえずの落ち着きを取り戻しても、原発をめぐる厳しいイデオロギー対立を反映して、放射線の影響について、首をかしげるような不安をあおるだけの極端な情報の流布がいまだに続く。
市民の知識は断片的
「専門家が答える 暮らしの放射線Q&A」(日本保健物理学会「暮らしの放射線Q&A活動委員会」著 朝日出版社 2013年7月)は、原発事故後、2013年1月末まで、放射線防護の学会である日本保健物理学会の有志が、学会の理事会の承認を得てサイトを立ち上げ、受け付けた質問1870件の中から、代表的な80件を選んで書籍にまとめたものだ。
ごく普通の市民の質問の分析から、放射線の知識がほとんどないか、あっても断片的で知識が体系化されていないこと、健康影響のメカニズムが腑に落ちないこと、「危険=その物質が元来もっている危険性×量」という量の問題が理解されていないこと、などが浮かび上がってきたという。著者たちは、被ばくによる線量は放射線の種類とそのエネルギーおよび放射線の量(数のこと)によること、また人体影響は放射線量によること、だけでも正確に伝わっていれば、質問内容も件数も変わっていたのではないかとする。
また、他の化学物質(ヒ素やダイオキシンなどの発がん物質)などに比べて放射線の影響については格段に理解が進んでいるという。それは、人類がこれまでたくさんの放射線障害事例を不幸にも積み重ねてきたからだそうだ。低レベル放射線の研究は、他の化学物質ではおよそ考えられない微細なレベルの研究だとの指摘はとても示唆深い。
本書の「直後の混乱を振り返る」(質問1~13)、「子供を抱えて」(質問14~26)、「日々の暮らし」(質問27~38)、「福島に生きる」(質問38~51)、「放射線被ばくとその影響」(質問52~67)、「専門家不信に抗して」(質問68~80)の各回答は、当時の生々しい状況を彷彿とさせるし、回答しにくいことにも誠実に対応していたことがわかる。
先例にならないチェルノブイリ
物理学者の菊池誠氏と福島県郡山市に実家があるミュージシャンの小峰公子氏の素朴なところからの質疑を収めた「いちから聞きたい放射線のほんとうーいま知っておきたい22の話」(筑摩書房 2014年3月)も不安をあおる議論に対する解毒剤として一読に値する。
旧ソ連時代にウクライナのチェルノブイリ原発事故で問題となった甲状腺がんの問題は、放射線論争の最大の焦点の1つだ。ただ、様々な研究機関で行われている被ばく線量推計によると、チェルノブイリに比較して福島における県民の被ばく線量が低いことがわかってきている(「平成26年3月11日「報道ステーション」の報道内容についての福島県立医科大学放射線医学県民健康管理センターの見解」(平成26年3月12日公表)、「原子放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR)報告書:福島での被ばくによるがんの増加は予想されない」(平成26年4月2日公表:国連広報センターに邦訳))。
メディアに求められる正確さ
元新聞記者の問題提起の書「官報複合体 権力と一体化する新聞の大罪」(牧野洋著 2012年 講談社)によると、1912年12月、コロンビア大学ジャーナリズムスクールで、1期生にピュリッツァー賞創設者の息子のラルフが講演で、「父にとって新聞記事の正確性は宗教のようなものでした。(中略)ニュースが正確であるかどうかの検証作業は新聞にとってますます重要になっています。責任ある新聞であれば、ニュースの発掘に四ドルかけるとすれば、そのニュースが正しいかどうかの事実確認に六ドルかけるべきでしょう。」と述べたという。不正確な批判記事は「権力側から攻撃されるのはもちろん、読者の信頼も失いかねない。」との著者の指摘を、報道の自由を担う関係者は重く受け止めるべきだ。
経済官庁(課長級 出向中) AK