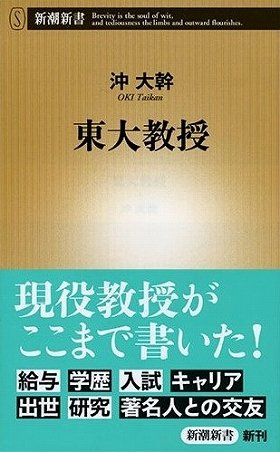「東大教授」(沖大幹著 新潮新書)
仕事柄、「東大教授」とご一緒する機会が多い。審議会、研究会等の委員として政策等についてご意見をいただくほか、研究費の審査のために研究計画書の評価をお願いすることもある。大学教授があまた存在する中で、国政に関係する東大教授の割合は多いように思う。立地上、霞が関に近いこともあろうが、「東大」というブランド(権威)も影響しているのかもしれない(最近は、ずいぶんと地盤沈下している感じもあるが…)。
本書は、その「東大教授」が自ら、給料等の待遇、どうすれば東大教授になれるのか、政府の仕事への関わり方、醍醐味は何か、研究や教育の苦労等について、率直に語っている。やや東大教授へのこだわりが鼻につくところもあるが、これまで、よく知らなかった「東大教授」の実情について、当事者がどう感じ、考えているのかを教えてくれる。
東大教授という仕事は、給与が保障された自由業
「東大教授」という肩書きを持つ者は約1300人(外部資金によって雇用されている特任教授を含めると1400人)と、意外に多い。
給与は、税込みで約1160万円(平均年齢55歳)。米国では教員間格差が大きく、ハーバードやUCLAだと約2000万円であるのに対し、州立大学等を含めた大学教授の年収の中位値は620万円とのこと(多くの大学では休み期間中を除く9カ月分しか支払われないという)。著者(東大生産技術研究所教授)曰く、定年まで全員在職でき、教授会等での投票権も平等に1票が保障されるなど、待遇を総合的に考えると、米国の大学よりも東大の方が恵まれているという。
本書では、給与の他、「教授になるまでの平均的キャリア」、「東京大学名誉教授の条件」、「制約のない勤務時間」、「なぜ学長ではなく総長と呼ばれるのか」など、部外者がちょっと知りたいトリビアが解説されている。
興味深いのは、東大の場合、待遇が業績にかかわらず変わらないこと(給与が増えるのは、大学の管理運営業務に携わる場合、つまり、総長や理事等の管理職となるケース)。著者は、この平等主義こそが「東大に未だに息づく学問の自由を支えている」と説く。
「目覚ましい成果が上がっても上がらなくても、世間に認められようが認められまいが、大学内ではほぼ同じように遇されるからこそ、結果が出るかどうかの確信が持てずとも学問的に重要だと信じる新しい研究に挑戦できる」
「仮に政府や社会、企業など様々な関係主体から当初は嫌われたり邪魔されたりする研究課題であっても、究極的にはきっと人類社会のためになる、という自らの信念さえあれば、それぞれ研究に打ち込める」
「本当に給料に不満があれば転職すれば良いのですが、ほとんどの先生が、どんなに世界 的な大研究者でも普通の教授とほぼ変わらない待遇、給与で勤務し、東大で定年を迎えられます」
著者曰く「東大教授という仕事は、給与が保障された自由業」だという。「お金」よりも、東大教授であることに伴う「自由と名誉と責任」にこそ価値があるとのこと。
政策への関与――政府の委員会での立ち振る舞い――
文明開化の時代には、「官」と「学」が一体として運営され、東大教授がそのまま役所の官職を併任していたこともある(初代の内務省土木技監の古市公威氏や第5代中央気象台長=現在の気象庁長官=の藤原咲平氏)。
今日でも、政府の審議会等に東大教授が委員として就任していることは多い。著者自身も国土審議会委員に就いているほか、各種国際交渉に日本政府推薦の専門家として出席することも多いという。
こうした社会的役割について、著者は、「東大教授が専門として深く学究し、世界の誰よりもまあまあ良く知っている事象はこの世のほんの一部に過ぎません。しかし、一芸に秀でるものは関連した芸にも通じているのではないか、という世間の期待を背負い、社会の意思決定や判断に対して知識人として助言する機会」であり、「教育研究活動に対する国民社会からの公的支援への対価として当然の義務」だと語る。
とはいえ、「御用学者」のレッテルを貼られることは本意ではないし、政治や政府との緊張感や距離感をどう保つかは難しい課題だという。「個人の見識と良心に基づき、できるだけ良かれ、と思う方向に結論が落ち着くように努力すべき」であり、「(反政府側や政府側の)両者から嫌われようとも賛成側、反対側、両方の理屈や気持ちを理解し、両者が歩み寄れるような道筋を考え、その方向へ誘導するのが大学教授の役目」と語る。
興味深かったのは、著者が語る、政府の会議で発言する際の二つのポイントだ。
①単に意見を述べるのではなく、答申案や報告案等の文書のどこをどう加筆修正すべきかを具体的に提案すること
②長々コメントせず、発言時間を厳守すること
確かに、的確な指摘だと思う。
後進を育てることが醍醐味
著者曰く「講義は東大教授の自己啓発の源」であり、「教室は教員の晴れ舞台」だという。「東大教授をしていてありがたい点は、極めて優秀ではあるけれど若者、ばか者、よそ者である新入生に毎年講義をし、専門分野を教える機会があって、その度に学生の新たな視点からの質問やコメントを受けて学べる点です」
しかし、時代は変わり、学生気質も大きく変わったという。
それでも、国家百年の計は、人材の育成、すなわち教育であると著者は語る。
「社会に出て将来様々な分野で活躍し、日本と世界の幸せな生活を支えてくれる可能性が高い東大生達に、講義や論文指導の場を通じて思うところを伝えられるのは、この上ない楽しみです」
本書を読み、「東大教授」をうらやましく思ったのは、後進を育てることの醍醐味だ。本書の随所で取り上げられている、著者の元から羽ばたいていった若手が、様々な場所で、素晴らしい業績を挙げ、新しい知見を切り拓いていく様子は実に見事だ。これこそが教育者たる東大教授が味わうことができる最上の喜びであろうし、日本社会に対する最大の貢献だと思う。
厚生労働省(課長級)JOJO