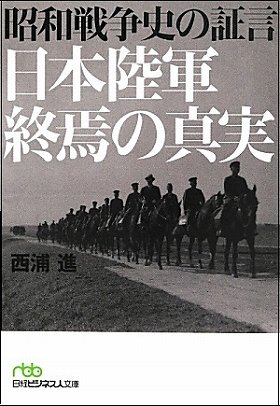「昭和戦争史の証言…日本陸軍終焉の真実」(西浦進著、日経ビジネス人文庫)
本書は旧軍人の著作であるが、いわゆる戦記ではなく、戦闘や戦場の記述は一切ない。陸軍のいわば実務官僚であった著者が、支那事変から今次大戦にかけての陸軍省勤務時代の回想をつづったものである。
著者は昭和6年(1931年)に陸軍砲兵大尉として陸軍省軍務局編成班勤務を命ぜられてから十余年にわたり軍事課に在籍し、予算班長など要職を歴任して17年から19年には課長を務めた。当時陸軍中央には、軍政を掌る陸軍省、統帥部すなわち最高司令部である参謀本部、教育を担当する教育総監部の三官衙が置かれていた。陸軍省には大臣の下に八局があったが、軍務局は最右翼の部局で、中でも軍事課は「一般陸軍軍政」、「陸軍建制」、「陸軍予算ノ一般統制」等を所管しており、参謀本部作戦課と並ぶ陸軍の中枢であった。
気負いなく淡々とした筆致で語る証言は、日本陸軍軍政の裏面史としての価値が高いが、実務の詰めを重視した合理的な指摘の数々は、現代に生きる我々にも大いに参考になる。
上級者の不勉強が陸軍下剋上の一因
著者が最も嫌うのは、実務を軽視した観念論や大言壮語であり、言い換えれば不勉強である。本書には、高級幹部の事務不勉強を指摘する箇所が多い。各局長が出席する予算省議の場で、「自分の局の仕事とは知らず、他局の担当だと思って強硬に予算削減を主張した局長」がいたとか、「幕僚の作文した報告書を尤もらしく読み上げるが、…部下の数が1万5千なのか2万なのかもはっきりつかんでいない将軍が少なくない」というような具合である。著者は、陸軍の下剋上の原因の一として、上級者の不勉強が下僚の増長を招いたことを挙げており、その観点から東条英機陸軍大臣の勉強熱心を「一般の上級将校の如く過去の智能の惰性で仕事をしている人とは違った」と評価している。(「不勉強」や「過去の智能の惰性」といった指摘は、高級幹部や上級将校ならぬ一小吏の筆者にも耳が痛い。)
高等司令部・中央部に 「事務の実兵指揮能力」欠如
また著者は、ペーパープランとしては立派だが実際には空転してしまった例、つまり事務能力欠如の事例を再三指摘する。例えば、昭和18年(1943年)、著者は、米潜水艦による船舶被害が増大する中、最も期待された対策であったはずの対潜音波警戒機が全く成果を上げていないことに気付く。関係者を軍事課長室に集めて生産から取り付けまで1台ずつトレースしたところ、輸送途中でストップしていたりして、生産された百数十台のうち、実際に船に取り付けられていたのはわずか2台でそれも取扱い訓練中であったことが判明した。あるいは、昭和19年秋のレイテ決戦時、著者は、戦場に送った新鋭戦闘機の稼働率が低く、数十機の戦隊中稼働機が2、3機しかないという声を聞き、調査に乗り出す。搭乗員から話を聞き、また飛行機の生産現場から発送の各過程をしらみつぶしに調べると、フィリピン進出前に上海で待機中、連日防空任務にあたっていたため上海出発時には既にオーバーホールの時期を迎えていたというような事情が次々に判明する。そして著者は、丁寧に調べて全体を総合調整すれば解決できる問題であることを指摘し、高等司令部や中央部の人々に「事務の実兵指揮能力」が欠如していたことを嘆くのである。このあたり我々も大いに参考にすべきであろう。
組織人に一読を推奨
このほか、中央官衙の機構改革についての「機構改革は…複雑なものになりやすい」、「機構改革は…関係部課の業務を著しく停滞せしむる」等の指摘はじめ、全編にわたる冷静で理知的な指摘は実に興味深い。
官公庁や企業に勤める組織人の諸兄姉に一読をお勧めしたい本であるが、それにしても「日本陸軍終焉の真実」という書名は何とかならぬものだろうか。ちなみに、昭和55年(1980年)に本書が単行本として刊行された際の書名は単に「昭和戦争史の証言」であり、昭和22年に著者が私家版として執筆した時の原題は「越し方の山々」であった。
山科翠(経済官庁 Ⅰ種)