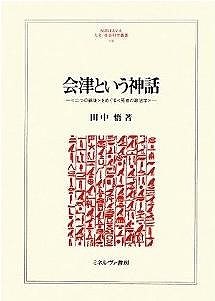今年の大河ドラマ「八重の桜」では、主人公山本八重を演じる綾瀬はるかさんの、凛とした会津弁が心にとても温かく響く。八重がかつて生まれ育った会津は、今、原発事故地から遠く離れているのに、単に福島県というだけで風評被害に苦しんでいる。この大河ドラマの後押しに、関係者の地道な回復の努力があいまって、会津地方の観光業なども愁眉を開いてきていて本当に嬉しい気持ちになる。
文化人類学者の山口昌男氏は、山本覚馬・八重兄妹など明治維新の「敗者」が京都の近代を創ったということを発見し、大河ドラマになる話だと語っていたそうだ。評論家の坪内祐三氏が、山口氏の追悼記事(産経新聞2013年3月14日付朝刊)のなかで、大仏次郎賞受賞作『「敗者」の精神史』(岩波書店 1995年 岩波現代文庫2005年)に関連して、いきいきと回想している。戊辰戦争後の八重についての今後の展開が楽しみだ。
「国民作家」が描いた悲劇
7月まで放映分の戊辰戦争の話までで、会津藩は、初代藩主保科正之公の遺訓に従い幕末の京都で治安維持の役目を引き受け、長州藩のうらみを買い、薩摩藩の政策転換で孤立し、幕府から見捨てられ、維新政府への恭順は認められず、絶望的な戦いの後、唯一藩を解体されてしまうことになる。江戸幕府や孝明天皇に忠義をつくした会津藩松平容保公のきまじめさを高く評価し、その顛末を同情的・悲劇的に描いたのが、「国民作家」である司馬遼太郎氏だ。1965年に発表された『王城の護衛者』(講談社文庫 新装版2007年)は、第2次世界大戦後、よるべを失っていた会津のアイデンティティの再確立に大きく寄与した。「街道をゆく33 奥州白河・会津のみち、赤坂散歩」(朝日文庫 1994年)も同様だ。
また、会津藩といえば、その紹介者として中村彰彦氏の一連の著作を忘れるわけにはいかない。藩祖正之公の英明さ・謙虚さを世の中に広く紹介した『名君の碑』(文春文庫 2001年)、幕末の会津藩などを概観する『幕末入門』(中公文庫 2007年)、魑魅魍魎の京都で会津藩の外交役として活躍した秋月悌次郎の生涯を描いた『落花は枝に還らずとも』(中公文庫 2008年)など、どれを読んでも会津への暖かな眼差しを感じる。吉村昭著『彰義隊』(新潮文庫 2008年)も、「賊軍」から戊辰戦争を描いた秀作だ。
戊辰戦争と第2次世界大戦を通じて
一方で、この大河ドラマでは全くよい所がなかった最後の将軍徳川慶喜の孤軍奮闘ぶりを描いたのが、練達の文芸評論家野口武彦著『慶喜のカリスマ』(講談社 2013年)だ。「あとがき」で、司馬遼太郎氏が作り出した日本における「明治維新ごっこ」の悪影響を憂い、現役世代の日本人は、歴史を学ばず、安易に大河ドラマで代替していると苦言を呈する。
今月は、日本では古来より死者と向き合うときだ。会津に関わる直近2つの戦争(戊辰戦争と第2次世界大戦)を通じて、近代における、戦争での死者への生者の受け止めを考察したのが、田中悟著『会津という神話―<二つの戦後>をめぐる<死者の政治学>-』(ミネルヴァ書房 2010年)だ。われわれは、すべての死者と向き合うことができるのか、どこまでの死者と向き合えるのか、という重い問題がテーマだ。この本ではなぜか論じられていないが、1997年夏に刊行され、大論争を生んだのが、加藤典洋著『敗戦後論』(講談社、ちくま文庫2005年)だ。「日本の三百万の死者を悼むことを先に置いて、その哀悼をつうじてアジアの二千万の死者の哀悼、死者への謝罪にいたる道は可能か」という問いかけは、氏自体の思想のその後の変遷にかかわらず、今もわれわれの前に依然としてある。
経済官庁B(課長級 出向中)AK
J-CASTニュースの書籍サイト「BOOKウォッチ」でも記事を公開中。