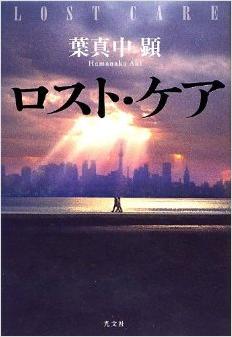本の帯に「日本ミステリー文学大賞新人賞受賞」、「社会の中でもがき苦しむ人々の絶望を抉り出す、魂を揺さぶるミステリー小説」とある。『ロスト・ケア』(葉真中顕、光文社)。
要介護高齢者とその介護者を「救う」ため、42人もの大量殺人を犯した介護従事者の物語。介護分野参入後、瞬く間にトップシェアをとりながら自滅したコムスンの不正請求事件を連想させる展開も描かれている。日頃、ミステリーなど無縁な評者だが、こうした評判を耳にして、思わず書店で手に取った。
介護保険後の日本の介護を描く
介護保険制度がスタートして今年で13年。本書に登場する看護師の言葉を借りれば、「やっぱ、介護保険が駄目なのよねえ。いかにもお役人が作ったって感じじゃない?」と酷評ばかりだが、介護保険前史を知る者の目から見れば、この制度の導入によって、日本の介護事情は大きく変わった。
評者が就職した30年近く前、ホームヘルパーは「家庭奉仕員」と呼ばれていた。連れ合いを失った男性単身世帯を中心に派遣され、掃除、洗濯、買い物といった身の回りの世話が主たる業務であった。寝たきり高齢者の介護は家族の役目。家族がいるのに他人を家に上げるなんて家の恥という感覚が一般的だった。認知症患者は、「呆け」、「痴呆」などと呼ばれ、今は主流のグループホームなどは存在せず、痴呆性老人対策という名称で、精神病院への入院が解決策と考えられていた。
そんな時代の介護文学と言えば、認知症や介護の問題を社会問題へと引き上げた『恍惚の人』(有吉佐和子)、老老介護の現実を男の立場から描写した『黄落』(佐江衆一)などが思い浮かぶ。
一方、本書は、介護保険スタート後の日本の介護を描く。介護保険ができても変わらない家族介護の過酷な現実、深刻化する認知症問題、そして、介護保険で急速に増えた介護従事者の厳しい労働環境などが活写されている。ただ、その視点は、要介護高齢者やその家族ではなく、介護労働者であることが新しい。
主役の一人が語る。「(介護保険は)駄目な制度だが、ないよりはあった方がましだ」、「(しかし)社会の軋みの大きさに、制度は追いつかない」、「今後、老人は更に増え続け、それを支える現役世代は減り続けるという。必要になった人が誰でも手厚い介護を受けられ、かつ、介護をする側に十分な報酬が支払われる――そんな未来は、どんな制度を作ろうとも、たぶんやってこない」。