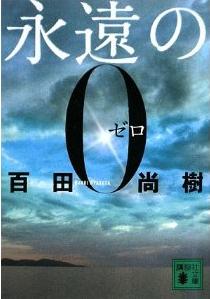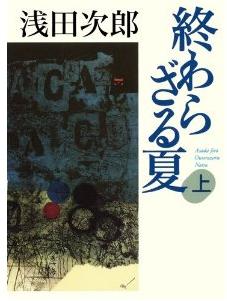戦争は多くの命を奪い、理不尽な悲劇をもたらす。その極限状況の中から数々の文学作品が生まれてきた。心に響く作品は戦争と平和への思いを新たしてくれる。この夏、手にとってほしい3冊を紹介したい。J-CASTニュースの新書籍サイト「BOOKウォッチ」
https://books.j-cast.com/でも特集記事を公開中
「臆病者」がなぜ特攻に志願したのか
『永遠の0』
太平洋戦争の末期、戦況悪化の下で多くの若者たちが特攻隊となって太平洋に散った。祖国のため自らを犠牲にして敵艦船に激突していったのだ。講談社文庫の『永遠の0(ゼロ)』(著・百田尚樹、920円)は、ある特攻隊員の謎をめぐる物語である。
終戦から60年目の夏、青年・健太郎は特攻で戦死した祖父の生涯を調べ始める。「娘に会うまでは死ねない。妻との約束を守るために」と言い続けていたのに、なぜ自ら志願して零戦に乗り命を落としたのか。戦友たちの証言から浮かび上がるのは、天才といわれるほどの腕を持ちながら臆病なまでに死を恐れていたという意外な人物像だった。ひとつの謎が浮かんでくる。そして、明らかになる真実。そこには、涙を流さずにはいられない、家族の絆があった。
北の孤島であった「知られざる戦い」
『終わらざる夏』
1945年8月15日、戦争は終わった。だが、北の孤島でその後も激しい戦いがあったことはあまり知られていない。千島列島北東端の占守島。ここに8月18日未明、日ソ中立条約を破棄したソ連軍が上陸、日本軍守備隊と戦闘になった。双方に多くの犠牲者を出したが8月21日に終結、捕虜となった日本兵はシベリアに連行、抑留された。
集英社からの『終わらざる夏』(著・浅田次郎、上・下各1785円)は、この占守島を舞台に戦争の恐ろしさと生きることの素晴らしさをうたいあげた大作だ。妻とひとり息子と共にアメリカへの移住を夢見ていた翻訳出版社に勤める男にある日、赤紙が届く。招集先は占守島だった。あの戦いは何だったのか。稀代のストーリーテラーが戦争を重層的に描き、人間の本質に迫る。
米軍捕虜を処刑した戦犯はなぜ逃亡したか
『遠い日の戦争』
福岡の西部軍司令部の防空情報主任、清原琢也中尉は終戦の詔勅の下った1945年8月15日、米兵捕虜を処刑した。無差別空襲で家族を失った多くの日本人に成り代わってその思いを遂げたと思っていたが、敗戦により価値観は一変、戦争犯罪の容疑者として追われる立場となり、逃亡を決意する。
新潮文庫の『遠い日の戦争』(著・吉村昭、515円)は、吉村作品に多く見られる逃亡小説の趣で、ストーリーはスリリングに展開するが、重要なのは、清原がなぜ逃げようとしたのかという点だ。そこには戦争犯罪とは何か、さらには東京裁判とは何か、という問いかけが込められている。また、著者特有の綿密な取材と史実の検証によって、戦後の価値観転換の混乱ぶりが見事に描き出されている。