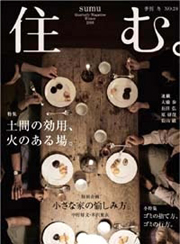岩手県盛岡市は、北上川と中津川、雫石川が合流する土地に栄えた城下町。その紺屋町の街道沿いに、南部鉄器「釜定」がある。
南部鉄器と聞いてすぐに思い浮かぶのは鉄瓶だが、釜定の最近の人気商品はオイルパンや洋鍋だという。シンプルで繊細で、使い勝手がよく、どこか北欧モダンを思わせる。
「日本の台所には物が多すぎる。整理して、すべてを賄える鍋とパンを、そして日本にしかない日本人の道具をと考えました」と「釜定」三代目の宮伸穂さん。
南部鉄器は鋳鉄の道具。内と外と二つの鋳型を土でつくり、その隙間に溶かした鉄を流し込んで成型する。
工房には長年使い込んださまざまな道具が並ぶ。しかし「何から何まで変わっている」と言う。
変えないものと変えてゆくもの

霰模様のある鉄瓶用の鋳型を修理する宮伸穂さん

オイルパン(右=40.5×21.5×H7.5cm 6825円)と鍋敷き(左=格子パネル小:13×13×1cm 2415円)
原料の和銑(わずく:砂鉄と木炭によるタタラ製造)は洋銑(ようずく:鉄鉱石と石灰、コークスによる銑鉄)になった。
また明治の頃までは、一つの鋳型から一つの製品しかつくれなかった。いまは鋳型を修理して繰り返し使う技術がある。その方が値段も安くできる。
もちろん手は抜かない。五十とも百とも数える鋳鉄の工程だが、宮さんは基本を大事に守りつつ、手仕事にしかできない部分を習熟させている。
「伝統工芸には、変えてはいけないことと、変えるべきことがあります。たとえば鉄は錆びる。錆びにくくするためには、材料を吟味することと、漆の焼き付けは変えられない。でも作業の効率を上げるためには、機械も取り入れる」。
いいものを、できるだけ安価に。実用の道具としての使いやすさ、道具以上の何かをもたらす魅力、きちんとつくる日本のクラフトマンシップ。
時代や流行に影響されず、いま必要とされるものをつくる現代のものづくり。
味の感じ方には個人差があるが、鉄瓶で沸かした湯はまろやかで美味しい。また、鉄器で料理すると、からだに必要な鉄分が摂れることが実証されている。
「住む。」編集部