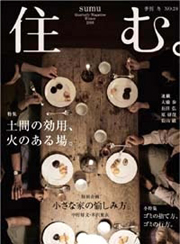ものを包む布を「風呂敷」と呼ぶようになったのは江戸時代のこと。銭湯に出かけるとき、湯道具や衣類を包んで運んだり、衣服を脱ぎ着するときに敷いたりしたのが由縁と伝えられます。風呂で敷くから「風呂敷」と。
布団を仕舞うときにも風呂敷は重宝

唐桟縞#181の3枚接ぎ(約110センチ角)5500円。5枚接ぎの一反風呂敷(約200センチ角)は1万5000円。取扱いの臼井織布では、風呂敷は受注生産になるので納期は約2週間。
当時は木綿や麻で織った反物を接ぎ合わせてつくられ、小さな一幅から、布団なども包める五幅までの寸法がありました。
近年では、持ち運びのために使うという役割は紙袋や布袋へと移行して、実用よりも冠婚葬祭や贈答の需要がほとんどになっています。
しかし最近また、繰り返して使える、畳んで仕舞えばかさばらない、包む物の形を選ばないなど、その良さが見直されています。
そしてもう一つ、風呂敷の良さは吸放湿性と通気性があることです。たとえば、押入に布団を仕舞うときにも、たいへん重宝します。
「住む。」編集部