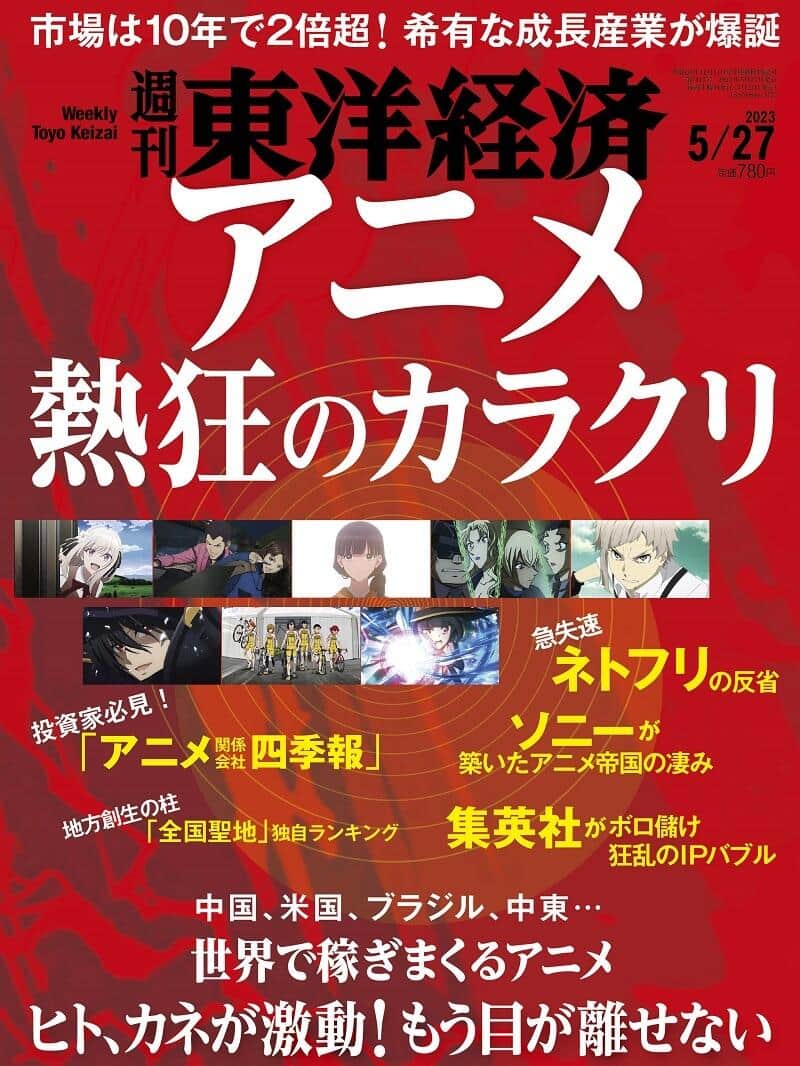「週刊東洋経済」「週刊ダイヤモンド」「週刊エコノミスト」、毎週月曜日発売のビジネス誌3誌の特集には、ビジネスパースンがフォローしたい記事が詰まっている。そのエッセンスをまとめた「ビジネス誌読み比べ」をお届けする(「週刊エコノミスト」は先週が合併号だったため、今週は休み)。
中国を介して調達される「電池」事情
2023年5月22日発売の「週刊ダイヤモンド」(2023年5月27日号)の特集は、「半導体 EV&電池 国家ぐるみの覇権戦争」。
米中対立の激化により、産業界では半導体に次いで、電池の調達リスクが高まっているという。世界最大の電池メーカー、中国の寧徳時代新能源科技(CATL)の日本上陸構想が浮上している動きを詳しく伝えている。
2020年ごろ、CATLが日本の自動車メーカーとの合弁で、電気自動車(EV)向け車載電池の工場を日本に建設する案が浮上したという。日本側の出資パートナーとして、ホンダと日産自動車の名前が挙がったが、構想は立ち消えになった。半導体に次いで、電池分野でも米中分断の様相が高まったからだ。
しかし、水面下ではその構想が再浮上しているという。主要自動車メーカーが野心的なEV販売計画を次々と掲げ、車載電池がひっ迫しているからだ。そこには中国抜きでは成立しえない電池の供給網事情がある。
半導体の場合、あらゆる主要工程を米国、日本、台湾、韓国、オランダが握り、西側諸国でサプライチェーンを完結できる。だが電池の場合は、中国を介さずに調達できる国は一つとしてない。
なぜなら、鉱物資源からレアメタルを取り出す精錬工程が中国に完全に握られているほか、電池製造では中国メーカーのシュアが高いからだ。世界首位のCATLの出荷量が46%に達するという。
すでにCATLは、中国EVメーカーにとどまらず、米テスラ、米ビッグスリー、日系大手3社など世界中のEVに車載電池を供給。「中国排除」のサプライチェーンは成り立たないのだ。
トヨタ自動車が2026年までにEV150万台を販売する計画を掲げた。「ついにトヨタがEVシフトに本気になった」という論調に対し、方針転換といえるほどの意味はないと疑問を呈している。
アメリカのZEV(ゼロエミッション車)規制を達成し、中国でのシェアを維持するには、EV150万台は最低限でもクリアすべき前提条件だと指摘している。
驚くべきは27年のEV構成比だ。欧州・中国ではほぼ半分に、米国でも35%に達している。新規参入者による下剋上は、トヨタ系列のサプライヤーを巻き込み、グループ瓦解を招くことにもなりかねないと危惧する。
◆日本の自動車メーカーの「部品調達力」
新型コロナウイルスの感染拡大以降、日本の自動車メーカーは半導体不足に悩まされた。同誌は、自動車7社の半導体を筆頭とする「部品調達力」を比較している。
最も部品調達力が弱かったのは、SUBARUだ。期初販売計画に比べて販売実績は21、22年度合計で45.6万台の減少(23.5%減)。当初計画の4分の1の車を顧客に届けることができなかったことになる。
ホンダと日産自動車も共に16.2%減の落ち込みだった。7社のうち部品調達力が最も高いと評価されたのがトヨタだった。販売台数における部品調達力では1.9%と影響は軽微だったが、生産台数で見ると6.8%減となっており、大きな減産を強いられたのは間違いない、としている。
今後、EV化が進むと、自動車メーカーとサプライヤー、半導体メーカーとの力関係が逆転する「下剋上」が起こるかもしれないと見ている。
世界的ベストセラー「半導体戦争」の著者である、アメリカの国際歴史学者、クリス・ミラー氏に米中覇権争いと日本復活の行方を同誌はインタビューしている。
それによると半導体争奪は、「国家ぐるみの覇権戦争」の様相を呈し、「半導体は破滅的な兵器になり得る」というのだ。EV市場で中国メーカーが急速にシェアを伸ばしていることに注目し、あと数年で中国は日本を抜いて最大の自動車輸出国になる、と予測している。
ほかに、同誌は、最新決算から半導体・電子部品と自動車・自動車部品の「存亡ランキング」を作成した。8つの指標から見た「市場原則でも生き残れる98社」では、首位は半導体材料のシリコンウエハーで世界首位シェアの信越化学工業だ。2位は東京エレクトロン、3位が村田製作所、4位ソニーグループ、5位キヤノンとなっている。
日本のアニメ市場規模は10年で2倍に
「週刊東洋経済」(2023年5月27日号)の特集は、「アニメ熱狂のカラクリ」。10年で市場は2倍以上に拡大。日本で希有な成長産業になったアニメをめぐるカネの話題を追っている。
連日、海外における日本アニメの快挙を知らせるニュースが飛び込んでくる。3月に中国でも公開された「すずめの戸締り」が、現地で興行収入150億円を突破。4月20日には人気バスケットボール漫画「SLAM DUNK」のアニメ映画も中国で後悔され、120億円に達した。
日本のアニメ産業の市場規模は2010年代の序盤まで1兆3000億円程度だったが、動画配信の普及で潮目が変わったという。ネットフリックスやアマゾンが、続々と日本アニメを買い付けるようになり、全世界でタイムラグなく日本のアニメが広まるようになった。
海外のアニメ映像やグッズ販売が急伸し、21年には市場規模が2兆7422億円と、この10年で市場は2倍以上になったのだ。
年間300タイトルもの新作が製作されるアニメ独特の経済構造を解明している。そのほとんどが「製作委員会方式」で生み出されている。
製作委員会とは、アニメ製作に出資した企業の共同事業体だ。取りまとめ役の「幹事会社」を軸に、アニメを企画立案、スタジオに制作を委託し、できた作品の著作権を共同保有。利益を出資者に分配する。
参加企業は出版社や映画会社、テレビ局、パッケージメーカーなどさまざまだが、欠かせない参加条件は、事業面で作品に関連性を持つこと、業界内で信用されていることだという。
出資比率は「あうんの呼吸」で決まるとされる。ヒットにつながりそうな原作の争奪戦は激しさを増している。分け前の争奪戦を繰り広げる製作委員会に対し、いつまでも好況にあやかれないのが、アニメ制作会社だと指摘している。
800社近くあるアニメ制作会社は、製作委員会から直接発注を受ける1次下請け制作会社(元請け)と、その下に連なる2次・3次下請け制作会社(下請け)からなる。中小零細が大半で、作品に出資する力がなく、ヒットの果実が分配されないのだ。
◆好況に沸く大手出版社
原作を持つ大手出版社は好況に沸いている。
集英社の2022年5月期は売上高1951億円、純利益268億円。10年代半ばは好調な年でも売上高1200億円、純利益50億円程度だったから、飛躍的に成長している。講談社も同様で、赤字が続いてきた小学館も息を吹き返したという。
各社の業績を押し上げているのが紙や電子の漫画だ。「週刊少年ジャンプ」を擁する集英社では、累計発行部数が1億5000万部を突破した「鬼滅の刃」を筆頭に、爆発的なヒットが続出している。
背景には、アニメ市場の拡大があるという。動画配信の普及により国内外で視聴者が増え、メディアミックスのシナジーが膨れ上がった。もう1つの恩恵が、漫画IP(知的財産)を生かしたアニメやゲーム、グッズ化による版権収入だ。
その裏で、さまざまな業界のアニメプロデューサーたちによる原作の争奪戦が繰り広げられ、出版社が開く「アニメ権」をめぐるコンペには20社が参加することも珍しくないという。IPビジネスには伊藤忠や丸紅といった商社も参入している。
「ブラック労働」ぶりが伝えられてきたアニメーターの賃金も氷河期から「二極化」の傾向があるという。平均年収は455万円と、4年前から15万円増えている(日本アニメーター・演出協会のアンケート調査)。出来高単価に加え、「拘束費」が上乗せされ、年収1000万円以上というアニメーターも出現している。しかし、若手アニメーターは拘束費の恩恵に与れず、生活は厳しいままだというのだ。
日本のアニメ業界における「台風の目」は、ソニーグループという見方を紹介している。
ソニーが手がけた代表的なアニメ作品が「鬼滅の刃」だ。子会社のアニプレックスは、アニメの企画・製作会社として業界最有力のヒットメーカー。その強すぎる存在感を懸念する声もあるそうだ。
このほか、アニメに活路を見いだすテレビ局やアニメの興行収入が急伸する東映、東宝といった映画会社の動き、ビジネスパーソンが押さえるべき最新教養アニメ20作、「アニメ聖地」ランキングなど、アニメ関連記事が満載だ。
今、アニメの「聖地」には、茨城県大洗町、山梨県身延町など、これまではあまり聞き慣れない地名も。登場作品と地域活性化の事例を知ると、その効果に驚くだろう。(渡辺淳悦)