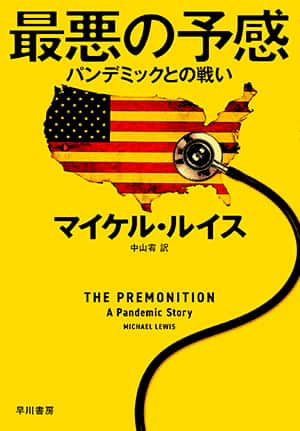アメリカの底力
アメリカにはパンデミック対策の計画が存在していた。ジョージ・W・ブッシュ大統領(息子)のときに生物学的な脅威に対処するチームがつくられたが、トランプ大統領になってメンバーは解雇または降格されていた。
そのチームの1人がダイヤモンド・プリンセス号での感染拡大について書いた部分が興味深い。「かすかな煙の気配だった」と書いている。
この時点で、アメリカ国内では新型コロナウイルスの検査は行われていないに等しかった。FDA(食品医薬品局)は、州や地域の保健衛生官に対し、CDCが提供する検査キットを持つように言い続けていた。しかし、CDCは、アメリカ人がこのウイルスに感染する危険性は非常に低いと主張していた。
役に立たない連邦政府と個人ベースでネットワークをつくり、危機を訴え、行動する人たちが対比して描かれる。このあたりは映画化を予想して小説的な手法を使っているが、事実であったことは間違いない。
CDCが検査キットの大量生産を試みたが、2回失敗したとか、判定に10日かかったとか、失敗のエピソードが書かれている。一方で役に立ったのは民間企業や大学、非営利団体が運営する微生物研究所だ。
「連邦政府がリーダーシップを発揮しないせいで、パンデミック対策用品の市場では自由競争が繰り広げられ始めていた。おもに中国製の商品をアメリカ人同士が競い合って購入するという図式だった」
新型コロナウイルスの感染が昨年(2020年)始まったころ、テレビのワイドショーではアメリカにはCDCという政府組織があり、多くの専門家が従事しているのに、日本は国立感染症研究所という小さな組織しかないので、ダメだ、と彼我を比較する声があった。だが、本書を読み、その実態を知り、愕然とした。「疾病対策」という名前はついているが、実際には患者を研究論文の対象としてしか見ていない官僚組織なのだ。
だからと言って、日本の政府や自治体の対応が褒められた訳ではないことは言うまでもないだろう。
アメリカはその後のワクチン製造において、巨大医薬品企業の底力を発揮し、世界にワクチンを供給している。「失敗」したが、その後の回復ぶりには目を見張るべきものがある。また、災厄の途中なのに、こうした実証的なノンフィクションが書かれ、映画化(ユニバーサル・ピクチャーズ)というのもアメリカ的だ。
翻って、日本でこういう作品が書かれるのか、考えてみた。多くの専門家がテレビに登場するが、こうした小説や映画には似合わない。また、本書に登場するような突出した個人もあまりいない。
冒頭に登場する少女のエピソードが、コロナ禍を終息させるための戦略として役立つことが終盤で明らかになり、伏線は回収される。ミステリーを読むように面白く、一気に読むことができるだろう。(渡辺淳悦)
「最悪の予感 パンデミックとの戦い」
マイケル・ルイス著、中山宥訳
早川書房
2310円(税込)