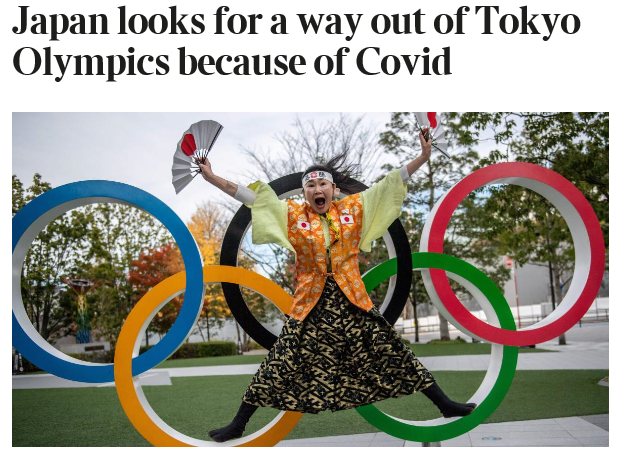今年(2021年)7月23日開幕予定の東京五輪まで半年を切った。
新型コロナウイルスの爆発的な感染拡大で、開催に反対する世論は8割を超えている。開催が危ぶまれるなか、ただ、「コロナに打ち勝つ証にする」と一つ覚えのように繰り返すだけのIOC(国際オリンピック委員会)や菅義偉首相に、新聞社説が堪忍袋の緒を切った。
開催に批判的な論調の新聞、賛成する新聞、双方の社説を読み解くと――。
日経コラム「IOC委員らVIPにも厳しいルールを課すべきだ」
「日本政府が東京五輪を中止せざるを得ないと内々に結論付けた」
と英国の有力紙「ザ・タイムズ」が報道して世界に衝撃が走ったのが日本時間の2021年1月22日だった。日本政府や東京五輪組織委員会は否定に大わらわだったが、全国の新聞では社説でこの問題を取り上げるところが相次いだ。
翌1月23日付以降に社説で取り上げなかった在京6大新聞は読売新聞と日本経済新聞だけだ(1月27日現在)。しかし、その日本経済新聞はスポーツ面のコラム「スポーツの力:無観客なら開催は可能か」(1月27日付)で、編集委員の北川和徳記者がこう訴えた。
「(国際オリンピック委員会=IOCのバッハ会長が無観客の開催に言及したが)観客を入れなければ五輪の開催が可能になるとはいかない。特に深刻なのは医療体制にかかる負荷。通常開催なら暑さ対策も含め期間中に1万人以上の医師、看護師が必要になる。無観客でもコロナ対策が加わる。国内のワクチン接種と大会時期が重なる。国民の理解は得られるのか」
「選手以外にも来日するIOCや国際競技連盟、メディア関係者らの感染対策も不可欠だ。その数は3万人以上。選手を外部との接触を遮断した『バブル』(完全隔離)環境に入れるなら、彼らにも厳しい行動制限のルールを課し、IOC委員らVIPにも従ってもらわなくてはならない。聖火リレーの開始も迫る。開催を目指すなら、感染者数の推移に一喜一憂している場合ではない」
と、一刻も早い決断を訴えたが、「事実上、無観客でも開催は無理だ」と主張しているに等しいように見える。
このように主要紙の論調は、影響が大きすぎることもあって、はっきりと「中止せよ」と訴えることを控えつつ、「事実上無理だ。もし開催したのなら、早くその方法を決断すべきだ」と行間で訴えるところが多い。
毎日社説「森会長や菅首相の精神論は説得力がない」
毎日新聞の社説(1月25日付)「東京五輪まで半年 現実見据えた議論足りぬ」は、森喜朗組織委会長や菅義偉首相の「精神論」では国民にまったく説得力はない、としてこう指摘した。
「IOCのバッハ会長は『(大会は)トンネルの終わりの光となる』と強気の姿勢で、組織委の森喜朗会長も『長い夜も必ず朝は来る』と語る。菅義偉首相は『人類が新型コロナウイルスに打ち勝った証し』と開催の決意を繰り返し、国会では『ワクチンを前提としなくても開催できるよう準備を進めている』と答弁した。だが、大会のコロナ対策に責任を持つ政府の説明としては具体性と説得力を欠く。何より今は現実を見据えた議論を急いで進める必要がある」
そして、仮に開催するというなら、早くコロナ対策を示せと主張した。
「最優先で検討すべき課題は明らかだ。変異ウイルスの侵入も予想される。昨年以降、欧米のプロスポーツの多くが無観客で実施されている。五輪も、無観客開催や観客を日本在住者に限定した方法が望ましいとの意見が出ている。 感染防止策では、隔離した環境に選手らを滞在させ、競技会場と宿舎を往復するだけの『バブル』方式を採用するアイデアもある。開催への危機感、関係者の具体的な動きが見えない現状を早く改めなければならない」
東京新聞の社説(1月25日付)「見えない現状を早く改めなければならない」は、開催の可否の現実を具体的な数字を挙げて、早く決断せよ、と迫った。
「これまで政府や都、組織委が『満員の競技場で全競技を行い、多くの観光客を入国させる』という最善プランに固執したことが、不安を招いた一因だ。 遅まきながら縮小案や中止案について検討し、準備状況や影響予測を公表する。そのうえでどの案を選ぶか丁寧に説明するべきだ」
として、影響のプラスマイナスを数字で示した。
「開催する場合は1万人超の選手、約8万人のボランティア、世界中から多くの観衆らが計30日間、複雑に行動する。ボランティアと医療スタッフを確保できるか判然としない。(無観客開催なら)チケット収入が減り大会収支は悪化する。観光客が来日しなければ、経済効果も乏しい。どんな形であれ開催するための大前提は、感染拡大を抑え緊急事態を早期に解消することだ」
「一方、中止する場合は約3000億円の追加支出は抑えられるが、支出済みと考えられる約1兆3000億円の開催経費、新設施設が意義を失う。チケット収入はゼロで、特需を当て込む観光や警備業界なども打撃を受ける。聖火リレー開始は3月25日。それに間に合うよう方針を国内外に説明し、理解を得ようとするなら残り時間は少ない」
朝日新聞社説(1月27日)「五輪の行方 現実踏まえた対応急げ」は真摯に人々の疑念と向き合えと訴えた。
「朝日新聞が1月23、24日に実施した世論調査では(開催に反対)と答えた人が86%にのぼった。世界で新型コロナの感染が収まる気配がないなか、当然の受け止めと見るべきだ。しかしIOCや日本の組織委、政府、都から聞こえてくるのは、『プランB(代替案)はない』『コロナに打ち勝った証しとして開催する』といった根拠不明の強気の発言ばかりだ」
「人びとの疑問や懸念に向き合い、とりうる道をともに探ろうという姿勢はうかがえず、溝が深まる悪循環に陥っている。前例のない事態に直面し、それでも五輪への求心力を維持しようとするなら、適切な情報開示と議論の透明化、衆知の結集が不可欠だ。ところが開催者側はその努力を怠り、逆に不信を深めた。開幕まで半年を切ったいま、納得できる工程表を速やかに示すことを改めて訴える」
主要各紙がやや歯切れの悪い論調を展開しているのに比べ、はっきりと「中止」という言葉を見出しに入れて、キッパリ主張しているのが広島市に本社を置く中国新聞である。
はっきり「中止」を打ち出す中国新聞と高知新聞
中国新聞の社説(1月18日付)「東京五輪 中止も想定すべきでは」は、スポーツの競技そのものが感染拡大の危険を負っていると強調する。
「感染急拡大は世界でも昨年(2020年)秋以降、欧米を中心に深刻になっている。これでは半年後とはいえ、安全な開催を確信できないのも無理はなかろう。『3密』を避けられない競技や合宿など、スポーツには感染リスクが伴う。実際に今月、相撲界では力士たちが共同生活する部屋で集団感染が発生した。水球では、日本代表候補合宿に参加していた選手が陽性と判定され、合宿は中止となった」
「コロナ禍は、五輪に対する国民の期待をしぼませた。再延期すべきだとの私見を表明したメダリストもいる。ボートで『金』を4個得た英国のマシュー・ピンセント氏は『順番変更を求め、2024年まで延期すべきだ』という。開催を4年ずつずらし、パリを28年、ロサンゼルスは32年とする案だ。検討に値するのではないか。五輪中止も含め、政府はあらゆる対応策の検討を急ぐべきだ。開催の決意ばかり語っても、冷めかけた国民の心に火はつくまい」
地方紙の高知新聞社説(1月26日付)「東京五輪 現実に即した議論進めよ」も、「中止」という言葉を見出しにこそ使っていないものの「中止せよ」という論調を、在京の主要紙よりも強く打ち出している。
「開催する、の一点張りでいいのか、懸念せざるを得ない。開催に当たっては、各国の国民の理解が欠かせないのではないか。1月初旬の共同通信による世論調査では『中止するべきだ』が35.3%、『再延期するべきだ』が44.8%で、計80.1%が見直すよう求めた。五輪よりコロナ対策を重視する考え方の裏返しとみていいだろう。現実に基づいて議論を進めるべきだ。再延期や中止を含め、早急に検討するよう求める」
「陸上女子1万メートル代表の新谷仁美選手は、テレビ取材に対し『アスリートとしては賛成、一国民としては反対』と率直に心境を語った。年齢や体力から東京五輪を競技人生の締めくくりと位置付ける選手は複雑な心境だろう。 『人類がコロナウイルスに打ち勝った証しとして』。安倍政権から続いてきた前のめりの決意ではなく、誰もが納得できる方向を示すべき時だ」
(福田和郎)