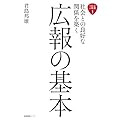焼却灰を1450度から1800度の高温で溶融
一方、日本環境保全(茨城県牛久市)は茨城大学工学部、茨城県工業技術センターと共同で、焼却灰の小型高温溶融炉(日本、台湾、韓国で特許取得済み)を開発し、アスベストの無害化に成功している。この溶融炉はA重油に還元水を混合し、特殊バーナーで油の中に微細な水粒子を混合させるエマルジョン燃焼方式により、焼却灰を1450度から1800度の高温で溶融することに成功した。アスベストだけでなく、ダイオキシン等の有害物質の発生も抑制し、溶融によるスラグ(鉱滓)化で無公害化処理を行う。
燃料はA重油だけでなく、廃油や再生油を使うことができるのでランニングコストが安くて済み、溶融後のスラグはリサイクルが可能という優れもの。現在はセシウムなど放射性物質の処理にも力を入れており、昨年(2013年)1月から2月にかけて福島県本宮市で神戸製鋼所とともに溶融実証試験を行った。日本環境保全の小型高温溶融炉は、1998年から1999年にかけて1年間行った実用化実証試験をはじめ、多くのメディアが取り上げている。ただ、廃棄物処理プラントは平成の大合併で大型化が進んだうえ、設備老朽化を受けて新しいプラントを導入するため、日本国内では導入事例が少ない。国内よりも早く、2001年に台湾高雄市に設置された。アスベスト、セシウム処理を追い風に、日本国内での設置に弾みをつけたいところだ。(管野吉信)