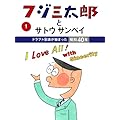今と地続きの時代を生きていた
「フジ三太郎」に登場する人物の顔ぶれはバラエティに富んでいます。三太郎の家族はおばあちゃんがいる三世代同居、家は一戸建てですが借家です。会社の上司には女性管理職がいて彼女は英語が達者です。
通勤途上のミニスカのOLに胸を躍らせますが、男女雇用機会均等法が施行され、職場ではもはやお茶くみが必ずしも女性の仕事ではありません。GWともなると、若手社員はこぞって長期の休みを取って海外旅行に出かけてしまい、職場に残るのは中高年オヤジだけです。
そう、「フジ三太郎」は、登場人物だけ見ても、戦後、日本の庶民像がモーレツに様変わりしていった時代の物語ということがわかります。古い慣習を引きずる老人もいれば、新しい考え方をする新入類に近い若手社員も登場します。
男尊女卑は否定され、職場での女性進出は止まらない。クルマ社会になり、マンションに住む人も増えて、生活の隅々まで利便性が高まる一方で、格差も微妙に広がり、公害などのマイナス面も指摘されるようになります。
社会の構造が変わり、階層分化が進む中で、人々の意識や生活様式、価値基準や規範も揺らぎ始める。そうした表面的には繁栄しているが、内部に不安定さを抱えた昭和後期の社会と人々の様子を、「フジ三太郎」は同時代記としてつづっています。それはまさに今の日本と地続きの、あるいは今を予見した姿です。
そのころ普通の日本人は何を思い、どんな行動をしていたのか。それは少し前の時代の日本人の姿と、どう異なり、あるいは変わらなかったのか。さらには今の私たちと…。「フジ三太郎」にはそんな高尚なことを考えるヒントもあちこちに隠されています。
一読して「くすっ」と笑った後に、じわーっと不思議な感情が湧いてくる――。そこにこそ「フジ三太郎」の比類なき面白さ、真骨頂があるといえるでしょう。