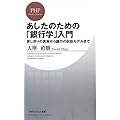原発停止によって、どこにどんな影響があらわれるのか
発電単価は、低い方から原子力、石炭、天然ガス、石油となるのが一般的だ。原子力発電所を止めれば、低い階段をなくして高い階段から始まることになる。
需要曲線の左側にある階段の面積が増えれば、コストはあがる。日本の電力料金制度はコストが上がった分を価格に反映することになっているので、そのまま利用者の負担になる。
日本における電力消費は、家庭用が3割、オフィスやスーパー、病院などが2割強ほどになる。こうした個人や法人は生活に密着しているので、電力料金があがっても海外に移るということにはなかなかならない。
一方、4割以上を占めるとみられる製造業は、日本のGDPの2割弱を占めていることを考えると、その集中度は高い。電気料金が安い海外への移転も起きやすい。前回提示した仮説のように企業の海外流出が日本経済にとってプラス効果であれば、少しは安堵できる。
さらに、原発の代わりに火力発電所を動かせば化石燃料の輸入額が増大する。これが日本の経常収支を悪化させ、国債金利、ひいては企業の貸出金利にマイナスの影響を与えるおそれがある。
何がどうなったら、どこにどんな影響があらわれるのか。100%確実に分かる経済モデルにはならないだろうが、モデルを組み立てることで、より客観的な議論を進めることができるのではないだろうか。(大庫直樹)