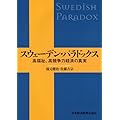イングヴァール・カールソン――。彼の名前を知る人は、日本にはほとんどいないと思う。スウェーデンの政治家。社会民主労働党党首、スウェーデン王国の首相を合計7年にわたり務めた。
僕がこの政治家のことを心に留めているのは、彼が社会民主労働党党首として真に国民に向けた変革を行ったからである。
増税を掲げて選挙に大敗し、次の選挙で大勝
ときに1990年、スウェーデンは付加価値税を上げざるを得ない局面を迎えていた。カールソンは、その難局に増税を決意した。
確実に次回の選挙には負ける。負けたとしても、やがて国民は増税の必要性に気づき、その次の選挙では返り咲くことができる。彼は、そう確信していた。そして、それは事実、大敗のあとの大勝となった。
みんなが受け入れたくないことでも、正しいと信念で思うのならば、身を切っても実行に移す政治家がいる。僕は感銘を受けた。そして、この物語を、ある金融専門誌の匿名コラムに執筆した。
僕は、カールソンのことを知ってから、彼についてもっと知りたいと思った。なぜ彼はこんなにも大胆な意思決定をすることができたか、と。根源的には、冷徹な社会・経済分析があったはずである。
1990年代になる直前に、日本よりも先行してバブル崩壊をスウェーデンも経験している。
バブルが崩壊すれば当然、経済不況は進展する。スウェーデンが世界的に注目を集めることになった高福祉政策も、財源不足、公的部門の肥大化、勤労意欲の低下など、さまざまな問題点が露呈を始める。高福祉政策を続けるにしても生産性の向上や財政面での裏付けが求められた。
あいまいなイデオロギーとしての高福祉政策の堅持ではなく、冷徹な財政面での分析があったこと。それが、正しい選択を行うための前提となった。
もうひとつの理由は、僕自身、彼と会って話したこともないから、これは推測の域を決してでるものではない。しかし、彼自身が首相の座にしがみつきたいタイプでは決してなかったことだと、僕は思っている。
中長期的な評価を心の支えとすること
多くの人が、大抵の場合、正しい判断ができなくなってしまうのは、今ある地位を少しでも長く維持したいからだ。組織に属し、その中で自分の地位を守ることに執念を燃やす。
でも、91年の総選挙前にカールソンはあっさりと自分の地位を捨てる判断をしたはずだ。そのときの世論、社会的な風潮、マスコミのする支持率調査を考えたら、確実に選挙に負けることが分かっていたはずだからだ。
さらに、94年の選挙で大勝して首相に返り咲くものの、わずか2年で後任のハンス・ヨーラン・ペーションに首相の座を譲ることになる。
ペーションの政権は、その後10年続いている。カールソンは、組織に帰属することや、その地位に固執することがない人物のように、僕には思える。きっと、彼は市場の評価、つまり有権者の判断を心の支えにしていたのだと思う。それも当面の評価ではなく、中長期にわたる評価を、である。
実は、コンサルティングの世界もこれに似た世界である。基本的には、何が正しいか、ファクトとデータ、分析にもとづいた冷徹な判断がまずはある。一方、そうした判断を実際にクライアント内で実行に移すために、正しいことを伝える場面が訪れる。
どんな組織にもポリティクスがあって、どのように伝えていくか、コンサルタントの腕の見せ所になる。ただ、ややもするとクライアントのポリティクスに迎合しがちになる。ポリティクスから見て正しいことをすることの方がずっと優しいからである。
僕は、正しいことを伝えたいと思っている。それでクライアントから嫌な顔をされて、一旦は付き合いが終わったとしても。いつかきっと、あのときのことを感謝してくれる日が来るに違いない。そう思いながら、僕はコンサルティングを続けている。
大庫 直樹