努力とは、いい成果を出すための行為であって、それ以上でも以下でもない――。成果主義の下では確かに正解かもしれませんが、人や組織の成長を考えてみると必ずしも正しいとはいえないことが分かります。
誰もができない仕事には空振りもある
誰にでもできる仕事は、決まった時間だけ行えば、誰にでも決まった成果が上がります。
しかし「稼げる人」を目指す仕事は、そういうものばかりではありません。むしろ、努力した分だけ成果がすんなり出る仕事の方が少ないものです。
例えば、あなたが初めてお客さんに出す提案書を、何日も苦労して仕上げたとしましょう。しかし、お客さんにその提案は受け入れられず、目指す売り上げが達成できなかった。あなたのショックは大きいでしょう。
「競合会社の資料も詳細に調査し、比較したうえでお客さんのメリットを提示できたはず。なのに、なぜ受け入れられなかったのか。あれだけの努力が水の泡じゃないか」
受け入れられなかった理由は、先方の都合もあるかもしれませんし、思いもよらないトラブルがあったのかもしれません。あなたは悔しくて眠れない日が続くでしょう。
上司は「成果が上がらない努力には、会社は給料を支払わない。早く帰った方が会社のためだ」と痛烈な嫌味を言うかもしれません。しかし、「あの努力は水の泡になった」のかといえば、そういうわけでもないのです。
成果が出なくても努力した事実は残る
努力とは、いい成果を出すための行為ですが、それだけのものかといえば少々違います。なぜなら、成果が出なくても努力した事実は残るからです。採用されなかった提案書を作る上で試してみた工夫は、次回の提案にきっと活きます。
なにしろ、うまくいかなかった経験そのものが、次回以降の仕事へのバネになります。もし努力をせずに同じような失敗していたら、そんな成長のタネも生まれていなかったに違いありません。
また、仕事や取引が人を通じて行うものである限り、仮に結果が出なくても、人が努力を認めてくれるときもあります。提案書を作る努力を上司が見ていたり、取引先が顧客志向の資料を認めてくれたりすることもあります。
「仕事は結果がすべて」と考える人もいますが、何事にも成功と失敗があることを知っている人であれば、「彼・彼女の努力を無にしたくない」と周囲が次のチャンスにつなげてくれることも少なくありません。
努力すれば心の底から成功を喜べる
私も若いころ、編集部の仕事で地道に取材を重ねた記事がボツになってしまったことがありました。あまりのショックに、しばらくふてくされていましたが、あるとき企画が実現して、読者から高い評価を得ることができました。
聞くところによると、私の取材の様子を見ていた先輩が「あいつの努力は特筆モノだ」と上司に掛け合い、企画の復活を働きかけてくれたとのこと。努力すれば誰かが見ていてくれる――。今でもじんわりと思い出します。
こう考えると、高い目標に向けて努力することは「無意味」でも「損すること」でもなく、「稼げる人」になるために不可欠な要素ということが分かります。
以前「仕事に終わりはない。ならば途中でも切り上げよう」と書いたことと矛盾するかもしれませんが、思う存分努力すれば、失敗したときにも悔いが残らないし、次回以降の成功にもつながるし、成功すれば心の底から喜べるし、周囲からの共感も得られるしと、いいことばかり起こるように思えます。
高城幸司
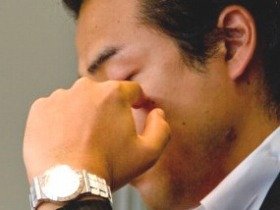



 桑田真澄を桑田真澄が総括する
桑田真澄を桑田真澄が総括する 日本の現状…
日本の現状…