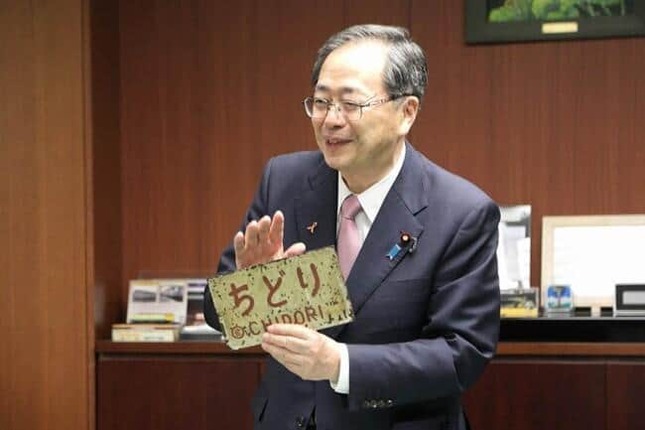2024年秋の総選挙で少数与党に転落した自民・公明連立政権は、立憲民主、日本維新の会、国民民主党の主要3野党と個別に交渉を重ねながら、かろうじて政権を維持している。25年7月の参院選に向けて3野党がさらに政策要求を強める一方で、「支持率が回復しない石破茂首相では選挙は戦えない」と自民党内からも倒閣の動きが出ても、不思議ではない状況だ。
そんななか、自民党と連立政権を組んで23年になる公明党は、「踏まれても、ついていきます下駄の雪」と陰口をたたかれてきたが、立党60年の歴史をたどると、見えてくるものがある。
自民党を政権転落に追いやった過去
故安倍晋三・元首相が、従来の憲法解釈を変更して「集団的自衛権の行使」を認めた時、連立与党の公明党は「平和の党」の立場から強く反対したが、最終的には同意した。安倍氏が政権に復帰して、公明党と再び連立を組んで間もなくの2014年7月のことだ。閣議決定の後に、あちこちでささやかれた。「やっぱり下駄の雪か」。
公明党が結成されたのは1964年。戦後復興を経て間もなくの高度経済成長期に、東京をはじめとする都市部に地方から人口が集中した。急拡大した都市人口を中心に増えた創価学会の信者を基盤に、公明党は東京都議会はじめ国会に勢力を広げ、69年の衆院選では47議席を獲得、第3党に躍進した。
一方で、「政教一致」を批判する書籍の出版に創価学会などが圧力をかけたとされる「言論出版妨害事件」について、社会の批判が広がった。故池田大作・創価学会会長が70年に謝罪。「政教分離」の立場から、公明党と創価学会の組織を明確に分離する方針を明らかにした。70~80年代に、公明党は自民党に対抗して「中道勢力」として、社会党や民社党と連携、83年選挙では衆院で結党以来最高の59議席に。
90年代になると、日本新党の細川護熙氏(首相)を担いだ「8党派連立政権」(1993年8月)に参加。自民党は結党以来、初めて政権から転落した。当時の自民党の機関紙「自由新報」は公明党と創価学会を激しく批判した。後にこの事実を紹介した評論家の佐高信氏は「わずか五年後にその水と油は連立を組んだ。これを野合と呼ばずして」と嘆いた(「自民党と創価学会」佐高信著より)。新進党解党を経て公明党は1999年、小沢自由党とともに小渕恵三政権に参加した。以来、民主党政権の3年間を除き、自公連立が続く。
頼みの創価学会は高齢化
公明党の原点は「庶民の声を代弁する党」であり、政権参加は、食料品の軽減税率など「政策を実現」することが目標だった。何より選挙では「自民党候補への学会票支援の見返りに比例票で自民候補が協力する」という「棲み分け」が構築された。
ただ、創価学会の世代交代が進まず、近年の公明党の比例得票は激減している。2005年衆院選の898万票をピークに、2017年衆院選では700万を割り、昨年2024年秋の衆院選では596万票に。20年足らずで、3分の1にあたる300万票を減らした。24年には新代表になったばかりの石井啓一氏が埼玉14区で落選して辞任、選挙区では大阪の4選挙区で全敗するなど8議席を減らし、立党直後の1967年(25議席)を下回る24議席に落ち込んだ。23年11月には60年余り会長・名誉会長だった池田大作氏が死去した。
新代表の斉藤鉄夫氏は、「下駄の雪」批判に対してこう言う。「自民に寄りすぎとの批判はある。クリーンな政治という原点に立ち返りたい」。2025年夏の参院選をはさんだ政局は、政権交代から大連立まであらゆる可能性があると言われる。公明党は生き残りをかける。
(ジャーナリスト 菅沼栄一郎)