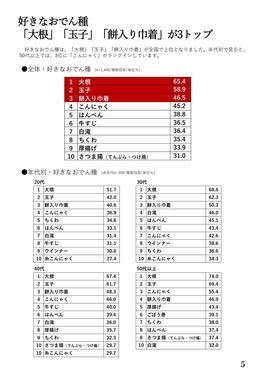「おでん」にも物価高騰の波が押し寄せている。2025年1月23日付のHBC北海道放送の報道によれば、おでん種を総務省の消費者物価指数と照らし合わせると、大根は5年前から43.5%上昇。ちくわ、たまごも26.5%も上昇している。こんにゃくや昆布、さらには出汁に使うかつお節も高くなっているという。
贅沢な味になりつつあっても「不動の人気」
しかし、物価高騰の中でも、おでんの人気は不動の地位を保ったままだ。
食品メーカーの紀文食品(東京都中央区)が発表している「紀文・鍋白書データ」には「鍋喫食率ランキング」が掲載されており、最新の2024年調査版で堂々1位に輝いたのが、おでんだ。
調査を始めた1997年以来、「鍋喫食率ランキング」におけるおでんの地位は揺るがず、26年連続でトップの座を守る絶対的な存在である。
どういうときにおでんにするか。そのランキングの1位が「寒い時」、2位「体を温めたい時」、3位「季節感を感じたい時」である。
なぜ、人はおでんを求めるのか。
独立行政法人農畜産業振興機構のウェブサイトでは、おでんが愛される理由として「自由度の高さ、懐の深さ」を挙げている。
例えば、関東はかつおだしを効かせ、濃口しょうゆで味付けをする。名古屋ではみそで煮込む。おでん種も関東ではちくわぶ、関西では牛すじが親しまれるといった地域性がある。様々な楽しみ方がある。
時代とともに様々なおでんが楽しめるようになった。ソーセージ、チーズ入り巾着など洋風の具材が登場し、豆乳や カレー、トマトベースなどのバラエティ豊かな鍋つゆも珍しくない。
おでん種の幅が広がり、味付け、食べ方も好きなようにできる。この懐の深さはおでん以外の料理には見らない。 また、材料やだしが手に入りやすく、誰でも調理出来て失敗がない。
先のHBC北海道放送の番組では、「値段が上がっても、おでんを食べますか?」と街頭で質問をしている。その答えは「やっぱり食べるかな、日本人なので」。ちょっとやそっとのことで人気は揺らがないようだ。
(J-CASTニュースリサーチ班 大山雄也)